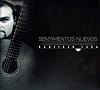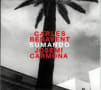ご無沙汰してました。
ニュースブログ、フラメンコ最前線にかまけて、こっちにはとんとご無沙汰でございました。申し訳ございません。
その間にたまったCD、DVDなど、少しずつでもご紹介していくつもりでございます。
それにしても。
折からの不況、経済危機、インターネット配信の影響などで、フラメンコの新譜。めっきり数が減りました。それだけ切磋琢磨したいいアルバムも多く、確率的にいいアルバムに当たることは多くなってきたかも? しょーもない、と、放り出してしまいたくなるようなアルバムに当たることは少なくなりましたね。
サンティアゴ・ララ「センティミエントス・ヌエボス」も、若いギタリストのフラメンコ愛、ギター愛を感じられる1枚。なんといってもこの人、自主制作しちゃってるんですから。それもアフィシオナードに毛がはえた、って感じの人ではありません。ばりばりのプロ。
メルセデス・ルイスの旦那様で、彼女との共演も多いけど、ソロでも活躍している人です。
先のヘレスのフェスティバル期間中にアルバム発表記念コンサートを行ったのですが、私は行くことがかなわず。で、今になりました。
巧いです。
最近の若い人は(←こういう言い方がすでにおばさん)皆巧いですが、その中でもとくに巧い。
1984年生まれというから今年28歳(わ、もうそんな年に)。ですでに2枚目のアルバム。同年代の中では圧倒的に早いですね。
若いだけあって、やはり音が一杯につまっている感じがあって、静寂や静止を音楽にするには至ってはいないけど、センスはいい。しょっぱなの早いシギリージャスなんてかっこいい。最近、こういうの多いですね。視覚的な感じ。やっぱ踊り伴奏やってて、その中で生まれて来るものだからかな。
個人的には、ビセンテの影響がすごく大きいと思います。文法だけでなく、パルマやハレオまでまねしてるのがほほえましい。ビセンテってやっぱすごくて、え?ってないうような人にまで影響与えているんだよね。それはやっぱ彼が、それまでにはなかった文法をつくりだしたからだろうな。ビセンテに似ている、ってのはやっぱ、マノロ・サンルーカルの第2ギターをビセンテの何代か後につとめたこともあるんだろうか。ビセンテがマノロの影響を受けているように。。。
最後の曲とかはビセンテ経由のパット・メセニーかもしれない。
カンテではミゲル・ラビ、ダビ・ラゴス、ロンドロ、ヘスース・メンデスとヘレスの中堅がそろって参加。カンテファンにもいいかもしれません。