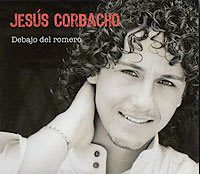昨年の
「モレンテ・フラメンコ」につぐエンリケ・モレンテの新譜。
今回もかつてのライブ録音とスタジオ録音が混在。
ライブは84年、マドリードのフェスティバル、クンブレ・フラメンカでのものから94年グラナダ国際音楽舞踊祭でのものまで7曲。あとの3曲がスタジオ録音。
なんといってもすごいのが1曲目。
94年グラナダ国際音楽舞踊祭で、エンリケがマノロ・サンルーカル、マリオ・マジャと共演したときのもので、そのオープニングのカバーレス。
三人の名を紹介するマリオの声ではじまり、
「タウロマヒア」のオープニングを思い起こさせるマノロのギター、
そこにかぶさるエンリケの伝統をきちんとふまえながらもところどころに
モレンテ流のアレンジが加わる熱唱。
そして見事なサパテアードが。
この公演、私は実際に観ていたので思い出しました。
マリオの十八番、椅子に座ってのあのサパテアード、
あまりに音がきれいなので後で聞いたら椅子にマイクが仕込んであったそうな。
タイトルのトレス・カバーレスは、3人のフラメンコ通という意味もあり、
現代フラメンコを代表する3人の共演はフラメンコの歴史に残る出来事だったのだなあ、といまさらながらに思ったり。
2曲目はスタジオ録音、パワフルなフィエスタ・ポル・ブレリア。
どんなに落ち込んでいるときでも元気がでそうなくらい
エネルギッシュで明るく楽しい。
とっても今風なニュアンスもあるのがエンリケぽい?
それと抜群の相性のギターはモレンテの義弟(奥さんの弟)であるモントジータ。ホアキン・コルテスと一緒に何度も来日しているのでご存知かな。
3曲目はナナス・デ・ラ・セボージャ。
スペインを代表する詩人の一人、ミゲル・エルナンデスの有名な詩を歌ったこの曲はラファエル・リケーニ伴奏で。
リケーニの天才がエンリケのしっかり詩をきかせる歌に寄り添う。
エンリケはロルカも多く取り上げているけど、いつもきちんと詩が聞こえるように歌う。これって大切。
曲優先で詩がききとれないような人もけっこういるけどね。
ベースはパコ・デ・ルシアのグループで活躍中のアライン・ペレス。
しっとりと落ち着いた1曲。
4曲目のマラゲーニャ、5曲目のカーニャ、ポロは1989年の録音。
伴奏はモントジータ。この頃の彼の伴奏はすごくまっすぐ。
カーニャの声には彼が伝説のタブラオ、サンブラでの同僚で
カーニャを得意としたラファエル・ロメーロの響きも感じられます。
6曲目はティエント。ロルカの詩をうたった、これもエンリケの十八番。
89年の録音です。これも伴奏はモントジータ。
後ろに引っ張られるような、ティエントらしいティエントです。
7曲目のソレアは90年のビエナルでの録音。これも観てるな。。。
ペペ・アビチュエラの伴奏がめっちゃいいです。
8曲目のロンデーニャ、ハベーラはエンリケの名唱もさることながら
観客のオレ!がすばらしい。
そういえば最近、こういう、見事なオレ!を聞きません。
1989年、マドリードでの録音。
9曲目のソレアは84年のクンブレでの録音。声が若い!
最後のマルティネーテ、トナーも8曲目と同じときの録音。
でやっぱいいところにオレがとぶんですね。。。
観る方のアルテ、という感じ。
こうしてエンリケの軌跡をおっていくと
彼のすごさがよけいにわかるのではないかな?
モデルノということで敬遠気味の人も一度は聴いてみることをおすすめします。