鹿児島県曽於市恒吉
4月に鹿児島の曽於市内を車で走った際に、
「そういえば…」
と急に思い出して、岩川から恒吉(つねよし)まで遠回りして立ち寄ったのがこの石橋でした。
案内板には「恒吉太鼓橋」と書かれています。
この橋のすぐ西側には恒吉城(日輪城)という城跡があって、かなり規模の大きな城跡なのですが、やはり南九州によく見られる、シラスの切り立った崖に囲まれた曲輪がいくつも集まっているタイプの城です。
その城跡の堀切が何十年か前までは道として利用されていて、その道がちょうどこの橋を経て東のほうへと続いていたそうです。
私は8年ほど前、この近くまで仕事でよく来ていて、その際に隣の新しい橋からよく眺めていたのですが、先日ふと、すぐにも崩れ落ちてしまいそうな感じであったのを思い出して、この石橋はいったいどうなっただろうかと立ち寄ったのです。
この石橋が架けられたのは寛政2年(1790)のことで、218年も前の話です。松平定信による寛政の改革…の頃ですが、年表を見てみると「人足寄場を江戸石川島に設置」とあり、あの、火盗改めの鬼平が活躍した時代ということになります。
(とはいってもなかなか想像できないのですが…)
いま、川を挟んでこの橋の両側に道はほとんど残ってはおらず、すぐ近くには新しく作られたアスファルトの道が新しい橋を通って続いています。
ただ、最近になって修復されたようで、案内板も新しくなっていました。
ここだけ時間に取り残されたような雰囲気ですが、いま人々が利用している多くの橋があちらの岸とこちらの岸を繋いでいるものであるように、この石橋はここでこうして昔と現在を繋いでいるのかもしれません。

長さ15.5メートル、幅は2.8メートル。県内では4番目に古い石橋だそうです。

にほんブログ村」歴史ブログランキングに参加しています
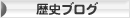
4月に鹿児島の曽於市内を車で走った際に、
「そういえば…」
と急に思い出して、岩川から恒吉(つねよし)まで遠回りして立ち寄ったのがこの石橋でした。
案内板には「恒吉太鼓橋」と書かれています。
この橋のすぐ西側には恒吉城(日輪城)という城跡があって、かなり規模の大きな城跡なのですが、やはり南九州によく見られる、シラスの切り立った崖に囲まれた曲輪がいくつも集まっているタイプの城です。
その城跡の堀切が何十年か前までは道として利用されていて、その道がちょうどこの橋を経て東のほうへと続いていたそうです。
私は8年ほど前、この近くまで仕事でよく来ていて、その際に隣の新しい橋からよく眺めていたのですが、先日ふと、すぐにも崩れ落ちてしまいそうな感じであったのを思い出して、この石橋はいったいどうなっただろうかと立ち寄ったのです。
この石橋が架けられたのは寛政2年(1790)のことで、218年も前の話です。松平定信による寛政の改革…の頃ですが、年表を見てみると「人足寄場を江戸石川島に設置」とあり、あの、火盗改めの鬼平が活躍した時代ということになります。
(とはいってもなかなか想像できないのですが…)
いま、川を挟んでこの橋の両側に道はほとんど残ってはおらず、すぐ近くには新しく作られたアスファルトの道が新しい橋を通って続いています。
ただ、最近になって修復されたようで、案内板も新しくなっていました。
ここだけ時間に取り残されたような雰囲気ですが、いま人々が利用している多くの橋があちらの岸とこちらの岸を繋いでいるものであるように、この石橋はここでこうして昔と現在を繋いでいるのかもしれません。

長さ15.5メートル、幅は2.8メートル。県内では4番目に古い石橋だそうです。

にほんブログ村」歴史ブログランキングに参加しています


































