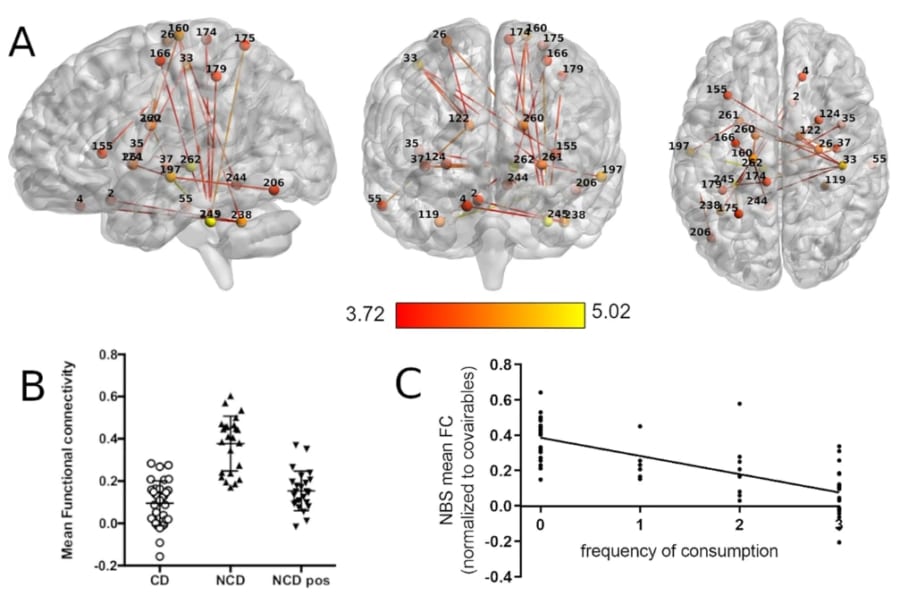娘の金遣いが荒い…父親が気付き発覚 中3女子に複数の男性客とわいせつ行為させる 男女2人逮捕
岐阜県内で去年、中学3年の女子生徒に、18歳未満と知りながら複数の男性に対し、わいせつな行為をさせたとして31歳の男と24歳の女が逮捕されました。
逮捕されたのは、岐阜市の自営業・藤井隆之容疑者(31)と岐阜県垂井町のアルバイト・田島えり容疑者(24)です。
逮捕されたのは、岐阜市の自営業・藤井隆之容疑者(31)と岐阜県垂井町のアルバイト・田島えり容疑者(24)です。

藤井容疑者らは岐阜県内で去年4月から6月にかけて、中学3年の女子生徒(当時14)に対し、18歳未満と知りながら複数の男性客に対してわいせつな行為をさせた児童福祉法違反の疑いが持たれています。
3/16/2020
警察によりますと、出会い系サイトを通じて女子生徒と知り合った藤井容疑者らは、別の出会い系サイトで隠語を用いて女子中学生とわいせつな行為ができる旨の書き込みをしていたということです。
藤井容疑者らは申し込みのあった複数の男性客のもとに女子生徒を車で送り届け、客から支払われた現金の一部をマージンとして受け取っていたということです。
去年6月、女子生徒の父親(40代)が娘の金遣いが荒いことを不審に思い、岐阜北署へ相談に来たことで事件が発覚しました。
警察は藤井容疑者らの認否を明らかにしておらず、余罪や共犯者がいないか調べています。
警察によりますと、出会い系サイトを通じて女子生徒と知り合った藤井容疑者らは、別の出会い系サイトで隠語を用いて女子中学生とわいせつな行為ができる旨の書き込みをしていたということです。
藤井容疑者らは申し込みのあった複数の男性客のもとに女子生徒を車で送り届け、客から支払われた現金の一部をマージンとして受け取っていたということです。
去年6月、女子生徒の父親(40代)が娘の金遣いが荒いことを不審に思い、岐阜北署へ相談に来たことで事件が発覚しました。
警察は藤井容疑者らの認否を明らかにしておらず、余罪や共犯者がいないか調べています。













 コーヒー常飲者はコーヒー脳になる / Credit:Depositphotos
コーヒー常飲者はコーヒー脳になる / Credit:Depositphotos