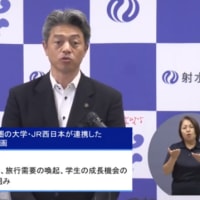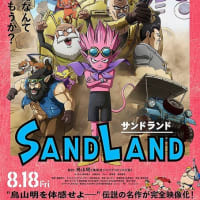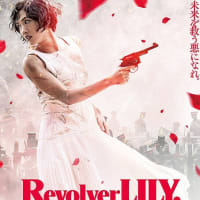以下引用 毎日新聞Web 2016年2月18日  http://mainichi.jp/articles/20160218/ddm/004/070/025000c
http://mainichi.jp/articles/20160218/ddm/004/070/025000c
日本の法律で手話は「言語」と位置づけられているのをご存じだろうか。障害者基本法3条には「言語(手話を含む)」とのくだりがある。
それまで言語といえば、日本語のみを指し、手話は「手まね」とさげすまれ、言語とみなされていなかった。耳の聞こえない子供たちが集うろう学校では、手話の使用を禁止し、口の形を読み取る、いわゆる口話法による教育が長い間、続いてきた。
今では多くのろう学校が日本語のコミュニケーション手段として「手話」を活用するようになってきた。言語学、教育学などの世界で手話を言語として認知、理解する人が増えてきているのは心強い。
それでも、言語として手話を教育するシステムを取り入れているろう学校は一部にとどまる。手話を言語として「獲得」する環境整備はなお、進んでいない。
労働、医療等の生活場面で手話を使用する環境の整備は、著しく立ち遅れている。例えば手話を第1言語として使うろう者のほとんどは、手話を使用する機会がない状態で働いている。就職面接や職員会議の場で手話通訳者が同席することは極めてまれだ。諸外国では報道等の番組に手話の挿入が多くみられるが、わが国ではほとんど見られない。
そうした状況下で、地方では手話を使用できる生活・労働環境や手話を習得する教育環境の整備を進める「手話言語条例」を制定する動きが活発になっている。鳥取県が最初に踏み切り、現在は30以上の県や市町が制定している。多くの自治体が登録手話通訳者の増加、学校での手話教材の導入、遠隔手話通訳システムの導入等を図っている。
手話が言語としての一つの文化を形成していることを知り、条例が自分たちの町を皆が共に暮らせる町にしようと考える契機になったこと、手話言語を通してコミュニケーションの大切さを学ぶことができるようになったなどの報告が寄せられている。条例制定は共生社会の実現に大きな成果をあげていると言えよう。
こうした動きをさらに定着させるためにも、「手話言語法」の制定が強く求められている。
ろう児やろう者が手話を言語として自然に習得でき、手話を自由に使用できる環境整備を進め、手話の普及を図る基本法だ。すでに全国の都道府県や市町村議会の99・9%の議会が早期制定を求める意見書を国に提出している。
2020年には東京オリンピック・パラリンピックが開催される。共生社会は多様な人が共に生き、支えあう社会であり、それは多様な文化、多様な言語、多様なコミュニケーションを受け入れる社会でもある。
豊かな言語やコミュニケーションが織りなす共生社会の形成に貢献する「手話言語法」の一日も早い制定に幅広い理解と協力を願いたい。
■人物略歴
ひさまつ・みつじ
電機メーカー勤務を経て全日本ろうあ連盟に。全国手話研修センター理事、日本障害者スポーツ協会理事などを兼任。
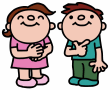 「手話言語条例」が大事ですが、「手話言語法」の方がもっとも重要ですね。
「手話言語条例」が大事ですが、「手話言語法」の方がもっとも重要ですね。
「手話言語法」について、再度学習してみましょう!
日本手話言語法案が作成されました。
(目的)
第1条
この法律は、日本手話言語(以下「手話」という。)を、日本語と同等の言語として認知し、もってろう者が、家庭、学校、地域社会その他のあらゆる場において、手話を使用して生活を営み手話による豊かな文化を享受できる社会を実現するため、手話の獲得、習得及び使用に関する必要な事項を定め、手話に関するあらゆる施策の総合的かつ計画的な推進を図ることを目的とする。
(定義)
第2条
この法律において、「日本手話言語」とは、日本のろう者が、自ら生活を営むために使用している、独自の言語体系を有する言語を指し、豊かな人間性の涵養及び知的かつ心豊かな生活を送るための言語活動の文化的所産をいう。
2012年5月27日、千葉聴覚障害者センターにて全日本ろうあ連盟東京事務所長・久松三二氏による講演会が行われました。