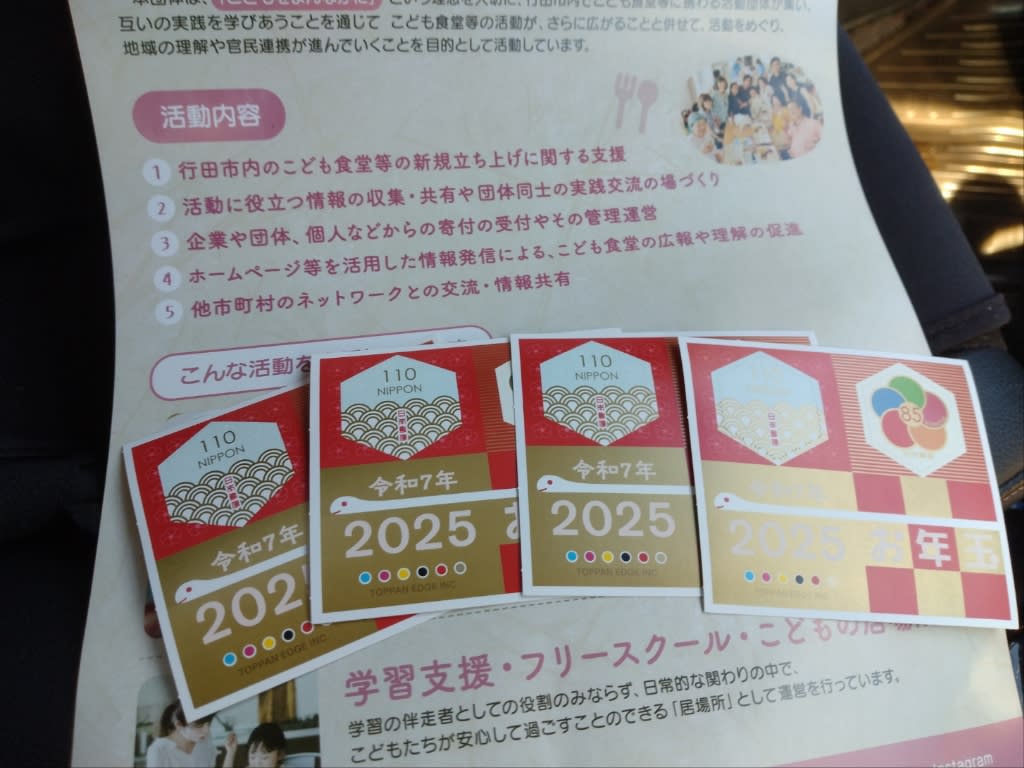奥さんの誕生日を迎えました。結婚して21年ですが、23歳の時からお付き合いしていましたので24回目のお祝いになります。

コーヒー好きですので、毎年コーヒーで乾杯します。これからもどうぞよろしく。







旧大里村玉作の地名は古代勾玉や管珠が製作された場所で、近くには船木遺跡からの出土品として見られる。往古玉造部が住んでいたと考えられており、近くを流れる荒川支流和田吉野川の治水に苦心してきた。

現在玉作水門が建てられその治水の役を果たしているが、荒川流域の氾濫は古くから地域を悩ませていて、この八幡神社の社殿も水害を避けるために水塚の上に建てられている。

『郡村誌』の記述によれば往古は「玉作神社」と記されていて古代の玉造部が信奉した神社ではないかと思われる。玉造神社から八幡神社へと改称した時期や理由は明らかではないが地内にある玉泉寺は源頼朝の弟、源範頼が創建した慈眼院を再興したものとの伝承があることから源氏の台頭にともなって八幡神社となったものと推測される。御祭神の誉田別命は戦の神とされ、戦時下では出兵兵士の武運を祈る八幡参りが盛んにおこなわれたという。大戦後現代となってそうした信仰から五穀豊穣や家内安全が主に祈願されるようになっている。


境内末社の石碑がしっかりと祀られていて、過疎化に伴う氏子の減少からか、境内の見回りも警察のパトロールに頼るところも見られる。

一方境内地脇には広々とした敷地にたくさんの桜が植樹されており、氏子の神社に対する思いが伺われる。植樹20年前後のものが多く、幹も枝もまだ若々しさが残っている。もししばらくすれば美しい桜の花が咲き誇るのだろう。

日本海側の大雪のニュースが伝えられていますが、最強寒波と呼ばれる低気圧もやや弱まり、雪解けの気温となるようです。暦の上では今年は二月三日が立春でした。四年ほど前に125年ぶりの春節分が2月2日になって以来、今後は春の節分が二日になったり三日になったりするようですね。旧暦では立春に近い新月の日を元日としていたそうです。寒が明けて少しづつ春の兆しが見え始め、一年のスタートにふさわしい季節です。
立春の日にその年の恵方(今年は西南西)の井戸から汲んだ水は「若水」と呼ばれ一年の邪気を祓う神聖な水と信じられてきたそうです。のちに元旦早朝の組み水になり、神棚にお供えして飲食に使う風習が残されるようになりました。
今では恵方といえば太巻き寿司ですが、巻きずしを食す風習はそれほど古いものではないようです。商魂はなはだしいところではありますが、今ではすっかり立春前の行事となっています。
春の語源は様々ですが万物が「発る」だとか草木の芽が「張る」天候が「晴る」など命の芽吹きを感じるところです。ではなぜ厳冬の時季に「春立つ」のでしょうか。

古来中国では陰陽五行の思想から「陽極まって陰に転じ、陰極まって陽に転ず」と考えられてきました。
寒さも極まると暖かさに転じる
寒の極みこそ春の始まりだと昔の人は感じ取ったのです。