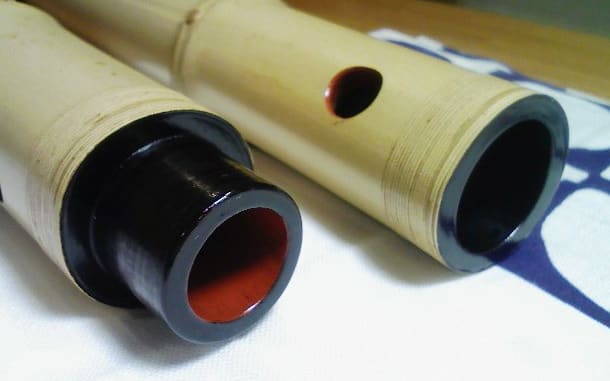今朝、初めての方からお電話がありました。
着信の電話番号から、関西からと分かったのですが、
「お店はやっていますか?」との事。
当ブログをご覧頂いて、堺にもお店があると誤解されたみたいです。
私の書き方が悪かったでしょうか、、、
大阪(堺)には、出張で参りますので、常時居る訳ではありませんので。
申し訳ありません。。。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
そのお電話の内容なのですが、、、
中継ぎゆるみの補修に関してのお電話。
「とりあえず、マニキュアを塗ったらいいですか?」
と言われたのですが、出来れば止めておいてくださいと申し上げました。。
中継ぎの部分は、竹で出来ており、接合の固さ具合を、漆を塗って調整しています。
ですので、漆以外の別のものを塗るのはあまりよろしくないですし、ヘタにすると、抜けなくなったり、という可能性も無きにしもあらず。
ぜひ、専門家にお任せになることをオススメします。
ちなみに、私の所では、漆を塗り重ねるだけで大丈夫なくらいでしたら、5000円程の費用です。
直接お越しいただけなくても、遠方からでも、郵送で受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。
尺八は、琴や三味線のように、糸を変える必要もないですし、破けて張り替えないといけない皮の部分もありません。
とてもメンテナンスの楽な楽器ですが、中継ぎはそういう意味では、一番手入れが必要な部分かもしれません。
着信の電話番号から、関西からと分かったのですが、
「お店はやっていますか?」との事。
当ブログをご覧頂いて、堺にもお店があると誤解されたみたいです。
私の書き方が悪かったでしょうか、、、
大阪(堺)には、出張で参りますので、常時居る訳ではありませんので。
申し訳ありません。。。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
そのお電話の内容なのですが、、、
中継ぎゆるみの補修に関してのお電話。
「とりあえず、マニキュアを塗ったらいいですか?」
と言われたのですが、出来れば止めておいてくださいと申し上げました。。
中継ぎの部分は、竹で出来ており、接合の固さ具合を、漆を塗って調整しています。
ですので、漆以外の別のものを塗るのはあまりよろしくないですし、ヘタにすると、抜けなくなったり、という可能性も無きにしもあらず。
ぜひ、専門家にお任せになることをオススメします。
ちなみに、私の所では、漆を塗り重ねるだけで大丈夫なくらいでしたら、5000円程の費用です。
直接お越しいただけなくても、遠方からでも、郵送で受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。
尺八は、琴や三味線のように、糸を変える必要もないですし、破けて張り替えないといけない皮の部分もありません。
とてもメンテナンスの楽な楽器ですが、中継ぎはそういう意味では、一番手入れが必要な部分かもしれません。