さてさて、和歌山県湯浅町での散策を始めたワタクシは、
醤油の醸造元の建物がある一帯へと歩を進めました
湯浅は我が国の醤油の発祥の地と言われておりまして、
鎌倉時代に中国から伝わった嘗め味噌(現在では金山寺味噌で有名ですな)を作っていたところ、
味噌の中の瓜や茄子からしみ出てくる水分を嘗めてみるとこれがなかなか美味しい。
それが醤油の始まりだそうです。
江戸時代には紀州藩の保護も受けて、湯浅には92軒の醤油の醸造所があったとか
明治以降は藩の保護もなくなり、大量生産をする大手企業の進出もあり…
それでも今も昔ながらの手法で醤油を作っている醸造所が残っています。

風情のある街並みが広がってきました

天保年間創業の醤油屋さんです(1840年代ですよ)


お店の裏側はこうなっておりまして…
この壕を大仙堀というのですが、昔はここに船が入ってきて荷出しをしていたそうです。
「醤油発祥地」の看板に歴史を感じますなぁ


朝早くから、醤油が瓶詰めされていました。
この界隈を歩くと、醤油の匂いが漂っています

重厚な瓦屋根も美しく…

伝統を守り続ける姿には、老舗の誇りを感じました。
かくして、ワタクシもお土産に香り高いお醤油を買って帰りました
湯浅の散策、もーちょっと続きます
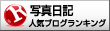 ←ランキングに参加しました。
←ランキングに参加しました。
よかったら「ポチッ」と押してやってください
醤油の醸造元の建物がある一帯へと歩を進めました

湯浅は我が国の醤油の発祥の地と言われておりまして、
鎌倉時代に中国から伝わった嘗め味噌(現在では金山寺味噌で有名ですな)を作っていたところ、
味噌の中の瓜や茄子からしみ出てくる水分を嘗めてみるとこれがなかなか美味しい。
それが醤油の始まりだそうです。
江戸時代には紀州藩の保護も受けて、湯浅には92軒の醤油の醸造所があったとか

明治以降は藩の保護もなくなり、大量生産をする大手企業の進出もあり…
それでも今も昔ながらの手法で醤油を作っている醸造所が残っています。

風情のある街並みが広がってきました


天保年間創業の醤油屋さんです(1840年代ですよ)



お店の裏側はこうなっておりまして…
この壕を大仙堀というのですが、昔はここに船が入ってきて荷出しをしていたそうです。
「醤油発祥地」の看板に歴史を感じますなぁ



朝早くから、醤油が瓶詰めされていました。
この界隈を歩くと、醤油の匂いが漂っています


重厚な瓦屋根も美しく…

伝統を守り続ける姿には、老舗の誇りを感じました。
かくして、ワタクシもお土産に香り高いお醤油を買って帰りました

湯浅の散策、もーちょっと続きます

よかったら「ポチッ」と押してやってください























 FUJI FILM X10
FUJI FILM X10
 FUJIFILM X-E1
FUJIFILM X-E1
 FUJIFILM X-T1
FUJIFILM X-T1
 FUJIFILM X-Pro2
FUJIFILM X-Pro2
 FUJIFILM X-T30
FUJIFILM X-T30





まだ残っているのですね。
なんだか醤油の香りがしてきます。ホント!!
樽はこれは看板かなにかですか?
現役ではないですよね。
じっくりといいものを作る伝統は受け継いでいってほしいですね。^^
みたいな展示がされていました。
さすがに現役ではないですね(^^)
この界隈は本当に醤油の香りがするんですよ。
ぜひ機会があれば訪ねてほしいです。
醤油がない時はスーパーで間に合わせますが
たまには昔ながらに丁寧に作られている
老舗のお醤油はいいものですね。
今は、今井町で買ってきたものを使っています。
それにしても前記事に続き、いい街並み。
樽の写真も格好いいですね。
これは行きたいですね~。
昔の栄華を忍ばれるような・・・
「山中油店」でごま油を
今回は「角長」でお醤油を…
料理を作るのがけっこう好きなので
いい調味料があると気合いが入ります(^^)
今井町に行くと必ずお揚げさんとお豆腐を
買って帰るんですよ。
壕でたくさんの船が荷積みをしていました。
その時代には戻れませんが
醤油の味も作り方も
その時代と変わっていないでしょうね。
千葉県にも醤油の町がありますが。
近代的な工場なのでこんな味のある風景は
廃れていますね。
お醤油の発祥の地!何事も興味を持ってこそ発明発見があるのですね♪
上澄みを嘗めていなければ美味しいお醤油が生れていなかったかも・・・主人は醤油に目が無いですよ^^
大八車に積まれた醤油樽が時代を感じますね。
長閑な風情ある町中に一つ一つ愛情こもったこだわりが伝わるようです。醤油ひとつでお料理の味が変わりますから。日本人としてとっても大切な味だと改めて感謝しながらいただきたいですね。^^
キッコーマンのような大手企業にはない
味わいがありました。
醤油もいい香りです(^^)