言い伝えに依れば、源氏が壇ノ浦で平氏に勝ち、鎌倉へ凱旋した武将らが
戦勝を祝って踊った踊りが当地へ伝わり「鎌倉踊り」と称されていた

その後、江戸時代に大干ばつがあった時、農民が一心に氏神様の前で
雨乞いをして踊ったので、「雨乞い踊り」に改称され
更にその後は、豊作を感謝して踊った事もあって、「豊年踊り」に改称されたが
一時期廃れてしまい、現在では「谷汲踊り保存会」がその伝統を伝えており
1958年県の重要無形民族文化財・第1号に指定されている

長さ約4mの竹を半分に割り、これを2~30本の扇の骨の様な形に纏め
これを数色の和紙で彩り、鳳凰の羽根に見立てた「シナイ」を背中に背負い
胸には、直径約70cmの太鼓を抱え、シナイを捻りながら勇壮に踊る

当日は、時々強い風が舞っていたので、駐車場で行われた時は
シナイが強い風に吹かれて、シナイ同士が絡み、踊りが出来ない状態になり
踊りの途中で、この場所での「谷汲・豊年踊り」は終了となってしまった
谷汲・豊年踊りの最後は仁王門前で行われたが、時間が無くて
爺やは見る事が出来ず、後ろ髪を引かれながら帰ってきた


< <
<
 <
< トランジションのタグはどんぐり様からお借りしました ありがとうございました
トランジションのタグはどんぐり様からお借りしました ありがとうございました 












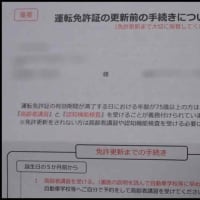



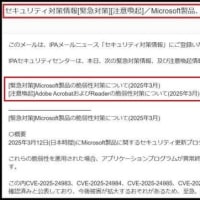

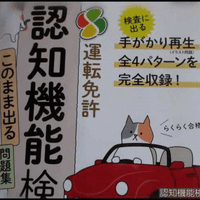

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます