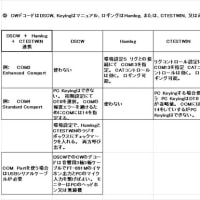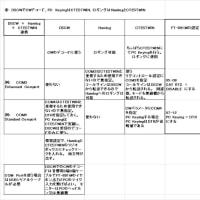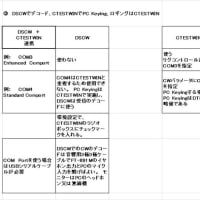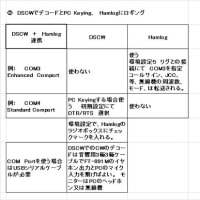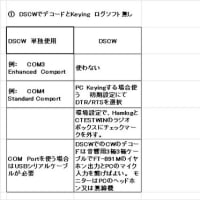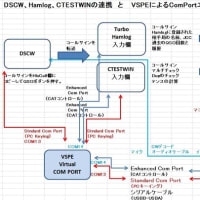台座とロッドの工作
この部分の工作の肝は、電鍵使用中にロッドが左右に動かないようにすること。
工具のΦの誤差
ドリルなどの穴あけ工具には許容誤差というのがあって、例えばΦ8㎜のドリルは、実際jにはΦ7.98㎜くらいの太さになっている。 しかし、実際に穴あけすると、ボール盤や卓上フライス盤にも回転誤差があってΦ8㎜+アルファの穴が開くことになる。 従って、Φ8㎜の丸棒をΦ8㎜のドリルの穴に入れるとゆるくなるのが常である。 これらの誤差があっても組み合うような工夫をすることが必要になる。 丸棒にローレットをかけて穴に圧入するのはこのためである。
心棒中央部にローレット加工をしてロッドの穴に圧入する。 使っている間にゆるくなることも考慮しΦ3㎜のネジピンでも抑える。
真鍮の心棒のベアリング穴への接続は、やはり圧入する。 心棒の端にもローレット加工をする。 ベアリングの台座へのセットだが、ここは圧入が難しいので、ここもΦ3㎜のネジピンで押さえる。 Φ16mmの穴はゆるゆるになりましたのでネジピンが必須です。 他に、通し穴を空け、中央を割って両側からネジで締める方法もありますが、Φが大きいのでネジピンにしました。
ロッドの加工
支点を中心に前後で重力がバランスするように前部を半分にカットした。 メタルソーで半割にカット。
さらにはカット部に10㎜置きに飾り穴を5つあけた。 うち2つの穴は上接点用(位置を変えられます)他は飾りの意味と配線を通すためです。
接点はニッケルシルバーをM4のダイス加工をし、上下ともやはりニッケルシルバーのナットで長さを調整の上、ロッドと台に締め付けて固定している。
上部接点はターミナル経由で台裏から来る配線をY端子で接続、ポリエチレン(まな板から削り出し)の丸台座で絶縁している。
丸台座は、外側にM6のネジ、内部にM4のネジを切ってあり、ロッドに空けたM6用のネジ穴に下からねじ込むようにしてあります。 内部にM4の上接点(ニッケルシルバー)のネジをねじ込みます。
ロッドに空けた飾り穴に配線を通している。 下部接点は台裏でもう一つのターミナルと配線で繋いでいる。 下部接点は上方向へは調節可能だが、最下位位置にほぼ固定。 電極はすべてニッケルシルバーで製作した。
エアピストン
バネが見当たらないことにお気づきでしょうか? ロッドの右下に四角い真鍮金具が見えるでしょう。 これはエアピストン・・・バネの代わりです。 金具の下中央にΦ6.5㎜の穴が開いていてその中にΦ6.35㎜の2つのネオジウム磁石を入れて反発させています。(NS-SN または SN-NS で向き合わせる)。 その上にニッケルシルバーのピストンを乗せ、その先端が真鍮の抑え金具の中央から上に出てロッドを浮かしています。 100均のネオジウム磁石だが、かなり強力です。 磁石は110円で8個入っています。
仮に磁石の磁力が雑音の原因になるようなら、ピストン穴の中にちょっと強めのバネ(ボールペンのバネ等)を入れれば簡単に変更できます。 でも、いまのところkEY-Soundからはノイズ音はでていません。
空気穴はなぜ必要かというと、ネオジウム磁石とピストンは穴とギリギリの大きさで上下移動できるようにしてあるのですが、空気による抵抗を受ける。 密室から空気圧を抜くために横穴を空けてあるのです。
つまみはブビンガを切り出して削りました・・・ちょっと小さ目でく少し打ちにくいので、作り直す予定。 鍋蓋のつまみを100均で買ったが、でかすぎてこの電鍵には合わなかった。
ロッドの後ろには、上下接点の間隔を調節するためのM4ネジが台から出ています。
打鍵中に台が動くのではないか、とシリコン製のクッションを買ってあるが、クッションなしに強く速く打鍵しても台は微動だにしません。 これは、設計上、つまみの位置を台の内側としたことで、テコの原理で台が浮き上がることがないため、と、真鍮の台座が重いことが貢献しています。
暇を見つけて木の台は漆で塗装する予定。 贅沢でしょう。 ついでに真鍮にはバフをかけて光るようにしたいですね。 でも、すぐに酸化被膜に覆われて現状のような色に戻ります。
モールス符号発信練習機、Key-Soundと、My電鍵を早速繋いでみました。
う~ん、結構いいね~。 接点は全く問題なく良い音を出します。ジージーといった雑音は全く入りません。 接点が閉じるときだけカチカチという音が出ます。 ほかの音は全く出ません。
接点間隔をできる限り小さくすると、Youtubeで見たOM(Old Men、先輩)の打鍵と同じような感じでカチカチと打てます。 Key-Soundを聞きながら打鍵してみたが、長点、短点ともに、自分の頭の中でよっぽどけじめをつけた上で打たないと、歯切れのよいモールス符号となりません。 特に短点は乱れやすいですね。 練習あるのみ・・・
最初は接点間隔は少し大きめにあけて、ゆっくり、きっちりと打鍵できるようになってから間隔を小さくして早く打てるようにしよう。
今日からは、発信の練習です。 ボケ防止、ボケ防止・・・CQ CQ・・・