
食べ物一般もそうだが、お酒の嗜好も時とともに変わる。私は根っからの日本酒党で、自慢にもならないが、かれこれ半世紀以上ほとんど毎日いただいてきた。
それが、以前は夏は冷酒、冬は熱燗と決まっていたのに、一時期、季節にかかわりなく年中熱燗、最近は年中冷酒である。なぜそうなったか、わからない。
とにかく、毎日のことだから、お酒とどう付き合うかは一生のテーマである。おいしいお酒を楽しく飲みたい。お酒をたしなむ人ならだれでもそう願っている。旅をすると、〈うまい地酒〉がたえず念頭にあり、巡り合えると、
「東京にはない酒だ」
とぐいぐいいく。何と言っても無名の地酒、掘り出しものがある。
「おれは××しか飲まないんだ」
と有名銘柄を口にする人もいるが、銘酒以上の地酒があるんだよ。
ところで、お酒のことを書く気になったのは、長野県庁が〈お酌禁止令〉を出し、職員に歓迎されている、という気になるニュースを『朝日新聞』(六月六日付)で読んだからだ。とっさに、なんと無粋なことを、と思った。
記事によると、禁止令を出したのは副知事の板倉敏和さんだそうで、この春、県内の蔵元が日本酒のPRに県庁を訪れた時、若い経営者の一人が、
「最近はお酌を嫌う若者も多い」
と漏らしたのがきっかけだった。高級官僚出身で海外勤務の経験もある板倉さんはかねてから〈お酌文化〉に疑問を抱いていたこともあって、年度替わりの幹部送迎会で、
「手酌で自分のペースで飲みましょう」
と呼びかけ、禁止令となった。若い職員の間では、
「お酌して回らなければとか、杯を空けなくてはというプレッシャーがなくなった」
などと好評だという。上司と部下が酒席をともにすることが多い役所や企業社会では、お酌禁止になったほうが、ことに若い部下たちは気楽に飲める。だが、気楽に、というのはそんなに好ましいことだろうか。せっかくの酒席だ。注ぎ合いながら、たまには激論があってもいい。
実はお酌を巡り、かつてこんな体験をした。まだ新聞社に在籍していたある春のことだが、人事担当の同僚に、
「新入りの女性記者に取材の心得みたいなこと話してくれないか」
と頼まれて、
「ああ、いいよ」
と気軽に応じ、仲間(男性)を誘い、娘くらいの女性二人の四人で居酒屋に出掛けた。二、三時間の語らい、女性組は割合お酒が強い。
先輩男性がかわるがわるお酌をすることになった。若い女性の手酌は考えられないから、こちらが注ぐのは当然だ。しかし、女性組はついに一度も私たちにお酌をしなかった。途中から、変だな、と思ったが、
「注いでくれ」
と言うわけにもいかないし、あまり盛り上がらないまま終了した。
◇欧米にない日本独特の風習意味合い伝達、手酌は困難
私にとっては一種の異常体験で、しばらく考え込んだ。先輩からご馳走になるのだから、注がれればたまには注ぎ返すのが礼儀であり、普通の人情ではないか。それをやらないのはなぜか。
いくつか推測はできた。第一に、慣れていない。しかし、二人とも一流大学を出ている。学生時代、コンパなどもやっただろうから、酒席と無縁ではないはずだが。
第二に、お酌をするのがはしたない行為と思っている。第三に、希望して席をともにしているわけではないから、お酌サービスなどできないという気負いがあった。第四に、世間知らずのお嬢さん……。
要するに、よくわからない。ただひとつ、私たちの世代に比べて、一般的に若い人たちは感情の交流、気配り、心配りが薄くなっている、と感じる。
だからなおさら、と言ってもいいが、私はお酌有用論である。『朝日』の記事によると、板倉さんは、
「お酌の習慣は欧米にはない。嫌々飲まされるという日本酒のイメージをなくすにも、お酌はいらない」
と感じたという。だが、欧米にない、日本独特の風習だからこそ値打ちがある。日本酒の悪いイメージにつながるお酌の仕方は改めればすむことだ。確かに、手酌で勝手に、のほうが平穏に過ぎる。しかし、人間関係、すべて平板に波風なくしてしまわないほうがいい。
お酌は極めてデリケートな世界である。お酌する側、受ける側、手酌では到底伝わらないものが伝わってくる。どのタイミングで、どんな頻度で注ぐか。相手は注がれるのを歓迎しているか敬遠しているか、それを敏感に察知できるか。同じ酒友でも日によって調子が違うのを嗅ぎとれるか。
酒席はただの歓楽だけでなく情報交換、情報入手の場でもある。相手がどの程度本音を語る気分になっているか、といったことはお酌などの直接的な接触を通じて感じ取ることができる。お互い手酌では、感じるものが少ない。
欧米で昔からやられている〈乾杯の文化〉の淡泊さと違って、〈お酌文化〉は濃密で奥が深い。乾杯のような、やあやあ、の一過性でなく、日本的でこまやかだ。メリットだけでなく、時にデメリットもあるかもしれないが、それがかえって面白い。
いまは使われていないが、かつて、
〈酌婦〉
という言葉があった。下級料理屋などで、お酌のほか売春もしていた女性のことだ。随分前だが、東北の山奥の温泉宿で料金表に〈酌婦料〉と記してあって驚いたこともある。
お酌にはそんなことから、マイナスイメージも多少つきまとっている。しかし、昔のことだ。
日本人が長年、慣習として繰り返してきたことを、若者への甘い態度だけで軽々に禁止しないほうがいい。私なんか、夜ごと、だれかにお酌している。お酌してもらってもいる。生活の一部なのだ。何ごとによらず、禁止はよくない。
<今週のひと言>
<東国原の乱>、ここまできたか。
(サンデー毎日 2009年7月12日号)
2009年7月1日
小父さんは根っからの下戸なんでお酒の楽しさの真髄を知らない。お酒が強い人は羨ましいよね。だけど、もう随分遠ざかっているが、お酌のさしつさされつで話が弾んだ経験もずいぶんある。座敷、宴会、酌婦なんて言葉は始めて聞いたが、そうそう日本の社会からなくならないでしょう。ただ、桜の木の下での酔いつぶれみたいな感じは減ってきたんじゃないかな?






















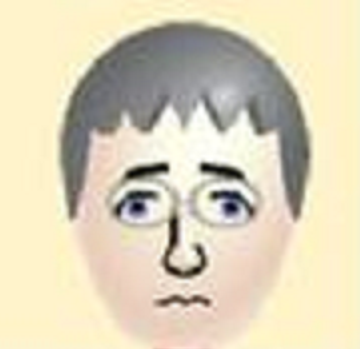




これは、誰のための禁止令?
部下のための?
禁止することで、お酌をしない部下に腹を立てなくて
よくなったから?
何だか、侘しい世の中になりましたね。
酌をしようが、しまいが大人の世界。
酒宴ですよね。
一応無礼講ですよね。(時々失敗する男もいるけど)
まあ、総理大臣周辺でも無茶苦茶になるくらいだから、こんなことを言う人がいても不思議じゃない世の中なのでしょうね(笑)
日本に帰って そんなことに気がつかないかも、、。
お酌っていいものですがね
面白い禁止令 できるんですね
何か こちらにもそんな ちょっと変わった 禁止令があったような、、、。
今思い浮かばないけど、、。
社会人生活遠ざかって、ずいぶんたちますが
私達は、当然でしたね(笑)
職場の宴席はビールとお酒と(最近ではお茶も?)
持って回りました。
順番とか、抜けがないか?気にしたのもです。(
気を張っていたので?酔うこともできず、お酒も強くなりました(笑)
今は、お酒の席は旦那様担当なので・・・。
そうか、アメリカはお酌がないんですね。
ビールの小瓶をラッパ飲みする姿もいつも珍しく
見ています。
宴会では、自分が続けて飲みたい時、手酌では調子が出ないので、先ず他人についで自分のビールのコップやおちょこに他人に入れてもらうのが習慣ですね(笑)。
●Neko★さん
そうか、Neko★さんは宴席の華だったんですね。
こういうコメントを初めてきくので何か新鮮です。
酔払いの集まる場所こそ、女性社員の活躍の場所な
わけなんですね。けっこう大変だ。