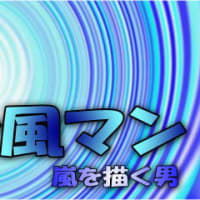その路地裏は、100メートル四方に切り取られた大きな羊羹のように昔のまま取り残され、時間が停止したようだった。
空がほんの少しだけ夕焼けに赤く染まりかけたころ、僕はその古い路地裏を抜け、家に帰ることにした。
いつもなら、こんな時間に薄気味の悪い場所を通ったりしない。
学校から家までの近道とはいえ、こんな時間にここを通ってしまった事を僕は後悔していた。
あたりは薄暗くなってきて、危険で不思議な雰囲気に満たされている。
時折、ヒューッと風が通り抜け、割れた窓ガラスをカタカタと揺らしている。
「ああ・・早く帰ればよかった・・・」僕の心の中は、心細くて小さく縮こまっていた。
さっきより風が強くなってきて、ごみの切れ端や枯葉を巻き込んで路地裏を勢いよく通りぬけていく。
はがれたポスターが幽霊の手のようにパタパタはためいていた。
そんな怖い気持ちが、僕の足を早足にしていた。
サッサッと急いで動かす足音が薄暗い路地裏通りに、他人の足音のように響いている。
こんな気分のときは、歩いても歩いてもここから出られないのではないかと、嫌でもそんな不安な気持ちになってしまうものだ。
カランッ・・・と、何かが落ちるような音が路地裏の奥に響いたので、僕はビックリして立ち止まってしまった。同時に、ニャーと、小さな声がした。
「なんだ、猫かぁ・・・」僕の心は、ほんの少しだけゆるんだ。でも、その時後ろに何か大きな人の気配が感じられた。
僕は、ギクリとして後ろを振り返った!
「うわっ~~~!」僕は、ありったけの驚きの声を張り上げ後ずさりした、そして、一目散に走りだした。
僕の後ろには、真っ黒な巨大なペンギンのようなタキシードを着、ハタハタと黒いマントをなびかせた、見るからに恐ろしげな男が立っていたからだ。
僕は後ろも振り返らず、一目散に走った。
ザッ!ザッ!ザッ!っと、僕のスニーカーの靴音が、無人の路地裏に木霊して、何人もの僕が一緒に逃げているようだった。
数メートルも行かないうちに、さっきの奇怪な路地裏の怪人が、僕の前に立ちはだかった。
頭には大きなケーキのような黒いシルクハットを被り、ギョロリとした輝く目が、心を見透かすように僕をにらんでいた。
とその瞬間、バサッ~~~!!っと、かび臭い大きく真っ黒なマントが僕の上に覆いかぶさってきた。
そして、僕の目の前は真っ暗になった!
一瞬の出来事だった、かび臭い匂いが無くなり、急に周りから賑やかな音がしてきた。
パフゥ~プィ~パァ~!ラッパのような音が遠くから聞こえてきた。
僕は何が起こったのかサッパリわからず、ユックリユックリ目を開いてみた。
そしてそこには、さっきまで居た路地裏が朱色の夕焼けに染まり、在った。
建物は変わりないのだが、さっきとはぜんぜん違った風景の路地裏が目に前に広がっている。
大勢の人たちが活気よく歩き、子供の声が近くや遠くでワイワイ聞こえている。
それはまるで放課後の運動場のようにも思えた。
どこからか味噌汁の匂いがフワァ~と漂ってきて、いい香りだ。
パフゥ~プィ~パァ~!と、遠くから聞こえたラッパのような音が近づいてきて、どこからか女の人の声がした。
「お豆腐屋さぁ~ん!待ってぇ~!」そうすると路地の向こう側から、自転車に大きな車輪の荷台を引っ張りながら、ラッパを首にかけた豆腐屋のおじさんが現れた。
そして、白いエプロンをしたおばさんが、1人、2人と、僕の前を走っていく。
僕は、頭がクラクラして立っているのがやっとだった。
「いったいここはどこなんだろう?わけがわからない!僕は、どうしてしまったんだっ?」混乱した気分で、僕はもう少しで泣きそうだった。
さっき路地裏の怪人に会って、何の理由も知らないまま一瞬のうちにこんな所に来てしまった。
景色は、さっきの廃墟の路地裏と変わらないのに、こんなにも人が一杯いて賑やかだ。
味噌汁の香りや、薪を炊く匂いや、草の匂いもしている。
突然に、棒切れを振り回しながら数人の幼稚園くらいの子供が、僕の横をキャアキャア叫びながらすごい勢いで走り去っていった。
「やぁぁ~い!俊夫ちゃんのバァ~カ!」数人の小さな子が、一人の男の子を追っかけながらからかっている。
逃げている子は、泣きながら追っかけられ走っていった。
「僕のお父さんと同じ名前だったな」泣きそうな気持ちだったが、僕はそんなことを考えていた。
なんだかジッとしていても心が不安なままなので、心細いけど少し歩いてみようと思った。
少し歩いていくと、眼鏡の下がったオジサンのついた古いホーロー看板があった。
もう少し行くと、見たことの無いような形のテレビが白黒のニュースを放送していた。
その隣には、見たことのような駄菓子が売られている小さな店を見つけた。
棚の上に並べられたガラス瓶の中には、いろんな色のお菓子が詰まっている。
美味しそうな煎餅や黒砂糖のついたたっぷり付いた麩菓子は、ビニール袋にも入っていなくって、そのままガラスケースの中に並んでいる。
わぁぁぁ~~~!っと、また、あの子供たちの声が近づいてきた。追っかけられていた一人の男の子が僕の後ろにサッと逃げ込んだ。
続いて数人の子供達が、その子を囃し立てている。
「やぁ~い!俊夫ちゃんの弱虫!」「やぁ~い!」一人の鼻水を鼻からたらした子が、棒切れの先にバッタの死骸を突き刺し、僕の後ろの子供の顔にくっ付けようとしていた。
「ほれほれ!」「死んだバッタだぞっ!」僕の後ろの男の子が、泣けば泣くほど数人のいじめっ子は、調子づいて囃し立てている。
「大勢で、いじめるのは止めろ!」僕は、妙に腹が立って強く怒ってしまった。
「わぁぁ~~っ」「ばぁ~か!」そう叫ぶと、いじめっ子達は、どこかへ走り去っていった。
後ろの子は、まだウェンウェン泣いてばかりで、いっこうに泣き止む様子はない。
「しょうがないなぁ・・・」そう思った僕は、ここの駄菓子屋でこの子にお菓子を買ってやることにした。ポケットの中には十円玉が3個しかなかったので、たいしたお菓子は買えないだろうが、なんとか泣き止んでくれればと、僕は考えていた。
「ごめんくださ~い!」駄菓子屋の店の前で、大きな声で僕は言った。
すると奥の部屋から、店のおばあさんが出てきた。
僕はサイコロの形の箱に入ったキャラメルと、赤いイチゴの形の飴を買い、その子に渡した。
ヒックヒックいいながらも、その男の子は泣き止んだ。
駄菓子屋のおばあさんは、男の子を見ながら言った「また、俊夫ちゃん、泣かされたんだねぇ、もうすぐお母さんがくるから待ってるといいよ」
いつも、この俊夫ちゃんと呼ばれた男の子は、いじめっ子に泣かされているのかもしれないと、僕は思った。
夕日で赤く染まった駄菓子屋のお菓子は、なんだか夢の中のようなお菓子に見えた。
そして、しばらくすると、その子のお母さんがやってきた。
「俊夫!また泣かされたのかい?」そう言うと、その子の頭を軽くコツンと叩いた。
すると、その子は、またグスグス泣きそうになっている。
「あんたが、うちの子を助けてくれたんかい?」おばさんがそう言ったので、僕はうなずいた。
「助けてくれてありがとうね!それから、お菓子もありがとうね!」そうお礼を僕に言いながら、おばさんとその子は路地を歩きながら帰って行った。
後ろ姿を見ていたら、急に僕のおばあちゃんを思い出した。
そうだ、さっきのおばさんは、僕のおばあちゃんにそっくりだった。
お父さんの名前の俊夫と、おばあちゃんにそっくりなおばさん!
「ここは、何十年か前の僕の町だ!そうだ、そうに違いないのだ!」僕は、確信したのだった。
あの路地裏の怪人は、僕を昔の路地裏に連れてきてしまったんだ!
あの怪人の黒い大きなマントはタイムマシーンのようなものなのかもしれない。
なんで僕が連れ去られてしまったんだろう。
あんな時間にこんなところへ来なければよかった・・・・・
後悔の気持ちが、僕の心の中を一杯にしていく。
もう自分の居た町には戻れないと思ったら、僕は急に泣きたくなってしまった。
夕焼けの淡い光が、僕の影を長く長く伸ばして地面に写し出している。
空には、カァカァと烏が寂しげに鳴いている。
すると突然に、僕の長い影にシルクハットの影がスゥーッと重なったかと思った瞬間に、僕はまたあの怪人のカビ臭い大きなマントにスッポリ覆われていたのだった。
バサッ!マントが風を切る音が響いた。
僕の目の前が真っ暗になり、一瞬静かになった。
かと思った瞬間、次には元のあの僕の町に戻っていた。
遠くでは、自動車のエンジンやクラクションの音が小さく聞こえてくる。
周りを見回したが、路地裏の不気味な怪人はどこにも見当たらない。
「ああ、さっきのは夢見たいなもんだったのかなぁ?」そう思いながら、不安な気持ちが無くなってホッとした気分だった。
廃屋だらけの路地裏は、夕焼けに染まって真っ赤になっている。
僕は急いでその路地裏を抜けると、なんだか気になって後ろを振り返った。
するとそこには真っ赤な夕焼けの空を背に、シルクハットを被った路地裏の怪人の長い影のシルエットが、一瞬見えような気がした。
とても恐かった。
でも、今ではあの路地裏の怪人が良い奴のような気がしているのだ。
・・・・なぜって?
昔のお父さんは泣き虫だった。
僕には「男は泣くんじゃない!」と、いつも言ってるくせに、自分は泣き虫だったんだ。
それに、僕には優しいおばあちゃんなのに、お父さんにはちっとも優しくなかった。
でも今は、僕はお父さんやおばあちゃんが、前よりずっと好きになっている。
何故だかわからないけど、さっきみた昔の町が、僕の心を優しくしてくれたのかもしれない。
遠くに見える路地裏は、夕焼けに染まりユラユラと揺れているように見えた。
Copyright (C) Sakai Houichi. All Rights Reserved.