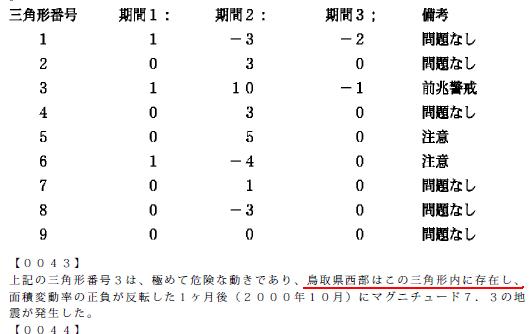東大名誉教授である村井俊治氏が、今年の3月に発生した伊予灘を震源とする地震を予測していたと一部で話題となっているようです。これは本当なのでしょうか?
本サイトでも紹介(こちら)しましたとおり、村井氏は、「昨年の11月頃から今年の3月頃までに南海トラフ巨大地震が起こる可能性が高い」と予測していました。それに対し、3月に発生した地震は、伊予灘の深い地下を震源とするM6.2の地震で、想定される南海トラフ地震とは大きく異なるものでした。これをどう評価すべきでしょうか。
■
村井氏は、「私が南海地震と言ったのは決して南海トラフ地震ではなく南海地方で起きる可能性のある地震を意味します」(村井氏の5月15日twitter)と釈明し、南海地域で地震が起きたのだから的中だと主張しています。
ですが、「南海地域」という広い範囲で良いのなら、最近だけをみても、
・2013年4月13日に淡路島付近を震源としてM6.3(最大震度6弱)
・2011年11月21日に広島県を震源としてM5.4(最大震度5弱)
・2011年7月5日に和歌山県を震源としてM5.5(最大震度5強)
・2010年2月27日に沖縄本島近海を震源としてM6.9(最大震度5弱)
などの強い地震が起きています。M7クラス以上の大地震に限ってみても、2004年に三重南東沖、2005年に福岡県などで起きています。つまり、「南海地域」が揺れる大きめの地震は、非常にコンスタントに起きているのです。
ですので、今回の村井氏のように「11月から3月まで」とほぼ半年もの長い期間をとって、「南海地域が揺れればどこでも的中」だという予想が当たったとしても、統計学的には全く驚くに値しないということが分かります。
■
そもそも、村井氏がtwitterで主張している「私が南海地震と言ったのは決して南海トラフ地震ではなく」というのは、本当なのでしょうか。メディアにおける彼の発言をみてみましょう。
「9月1-7日に、日本全国が異常な変動を起こした。(中略)10月前半に再び九州、四国、紀伊半島で異常変動があった。これらの場所は南海トラフ、特に九州、四国沖を震源とする南海地震の被害想定地域と符合する」(http://www.zakzak.co.jp/society/domestic/news/20140111/dms1401111456004-n2.htm)
「データを見て、本当にびっくりしましたよ。これは東日本大震災のときと同じじゃないかと。(中略)そうした経験から、私たちは今年12月から来年3月頃の期間に南海トラフでの大地震が起こる可能性が高いと考えたのです」(http://gendai.ismedia.jp/articles/-/37571)
…このように村井氏は明らかに、「南海トラフ巨大地震が起こる」と言っています。それを村井氏は鮮やかに翻し、「南海トラフ地震が起こるとは言ってない」と苦しい言い訳をしているのです。こうした言動をみましても、正直に申し上げて、村井氏の地震予測はあまり信用できないという印象を拭えません。
本サイトでも紹介(こちら)しましたとおり、村井氏は、「昨年の11月頃から今年の3月頃までに南海トラフ巨大地震が起こる可能性が高い」と予測していました。それに対し、3月に発生した地震は、伊予灘の深い地下を震源とするM6.2の地震で、想定される南海トラフ地震とは大きく異なるものでした。これをどう評価すべきでしょうか。
■
村井氏は、「私が南海地震と言ったのは決して南海トラフ地震ではなく南海地方で起きる可能性のある地震を意味します」(村井氏の5月15日twitter)と釈明し、南海地域で地震が起きたのだから的中だと主張しています。
ですが、「南海地域」という広い範囲で良いのなら、最近だけをみても、
・2013年4月13日に淡路島付近を震源としてM6.3(最大震度6弱)
・2011年11月21日に広島県を震源としてM5.4(最大震度5弱)
・2011年7月5日に和歌山県を震源としてM5.5(最大震度5強)
・2010年2月27日に沖縄本島近海を震源としてM6.9(最大震度5弱)
などの強い地震が起きています。M7クラス以上の大地震に限ってみても、2004年に三重南東沖、2005年に福岡県などで起きています。つまり、「南海地域」が揺れる大きめの地震は、非常にコンスタントに起きているのです。
ですので、今回の村井氏のように「11月から3月まで」とほぼ半年もの長い期間をとって、「南海地域が揺れればどこでも的中」だという予想が当たったとしても、統計学的には全く驚くに値しないということが分かります。
■
そもそも、村井氏がtwitterで主張している「私が南海地震と言ったのは決して南海トラフ地震ではなく」というのは、本当なのでしょうか。メディアにおける彼の発言をみてみましょう。
「9月1-7日に、日本全国が異常な変動を起こした。(中略)10月前半に再び九州、四国、紀伊半島で異常変動があった。これらの場所は南海トラフ、特に九州、四国沖を震源とする南海地震の被害想定地域と符合する」(http://www.zakzak.co.jp/society/domestic/news/20140111/dms1401111456004-n2.htm)
「データを見て、本当にびっくりしましたよ。これは東日本大震災のときと同じじゃないかと。(中略)そうした経験から、私たちは今年12月から来年3月頃の期間に南海トラフでの大地震が起こる可能性が高いと考えたのです」(http://gendai.ismedia.jp/articles/-/37571)
…このように村井氏は明らかに、「南海トラフ巨大地震が起こる」と言っています。それを村井氏は鮮やかに翻し、「南海トラフ地震が起こるとは言ってない」と苦しい言い訳をしているのです。こうした言動をみましても、正直に申し上げて、村井氏の地震予測はあまり信用できないという印象を拭えません。