2016年6月23日の国民投票の結果(開票は24日)、英国のEU離脱(BREXIT)が決定した(投票権は18歳以上。離脱51.9% 1741万742票 残留48.1%1614万1241票 登録に対する投票率72.2%)。離脱すると経済が下振れするとの脅しに離脱派の英国民は屈しなかった。離脱支持はイングランド、ウェールズで高く、逆にスコットランドや北アイルランドでは低かった。逆に残留はロンドン、スコットランド、北アイルランドで高い結果になった。つまりはっきりと地域差があった。年代的には若い人に残留が多く、高年齢層は離脱支持が多かった。ただ改めてはっきりしたことは、キャメロン首相(7月にテリーザ・メイ氏に交代 サッチャー以来の女性の首相)がイングランド、ウェールズの多数派を代表しておらず、社会経験や歴史を踏まえた高年齢層の支持も得ていなかったことだ。つまりキャメロンあるいは残留派に、イングランドを代表して発言する資格はない。
英国でも2008年以降5年続いて実質所得の低下 デフレ状況で移民が増加 ➡ 賃金の低下でマイナス成長へ 残留を希望するのはグローバル資本主義の恩恵を受けている大手企業やエリート層だという庶民の感情が強まった。また移民により 階級分裂高まり 移民排斥感情も高まった。国内で事業を営む中小企業には完全な離脱を望む声は多い。
英国の金融界はEUの金融規制を嫌っていたともされる(却って競争力を低下させる)。税制面(低い法人税のほか税金優遇 補助金などで自由度高まる)でも離脱はEUの制約を逃れるメリットがある。興味深い例は、金融取引税(に象徴される金融規制)は残留により導入されようとしていたが英国は反対していたことで、この点だけからいえば、残留派の金融界の利害と離脱派の主張が重なる点である。この対立を改めて考えると、英国は、通貨の問題を含め、EUのすべてを受け入れていたわけではなく、これまでもEUを都合よく利用する側で自己都合を主張する存在だった。そのロジックを進めた一歩先にあるのが、国民投票による今回の離脱決定だった。もともと英国政府が行っていた、EUの都合のよいところだけを利用するご都合主義的な考え方が、今回の離脱を招いた(英国は1999年のユーロ導入当初からユーロへの参加を見送ってきた。金融政策という主権の保持にこだわり、自国通貨ポンドの保持を続けた。国境管理を続けた点ではシェンゲン協定1996年とは距離を保った)。
このほか税制面でも低い法人税率で企業を誘致しようという英国のスタンスはEUの規制的な考え方とは違っていた。
EU残留派は、EU離脱が決定すれば「英国は解体する」「英国の景気は後退する」と脅しをかけた。離脱派に労働者が多く、残留派に都市部の高学歴層が多い。階級対立が明確になった。米国のトランプ旋風と合わせてBREXITの勝利は、ポピュリズム(大衆迎合主義)が指摘される。しかしそうした考え方自身に、所属階級による歪みがないかは検討される必要がある。
リスボン条約により 離脱は欧州理事会に通告して始まる 通告後2年でEU法は英国内で失効する。
2017年1月17日 英国のメイ首相(キャメロン政権時の内相)は EUからの完全離脱を表明した。単一市場への残留を放棄した形。こうした議論は強硬離脱(ハードブレグジット)とよばれていた。3月末までに通告(通知を受けてEUは正式渉開始のスタンス)、2019年3月が期限(通告から2年以内に脱退協定締結とリスボン条約にある)。加盟国の離脱は1993年のEU発足以来初めて。メイは表明のなかでEUに限定されない自由貿易協定FTAの促進を主張。
2017年3月29日 イギリスのメイ首相はEUに離脱を通知した。今回の通知は3月13日に英国議会がメイ首相に離脱を通告する権限を与える法案が通過したことによるもの。リスボン条約によるもので交渉期間は2年間。EUのGDPの16%を占める英国の離脱はEUにとっても大きな意味を持つ。EU離脱は英国への投資の減少につながるという意見もある。しかし2016年6月の国民投票で52%の国民が離脱の意志を表明したことは重い。
2017年6月8日 英国総選挙(4月18日 メイ首相が緊急声明で発表) 保守党は過半数割れにおいこまれる(メイ首相の求心力は低下)。やはり6月からEUとの間で清算金などの交渉。(2016年6月の国民投票で英国民は離脱を選択。2017年3月にEU基本条約第50条により正式に離脱を宣言。その後、2019年3月29日にEUを離脱した。これをBrexitと呼ぶ。)
2017年6月22日欧州連合首脳会議時点。市民の権利(英国在住のEU市民320万 EU在住の英国市民120万の権利)はそれぞれ守られることを確認した。今後、清算金(EU財政負担の約束を尊重で妥結)など離脱条件の議論を優先して議論。
欧州連合とイギリスは2018年2月5日 移行期間の協議にはいった。英国側は離脱後の移行期間について約2年としつつ、状況に応じて延長できる仕組みを求めた(2018年2月21日)。3月22-23日に首脳会議で暫定合意が成立。2020年12月までを移行期間としてEU単一市場関税同盟への残留が決まった。
なお英国はイングランド ウエールズ スコットランド アイルランドから構成されるが、そのスコットランドには独立を求める動きがあり、アイルランドでは統一(北アイルランドとアイルランド共和国の)を求める動きがある
2018-12-11(2016-06-26;2016-07-21;2017-06-23)










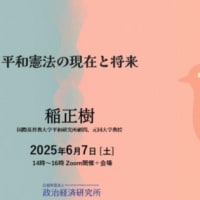





※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます