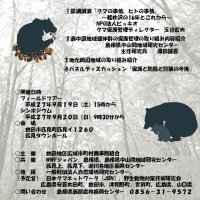粘菌(変形菌)を御存知でしょうか?
と言う私もあまりよく知りません。
先日、粘菌を採集することができましたので、粘菌の不思議な生態について報告します。
先月、私は、東京八王子で「森林環境教育研修」を受講していました。
この研修を一緒に受講していた神奈川県のSさんが、粘菌を飼っていらっしゃったのです(趣味で)。
それまでの私の知識は、「粘菌=南方熊楠が研究していた」程度でした。
しかし、「粘菌」の持つ不思議なイメージには、何か心惹かれるものがあり、一度本物を見てみたいものだと前々から思っていました。
そういう中で、研修で神奈川県のSさんと出会い、夜、Sさんの部屋で、和歌山森林管理署のKさんと一緒に粘菌(ウツボホコリ)の実物(子実体)を見せてもらいながら、粘菌の講義を聴かせてもらったのです。
Sさんの話の概要は次のとおりです。
① 粘菌は、現在、分類学上「変形菌」と呼ぶ。
② 変形菌は、世界に900種ぐらいあり、うち日本で600種※1ぐらい見ることが出来る。
※1 450種としている本もありました。
③ 変形菌は、どこにでもいる(どこの森林にもいるという意味でしょう)。
④ キノコのように子実体(キノコ)をつくって、胞子で増える。
⑤ 生活史の途中で「変形体」と呼ばれる「アメーバ」になる。
⑥ 落葉や倒木にいる微生物を食べるので、エサはいらない(水だけやっていれば良い)。
⑦ キノコの菌糸は、鳥の羽状に伸びるが、粘菌の変形体は扇状に広がる。
⑧ 雨の次の日によく見つかる(普段は、枯葉の裏とかに潜んでおり見えない)。
⑨ 6月~8月は、一番粘菌を見つけやすい季節である。
図鑑の写真を見ると、確かに山の中でよく見ているような気がします。森林には、普通にいそうな気がします。
実は、研修後、休みの度に山に行っては、林道沿いのジメジメしていそうなところを覗き込んで、粘菌を探していたのです。
そして、遂に戸田柿本神社の森の中で発見しました。うれしくて、見つけた時の写真を撮るのを忘れてしまいました。
ちなみに、戸田柿本神社は、彫刻がすばらしい神社でした(これも写真がありません)。
以下、採集してきた粘菌の写真です。

写真1 7/8 15:57現在
採取したときは、触手?を伸ばして広がっていた変形体が、家に持って帰ったら収縮してしまっていました。
似ていますが、決して「痰」ではありません。

写真2 7月8日 17時15分現在
変形体(アメーバ)が、移動しています。

写真3 7月8日 19時13分現在
変形体が、分裂して個々にまとまり始めました。

写真4 7月8日 20時14分現在
写真では、わかりませんが、変形体のかたちが粒状になりました。
一塊の黄色の粒が、まん丸い粒の集合体です。蝶の卵のようです。
非常に美しい黄色です。

写真5 7月9日 00時06分現在
寝苦しくて目が覚めました。
粘菌を見ると、茶色に変色し始めていました。

写真6 7月9日 05時04分現在
茶色の子実体(きのこ)になりました。

写真7 子実体の拡大写真
一塊の茶色の粒をよく見ると、数十本のフランクフルト様の子実体(高さ3ミリ程度)の寄せ集まりでできています。
小さいのに良くできています。感動です!
図鑑を見ると、採集してきた粘菌は「スミスムラサキホコリ」のようでした。
皆さんも、少し、注意して足下を見ながら森林の中を歩けば、これらの不思議な生物に出会えるかもしれません。
梅雨時期の山歩きが楽しくなりますよ。
投稿者 島根県西部農林振興センター益田事務所林業普及グループ 主任林業普及員 大場寛文
と言う私もあまりよく知りません。
先日、粘菌を採集することができましたので、粘菌の不思議な生態について報告します。
先月、私は、東京八王子で「森林環境教育研修」を受講していました。
この研修を一緒に受講していた神奈川県のSさんが、粘菌を飼っていらっしゃったのです(趣味で)。
それまでの私の知識は、「粘菌=南方熊楠が研究していた」程度でした。
しかし、「粘菌」の持つ不思議なイメージには、何か心惹かれるものがあり、一度本物を見てみたいものだと前々から思っていました。
そういう中で、研修で神奈川県のSさんと出会い、夜、Sさんの部屋で、和歌山森林管理署のKさんと一緒に粘菌(ウツボホコリ)の実物(子実体)を見せてもらいながら、粘菌の講義を聴かせてもらったのです。
Sさんの話の概要は次のとおりです。
① 粘菌は、現在、分類学上「変形菌」と呼ぶ。
② 変形菌は、世界に900種ぐらいあり、うち日本で600種※1ぐらい見ることが出来る。
※1 450種としている本もありました。
③ 変形菌は、どこにでもいる(どこの森林にもいるという意味でしょう)。
④ キノコのように子実体(キノコ)をつくって、胞子で増える。
⑤ 生活史の途中で「変形体」と呼ばれる「アメーバ」になる。
⑥ 落葉や倒木にいる微生物を食べるので、エサはいらない(水だけやっていれば良い)。
⑦ キノコの菌糸は、鳥の羽状に伸びるが、粘菌の変形体は扇状に広がる。
⑧ 雨の次の日によく見つかる(普段は、枯葉の裏とかに潜んでおり見えない)。
⑨ 6月~8月は、一番粘菌を見つけやすい季節である。
図鑑の写真を見ると、確かに山の中でよく見ているような気がします。森林には、普通にいそうな気がします。
実は、研修後、休みの度に山に行っては、林道沿いのジメジメしていそうなところを覗き込んで、粘菌を探していたのです。
そして、遂に戸田柿本神社の森の中で発見しました。うれしくて、見つけた時の写真を撮るのを忘れてしまいました。
ちなみに、戸田柿本神社は、彫刻がすばらしい神社でした(これも写真がありません)。
以下、採集してきた粘菌の写真です。

写真1 7/8 15:57現在
採取したときは、触手?を伸ばして広がっていた変形体が、家に持って帰ったら収縮してしまっていました。
似ていますが、決して「痰」ではありません。

写真2 7月8日 17時15分現在
変形体(アメーバ)が、移動しています。

写真3 7月8日 19時13分現在
変形体が、分裂して個々にまとまり始めました。

写真4 7月8日 20時14分現在
写真では、わかりませんが、変形体のかたちが粒状になりました。
一塊の黄色の粒が、まん丸い粒の集合体です。蝶の卵のようです。
非常に美しい黄色です。

写真5 7月9日 00時06分現在
寝苦しくて目が覚めました。
粘菌を見ると、茶色に変色し始めていました。

写真6 7月9日 05時04分現在
茶色の子実体(きのこ)になりました。

写真7 子実体の拡大写真
一塊の茶色の粒をよく見ると、数十本のフランクフルト様の子実体(高さ3ミリ程度)の寄せ集まりでできています。
小さいのに良くできています。感動です!
図鑑を見ると、採集してきた粘菌は「スミスムラサキホコリ」のようでした。
皆さんも、少し、注意して足下を見ながら森林の中を歩けば、これらの不思議な生物に出会えるかもしれません。
梅雨時期の山歩きが楽しくなりますよ。
投稿者 島根県西部農林振興センター益田事務所林業普及グループ 主任林業普及員 大場寛文