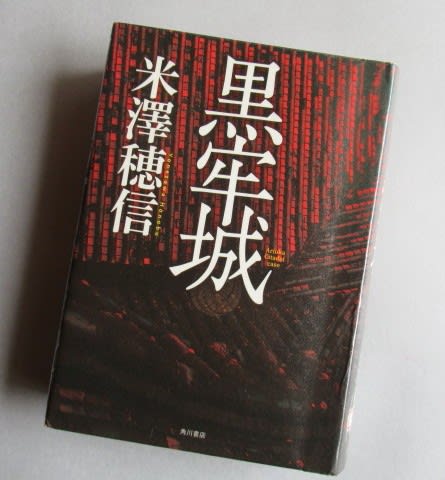「蹴れ、彦五郎」(今村翔吾著 祥伝社 令和4年7月20日初版第1刷発行)を読みました。

この本のタイトルは、「蹴れ、彦五郎」となっていますが、実際には、次の、
① 蹴れ、彦五郎
② 黄金(こがね)
③ 三人目の人形師
④ 瞬(まばたき)の城
⑤ 青鬼の涙
⑥ 山茶花(さざんか)の人
⑦ 晴れのち月
⑧ 狐の城
という、八編の短編から成っていました。
「① 蹴れ、彦五郎」は、今川義元の嫡男今川彦五郎氏真に関する物語を書いたものでした。
彦五郎は、蹴鞠と歌を何よりも好み、名家を没落させた武将として有名ですが、その当時には無い考え方の「職業選択の自由」を貫いた武将であったという側面から描いた内容のものでした。
「② 黄金(こがね)」は、織田信長の嫡孫織田秀信に関する物語でした。
織田秀信は、関ヶ原の戦いの際には西軍について破れ、高野山に送られますが、そこからも追放され、その後1月足らずで25歳の若さで没したということです。
なお、一部の史料には、陸奥棚倉1万石で大名に復帰したという記述もあるということが付記されていました。
「③ 三人目の人形師」は、他の七編とは趣の異なる、生人形(いきにんぎょう)師にまつわる、ホラー的な内容のものでした。
「④ 瞬(まばたき)の城」には、「星ヶ岡城」という太田道灌の頃に築城されたという城にまつわる物語が書かれていました。
そこには、太田道灌や、太田道灌に、「貧しくて蓑がないので貸せない」という意味を込めた歌に山吹の枝を添えて差し出したという謎の女性が登場してきます。
「⑤ 青鬼の涙」は、鯖江藩第7代藩主間部詮勝という人物に関する物語でした。
幕末の井伊直弼は赤鬼と呼ばれて有名ですが、鯖江藩第7代藩主間部詮勝は「鯖江の青鬼」と呼ばれていたとのことです。
彼は明治の世を見ることになりますが、明治になって、東京向島の屋敷から、一人、元の領地であった鯖江に旅立ち、そこで、若殿の時代に食べていた羊羹を買ったという内容でした。
「⑥ 山茶花(さざんか)の人」は、上杉家の猛将新発田重家に関する物語でした。
新発田重家は上杉家に反旗を翻し、義の家である上杉家に刃向かったわけですが、それは、彼が悪なのか、それとも、彼には彼なりの義があったからなのかという視点から書かれたものでした。
「⑦ 晴れのち月」は、武田信玄の嫡男武田太郎義信を主人公としたものでした。
武田信玄は、武田太郎義信が謀叛を企てたということで、彼を廃嫡するわけですが、それを、後日、信玄が後悔するという内容でした。
その辺の記述は次のようなものでした。
「・・・義信の死から五年後の元亀三年(1572)、かつて義信が予見したように美濃を得た織田家は一気に膨張し、武田家を大きく上回る勢力になっていた。このままではさらに国力の差が広がると見た信玄は、織田家と断絶し、それを討たんと西上作戦を決行した。
織田家との決戦を急いだ理由はもう一つある。
それは信玄の労咳の症状が悪化し、残された時が僅かであることを悟っていたのである。
初戦から武田軍の連戦連勝であったが、西上の途中、信玄は倒れた。
「今少し時があれば・・・・・口惜しい」
病床で痩けた頬を震わせながら信玄は零した。
跡取りの勝頼は勇猛であるが人を惹きつける魅力に欠ける。さらに一度諏訪家に養子に出していたこともあり、くせ者揃いの家中を纏めるには至らないと考えていた。
「太郎が生きておれば・・・・・」
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
「その通りだな・・・・・」
その譫言が最後の言葉であった。 (P.330~331) 」
最後の「⑧ 狐の城」は、北条氏康の4男北条氏規(うじのり)に関する物語でした。
豊臣秀吉による北条攻めの際、彼は、韮山城に籠もって激しく抵抗します。しかし、多勢に無勢、遂に韮山城を明け渡すこととしますが、その際、明け渡しの条件として北条家当主北条氏直の助命と相模など一部の領地の安堵などを申し出ます。
その後、氏規の努力により、氏直は赦され、河内及び関東に1万石を与えられ大名に復します。
なお、その後の北条家の推移については、次のように書かれていました。
「しかし、氏直は、11月4日に大坂で病死した。
小田原北条氏五代当主、北条氏直。三十歳という若さだった。
氏直の死後、氏規の嫡子である氏盛が、遺領のうち4千石を相続した。
氏規は河内国丹南郡に2千石、後に河内に約7千石を宛てがわれた。
慶長3年(1598)には隠居し、氏盛に己の全ての知行地を任せた。
領地を併せたことにより、氏盛は1万1千石の大名となった。北条宗家は、河内狭山藩主としてその血脈を幕末に至るまで紡ぐのである。 (P.377~378) 」
ちなみに、北条氏直の妻督姫は徳川家康の娘です。北条氏規のことを「狐」と称するのは、秀吉が、家康を「狸」と言い、氏規のことを「狐」と言ったことを、自らがいたく気に入り、両人をそのように称したことに由来するようです。