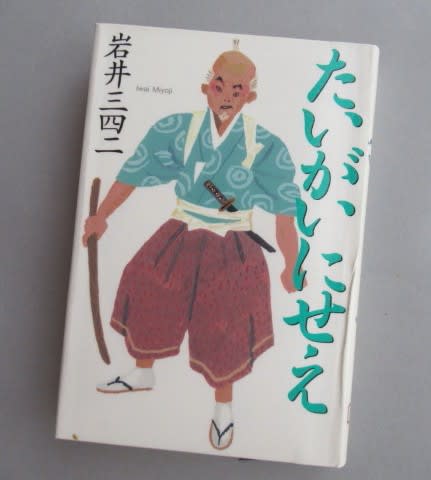「たいがいにせえ」(岩井三四二著 光文社 2007年12月25日初版第1刷発行)を読みました。
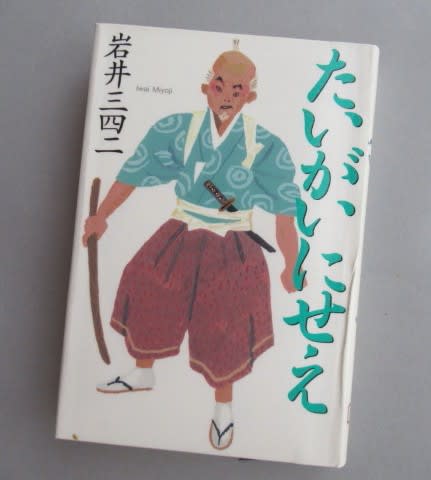
この本は、図書館に読み終えた本を返却に行った際、今度は何を借りてきて読もうかなと書棚を眺めていましたところ、何となく目に留まったもので、また、何となく気安く読めるように感じたものですから、借りてきたものです。
この本の「タイトル」が「たいがいにせえ」ということで、1冊の長編のように思われるかもしれませんが、実際には、
① 祇園祭に連れてって
② 一刻は千年
③ 太平寺殿のふしぎなる御くわだて
④ 信長の逃げ道
⑤ バテレン船は沖を漕ぐ
⑥ あまのかけ橋ふみならし
⑦ 迷惑太閤記
という、七つの中編を集めて1冊にしたものでした。また、それぞれの中編は、全く関連性がなく、それぞれが独立したものでした。
そして、それぞれの中編の内容は、戦国時代の一つの小さな出来事をテーマにしたもので、いわば「戦国時代こぼれ話」というようなものでした。
以下、それぞれの中編の概要を紹介いたします。
① 祇園祭に連れてって
祇園祭は平安時代から連綿と行われてきていましたが、応仁の乱から33年間は中断したとのことです。復興したのは明応9(1500)年のことということですが、なにせ、33年間も中断していたものですから、その復興は大変だったようで、その復興に当たっての関係者の苦労話をまとめたものでした。
② 一刻は千年
因島(いんのしま)を治める村上水軍の宿将の宮地氏の娘で、来島(くるしま)の村上氏に嫁いだ姫がいました。姫は、その後、来島の夫に先立たれ、実家に戻り、紹玉尼と称していました。
紹玉尼は、若い頃から美人の誉れ高く、また、女傑でもあったとのことでした。嫁入り前の14歳の頃には、ルソンから来た若い男と駆け落ちしましたが、すぐに捕まって連れ戻されたとの噂がありました。
ある者が、紹玉尼にその真偽を尋ねたところ、それは真実であると告げられたとのことで、また、すぐに捕まることを承知のうえで後先のことも考えずに駆け落ちしたが、そのルソンの男と過ごした一刻ほどが、千年にも万年にも思えたと語ったということでした。
③ 太平寺殿のふしぎなる御くわだて
安房の里見義弘と鎌倉太平寺の住持青岳尼とは、幼なじみでした。青岳尼は、下総国の小弓公方足利義明の娘で、元服したばかりの里見義弘は小弓公方の御所に出仕していました。
しかし、小弓公方足利義明の軍勢が北条の軍勢に破れ、足利義明をはじめ、一族郎党はみな討ち死にし、娘は父の後生を弔うために尼とならざるをえず、鎌倉太平寺に入り青岳尼となります。そのようなことで、里見義弘と青岳尼とは、別れ別れとなりました。
しかし、二人の間の思いは強く、二人は密かに連絡を取り合い、遂に、里見義弘は軍船を仕立て鎌倉の太平寺に赴き、青岳尼を救い出したという話です。その後、青岳尼は還俗して里見義弘の正妻となり、二人は仲睦まじく暮らしたということです。
④ 信長の逃げ道
織田信長が越前の朝倉義景の攻撃に出向くわけですが、その際、同盟関係にあった妹婿の浅井家の裏切りにあい、挟撃の危機に瀕します。そのため、豊臣秀吉と信長の同盟軍の徳川家康をシンガリとし、信長本隊は信長勢力地まで帰還することになります。
その際の信長の逃げ道となったのが山深い朽木越えの経路だったわけで、その際の、その朽木の地を領する朽木弥五郎元綱のとった行動を主とした内容でした。
その後、朽木弥五郎元綱は信長に仕え、本能寺の変のあとは秀吉に仕えました。関ヶ原の合戦では、当初、西軍に属しましたが、途中で東軍に寝返って9,590石を知行します。江戸時代になっても家を保ち、信長の朽木越えから62年後の寛永9年(1632)、84歳で生涯を閉じたということです。
⑤ バテレン船は沖を漕ぐ
大友宗麟からの指示で、バテレンを乗せた船が豊後の日出の湊を出て堺に向かいます。バテレンは、フロイス、ロレンソ、その他6人の計8人でした。
船は、海賊たちに関銭を払いながら、順調に瀬戸内海を堺へと向かいます。ところが、何カ所かの湊を通過するうちに、海賊たちが、その船にはバテレンが乗っているらしいことに気付きます。
バテレンたちも、乗っていることを勘づかれたらしいことに気付き、最後の湊には寄らず、沖合を漕いで突っ走るようにと、船頭たちを脅します。
やむなく、船頭たちは最後の湊には寄らないことを決意し、沖合を漕ぎに漕いで、ぎりぎりセーフで堺に着いたという話しです。
⑥ あまのかけ橋ふみならし
荒木村重は、信長に反旗を翻し、有岡城に籠もりますが、或る日、突然、城からいなくなりました。籠城中に城主がいなくなるという前代未聞の事態が発生したわけです。散々探しますが、そのうち、嫡子・新五郎が城主を務める尼崎城にいることがわかります。
有岡城に残された側室のだし(正室が死亡しているので実質正妻)たちは、その後も頑張りますが、遂に、力尽きて降参します。
その後の状況については、次のように書かれていました。
「有岡城に籠もっていた女子供など122人は、天正7(1579)年12月13日に尼崎近くで織田の手の者に磔にかけられ、ほかに若党や下女など500人以上が、家4軒に押し込められて焼き殺された。だしたち荒木一門の者は京に送られ、大路を引き回された上、16日に六条河原で首を切られた。
荒木村重自身は、尼崎城を抜け出して毛利へ下り、妻子が殺されたあともひとり生き延びた。本能寺で信長が憤死したあとは秀吉の元へ出仕し、茶人として利休七哲にも数えられ、天正14(1586)年、52歳で死去したという。
残らず斬られたはずの荒木一族の中で、2歳の幼児だけが乳母の機転によって助かったという話も伝わっている。その子は長じて、岩佐又兵衛という有名な絵師となった。又兵衛がだしの子かどうかは不明である。 (P.239~240)」
⑦ 迷惑太閤記
加賀藩士で200石取りの笠間儀兵衛は、70歳を過ぎても隠居もせずに、元気に城勤めをしていました。
普段、昔、戦場で首を取ったという武勇伝を語り、昔の自慢話ばかりをしていて、周りからは煙たがられていました。
ところが、或る時、「太閤記」なる書物が発刊されていることを、また、それを書いた者が、藩主の侍医であることを知りました。そうであれば、なおさらのこと、きっと、自分の働きのこと、自分が戦場で敵の首をとったことも書かれているに違いないと思うようになります。
しかし、やっと手に入れて読んだ「太閤記」には、自分が戦場で首を取ったのではなく、鉄砲で打ち倒された者の首を取った、つまり「拾い首」をしたように書いてあることに気付きます。
それでは、昔の自慢話も出来なくなるわけで、憤懣遣る方なしなわけですが、著者が藩主の侍医ではどうしようもありません。そこで、笠間儀兵衛は、「太閤記」の内容に不服である旨の書面を書き上げ、それを家老に提出したということです。
その辺のことについて、この中編の最後には、次のように書かれていました。
「小瀬甫庵の書いた太閤記が版本として刊行されたのは、寛永11年(1634)以降と推定されている。刊行当初から娯楽本というより、歴史書として読まれ、これ以降書かれる種々の歴史書に、多くの頻度で引用されることになる。
それだけに文中に自分や親の名を書かれた者たちは、その書かれように一喜一憂したようである。笠間儀兵衛は加賀藩家老あてに内容が不服である旨、書き上げたが、それに対して家老がどう対応したかは伝わっていない。 (P.280)」