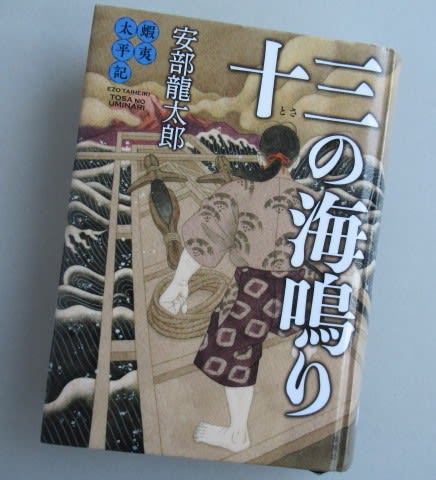「検証 長篠合戦」(歴史文化ライブラリー382)(平山優著 吉川弘文館 2014年(平成26)8月1日第1刷発行)を読みました。

この本も、いわゆる「歴史小説」というものではなく、「歴史書」といえるものに属するようです。
「長篠合戦は、天正3年(1575)5月21日、三河国長篠の設楽ヶ原(したらがはら)(当時は有海原(あるみはら))で、織田信長・徳川家康連合軍が武田勝頼の軍勢を撃破したもので、その勝因は織田軍が装備した鉄炮3,000挺であったこと、またその射撃法が三段撃ちであったことはつとに知られている」(P.1)わけで、それが通説になっているわけですけれども、その通説が、近年、多岐ににわたる批判に晒されれているので、それらについて、検証を試みようとして書かれたものでした。
その多岐ににわたる批判というものは、次のようなことだとのことです。
① 長篠合戦に織田信長が投入した鉄炮3,000挺は事実か。
② 鉄炮3,000挺の三段撃ちはあったのか(織田信長の天才的才覚による、この戦法の発明を契機に軍事革命、線戦術革命が起きたというのは事実か)。
③ 武田勝頼の軍勢に騎馬隊は本当に存在したのか。
④ 武田勝頼の作戦は無謀で、自殺行為ともいえる突撃が繰り返されたがそれはなぜか。
⑤ 武田勝頼は、味方の不利を説き、諫める家臣達を振り切って決戦を決断したというのは事実か否か。
⑥ 織田信長の装備した鉄炮とはどのように集められたか。
⑦ 武田氏は信玄以来鉄炮導入には消極的というよりも、むしろその有効性を軽視しており、これが長篠敗戦に繋がったというのは事実か。
⑧ 長篠合戦場には両軍の陣城跡が歴然としており、これが鉄炮と並んで合戦の帰趨に影響を与えたのではないか。
⑨ 馬防柵は、織田信長が緻密な計画を立案し建設したとされるが事実か。
著者は、これらのテーマに関し、多方面から、例えば、考古学の手法を使っての、両軍から合戦場に打ち込まれて残った鉄炮玉の数や大きさ、その材質などの研究成果なども考慮して、詳細に検討を重ねています。
その結果、著者は、
「① 織田・徳川軍と武田軍には、「兵農分離」と「未分離」という明確な質的差異はなく、ほぼ同質の戦国大名の軍隊であり、②合戦では、緒戦は双方の鉄炮競合と矢軍(やいくさ)が行われ、やがて接近した敵味方は打物戦に移行し、鑓の競合と「鑓脇」の援護による戦闘が続く、③打物戦で敵が崩れ始めると騎馬衆が敵陣に突入(「懸入」「乗込」)し、敵陣を混乱させ、最終的に敵を攻め崩す、④戦国合戦では、柵の構築による野陣・陣城づくりは一般的に行われており、それ自体は特異な作戦ではなかった、⑤合戦において、柵が敷設されていたり、多勢や優勢な弓・鉄炮が待ち受けたりしていても、敵陣に突撃するという戦法は、当時はごく当たり前の正攻法であった。・・・こうした戦国合戦の実相をもとにすると、武田勝頼が長篠合戦で採用した作戦は、ごく普通の正攻法であり、鉄炮や弓を制圧し、敵を混乱させて勝利を目指すものであったと考えられる。しかしそれが成功しなかったのは、勝頼や武田軍将兵が経験してきた東国大名との合戦と、織田信長とのそれとの違いであたと思われる。それは、織田・徳川軍が装備した鉄炮数と、用意されていた玉薬の分量、さらには軍勢の兵力の圧倒的差とい形で表れたと考えられる。」(P.230~231)
としています。つまり、
「武田勝頼の敗因、織田信長・徳川家康の勝因は、通説の如き旧戦法対新戦法、兵農未分離の軍隊対兵農分離の軍隊という両軍の質的差異、勝頼の無謀な突撃作戦などではなかったと推察される。両者の明暗を分けたのは擁した火器と弾薬の数量差、そして兵力の差であり、それらはいずれも武田氏と織田・徳川両氏の擁する領国規模と、鉄炮と玉薬の輸入もしくは国産の実現可能な地域とアクセスしうる可能性の格差という理由に絞られるであろう。」(P.234)
としています。
そして、著者は、
「前著(『長篠合戦と武田勝頼』)と本書の執筆を通して、今も根強い織田信長や徳川家康に対する過大評価は慎むべきだと痛感した。戦後歴史学は、歴史上の人物の業績を社会構造などから読み直すことを課題としてきたはずなのに、戦国・織豊期でいえば、織田信長、豊臣秀吉、徳川家康という個人の資質に、すべての現象を還元して議論する傾向から、なぜか今も抜け出せていない。たとえば織田権力と戦国大名を同列では論じることは出来ないとか、そもそも織田権力を「先進」とアプリオリに措定し、そこへの到達度で戦国大名の「発展」「後進」の度合いを論じることは本当に意味があることなのだろうか。前著と本書で力説したのは、織田氏も戦国大名であり、あらゆる面からみて武田・北条・上杉・今川氏などと同質の権力体だということだ。最終的に広大な領国を形成し「天下」を掌握したことだけを根拠に、だから戦国大名とは違うはずだ、はもう止めにしようではないか。」(P.240~241)
と書いています。