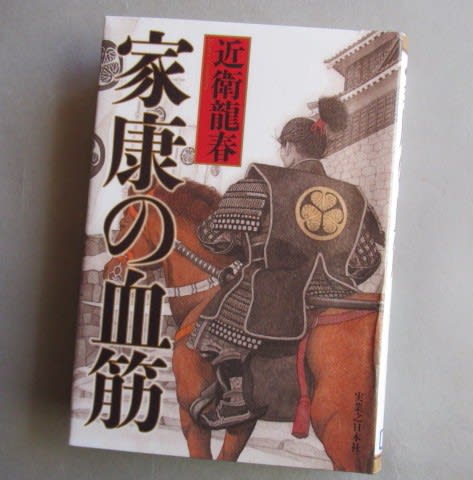「アーミッシュの昨日・今日・明日」(ドナルド・B・クレイビル著 杉原利治・大藪千穂訳 論創社 2009年5月25日初版第1刷発行)を読みました。

帯を着せた状態

帯を外した状態
本書は、以前に(2022年4月27日に)紹介しました「アーミッシュの謎──宗教・社会・生活」(ドナルド・B・クレイビル著 杉原利治/大藪千穂訳 杉原利治監修 論創社 1996年6月15日初版第1刷発行)の姉妹編ともいえるものとのことです。
なお、本書も、この「アーミッシュの謎──宗教・社会・生活」と同様、翻訳者の一人であります杉原利治さんこと故玩館館主の遅生さんからプレゼントされたものです(^-^*) 遅生さん、ありがとうございました(^_^)
ところで、本書は、次の34項目に分けて、「ペンシルベニア州ランカスター郡を中心としたアーミッシュの生活、文化の特徴とその意味を丁寧に説き明かし、アーミッシュ社会がダイナミックに変化しつつあることを示し」(P.147)ています。
① ランカスター郡のアーミッシュ
② 人口増加の秘密
③ 神話と現実
④ 宗教的ルーツ
⑤ アーミッシュ的価値のパッチワーク
⑥ アーミッシュの精神性
⑦ オルドヌング
⑧ 宗教儀式と実践
⑨ コミュニティ生活の構築
⑩ 家族と子供たち
⑪ 子供の誕生
⑫ 健康管理
⑬ 豊富な食べ物
⑭ 社会的集まりと休日
⑮ レジャー
⑯ 学校と教師
⑰ ラムシュプリンガ
⑱ 結構式
⑲ 土地を守る人々
⑳ 小さな産業革命
㉑ 女性起業家
㉒ 自動車の謎
㉓ トラクターと農場の機械
㉔ アーミッシュ電気
㉕ 技術の選択的利用
㉖ 社会参加
㉗ 政府、選挙、税金
㉘ 観光
㉙ アーミッシュとメディア
㉚ ニッケルマインズの悲劇
㉛ 芸術と創造的表現
㉜ 厳かな死
㉝ 再洗礼派グループ
㉞ アーミッシュ社会の未来
そして、「アーミッシュ社会の未来」については、
「21世紀、アーミッシュの生活の文化的特色はどのようなものになるのか、予測はできない。しかし、一つの新しいパターンが明らかに現れ始めている。つまり、田舎の家屋敷が彼らの伝統的やり方を保つのに最適な場所であり続けるということである。もし、アーミッシュが子供たちを教育して、コミュニティにとどめることができ、彼らの魂を売り渡すことなく生計を立て、より大きな世界との交わりを制限することができるならば、おそらく彼らは、21世紀にも繁栄するだろう。しかし、アーミッシュの人口がどんどん増加するにしたがい、確かになってきたことが一つある。彼らは、伝統的生活のうちで、旧態依然とした部分の多くを変化させ、適合させ、粉みじんに打ち砕き続けるであろうということだ。(P.146)」
と言っています。
また、アーミッシュの数百年におよぶ生活、文化の実践活動に対する評価と「アーミッシュ社会の未来」につきまして、本書の翻訳者の一人であり、アーミッシュ研究者でもあられる杉原利治さんこと故玩館館主の遅生さんは、本書の巻末の「解題」の中で、次のように論じています。
「 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
誤解を恐れずに言えば、アーミッシュは20世紀に誕生した。もちろん、歴史的には、ヨーロッパ宗教改革にルーツをもつアーミッシュにとって、外の世界との分離は当初から主要な命題であった。しかし、実際、アーミッシュと外の世界との乖離が大きくなり始めたのは、20世紀に入ってから、それも、大恐慌、ニューディール政策を経た1940年代以降である。・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
20世紀は都市化の時代である。そして、都市化は消費社会をもたらした。・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
アーミッシュは都市化に抵抗してきた。・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
これまで、都市化、すなわち、生産と消費の拡大に対しては、資源・環境問題がその拡大を阻む要因として考えられてきた。しかしながら、その前に、現代社会の不安定さが極大となり、生産と消費に急ブレーキをかけている。したがって、安定と持続可能の観点から、外の世界の社会システムのあり様を再考する必要がある。その際、アーミッシュの数百年におよぶ実践は、参考になるに違いない。小規模組織に関しては、幸いにも、家族はまだ完全には解体してはいないし、地域再生の試みも各地で盛んに行われている。また、個人のレベルでは、生産と消費の仕方、すなわち、ライフスタイルを21世紀にふさわしいものにつくりかえていく必要があるだろう。そして、外の世界の社会が持続していくためには、組織には自律機能、個人には自主管理能力の回復が必須である。
アーミッシュは、外の世界の私たちを映す鏡である。左右は逆だが、上下は同じだ。彼らは、生産と消費の両方に携わり、生産者として自分たちの足場を固めながら、注意深く生活を変化させてきた。もし、今後、私たちが日常生活において、アーミッシュのように徳と品格を身につけることができるならば、20世紀の抵抗者アーミッシュと外の世界のポストモダンとは、この21世紀に、案外、近づいてゆくのかもしれない。」
以上で、本書の紹介といたしますが、本書は、歴史小説などとは違い、大変に中身の濃いものでした。それを、強引に短文に纏めてしまいました(><)
しかも、私の理解不足もあり、本書の内容を取り違えて紹介しているのではないかと危惧してもおります(~_~;)
そのようなことで、本書の紹介などしないほうがいいのかな~とも思ったのですが、「アーミッシュ」というものの存在を知ってもらい、興味を抱かれた方には「アーミッシュ」関連の本を読んでいただければと思って敢えて紹介することとした次第です。