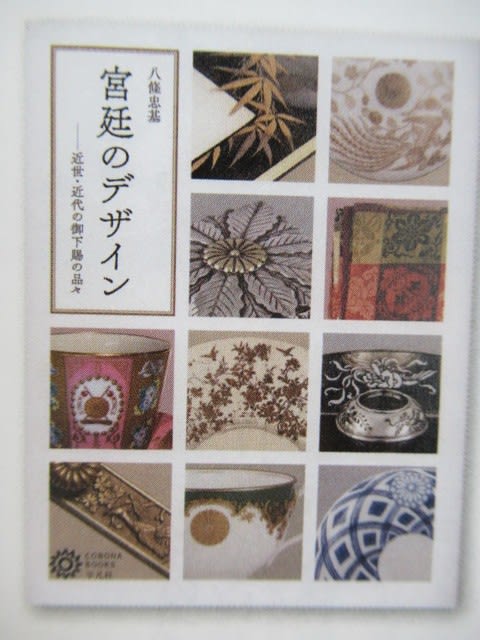今では止めてしまった拙ホームページの「古伊万里への誘い」では既に紹介しているのに、このブログではまだ紹介していない伊万里がまだ5点ほど残っていることを記してきているところです。
そして、これまでに、そのうちの「伊万里 染付 鶉文 中皿」の2点、「伊万里 染付 竹・燕文 中皿」の1点及び「伊万里 染付 二股大根にネズミ文 中皿」の1点の計4点を紹介したところです。
なお、今では止めてしまった拙ホームページの「古伊万里への誘い」では既に紹介しているのに、どうしてこのブログでは紹介しなかったのかにつきましては、それは、それらが本歌の古伊万里ではなく、最近作られた「古伊万里写し」なのではないだろうかとの疑念が湧いたためであったことも記したところです(~_~;)
しかし、そうした疑念のある物でも、そのまま、疑念のある物として紹介することにも、少しは意義があるのではなかろうかと考え直し、順次、それらを紹介してきたところです。
そのようなことで、今回は、残りの1点の「伊万里 染付 鹿紅葉文 中皿」を紹介いたします。
伊万里 染付 鹿紅葉文 中皿

表面

表面の一部の拡大(その1)

表面の一部の拡大(その1)の下側左の雌鹿の拡大
躍動感がなく、寝そべっているよに見えます(笑)
本来は、雄たちと共に躍動している様子を描いたのだろうと思いますが、表情からみますと、後ろ側の雄の接近にビックリして立ち上がろうとしているところを描いたようのも見えます(~_~;)

表面の一部の拡大(その1)の下側の真ん中の雄鹿の拡大
喜んで躍動しているようにみえますので、動きや表情の描き方はまぁまぁというところでしょうか。

表面の一部の拡大(その1)の下側右の雄鹿の拡大
この雄鹿も、気持ちよさそうに躍動しているようにみえますので、動きや表情の描き方はまぁまぁというところでしょう。
以上、この中皿に描かれた5頭の鹿のうちの3頭について拡大して見てみましたが、それぞれの鹿には、それなりの動きや表情が見られるようです。
伊万里も、江戸前期の頃のものには動きや表情が鋭く描かれているものが多いようですが、江戸も後期となりますとそれほどの鋭さが無くなるようです。
これらの鹿の描き方から判断しますと、この中皿は、江戸後期の本歌の古伊万里なのかなとも思えるわけですが、造りや素地、その他の文様の描き方などの全体から判断しますと、何となく腑に落ちないものを感じるわけで、やはり、最近作られた「古伊万里写し」なのではないだろうかとの疑念が湧いてしまうわけです(~_~;)

表面の一部の拡大(その2)

側面

裏面

裏面の一部の拡大
生 産 地 : 不明
製作年代: 不明
サ イ ズ : 口径:20.7cm 高台径:13.1cm
追って、前述しましたのように、この「染付 鹿紅葉文 中皿」につきましては、今では止めてしまった拙ホームページの「古伊万里への誘い」で既に紹介しているわけですが、その時の紹介文を、次に、参考までに再度掲載いたします。
なお、その紹介文の中では、この「染付 鹿紅葉文 中皿」につきまして、「生産地:肥前・有田」、「製作年代:江戸時代後期」としておりますことをお含みおきください。
=====================================
<古伊万里への誘い>
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
*古伊万里ギャラリー209 伊万里染付鹿紅葉文中皿 (平成27年10月1日登載)


鹿と紅葉の取り合わせは陳腐な取り合わせである。
しかし、この皿は染付にすぎないのに、これを見ていると、秋を美しく彩った「紅葉」が地面いっぱいに広がり、赤や黄色の絨毯を敷き詰めたような中を、まばらな木々の間をすり抜けるように駈ける鹿の茶色という色感が鮮やかに目に浮かんでくる。
「鹿と紅葉」というと、もう、脳がそのように記憶しているからであろう。これは、陳腐さの効能でもあろうか、、、。
また、この皿からは、急に雷鳴が轟いたため、それに驚いた鹿が飛び上がっている躍動感まで伝わってくる。
染付であるのに、色彩豊かな「静」と「動」とが伝わってくる皿である。
江戸時代後期 口径:20.7cm 高台径:13.1cm
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
*古伊万里バカ日誌138 古伊万里との対話(鹿紅葉文の皿) (平成27年10月1日登載)(平成27年9月筆)
登場人物
主 人 (田舎の平凡なサラリーマン)
鹿紅葉 (伊万里染付鹿紅葉文中皿)


・・・・・プロローグ・・・・・
暑さ寒さも彼岸までと言われるが、彼岸を過ぎたらめっきり涼しくなってきた。
そこで、主人は、秋を感じさせる古伊万里と対話をしたくなったようで、押入れから1枚の古伊万里を引っ張り出してきて対話をはじめた。
主人: まだ秋真っ盛りという状況ではないんだが、ちょっと季節を先取りした感じでお前に登場してもらった。
鹿紅葉: まだ、ちょっと、私の出番には早いんじゃないですか。来月でもよかったのでは・・・・・。
主人: なにごとも早いにこしたことはないからな。すべからく、時代を先取りしたものに注目が集まるし、季節を先取りしたものにこそ「粋」という言葉が付加されるにふさわしいだろうよ。
だいたい、お前のように「鹿に紅葉文」は陳腐な文様の代名詞みたいなものだからな。来月に登場したのでは、陳腐さを絵に描いたようなもので、誰も注目しないだろうよ。
鹿紅葉: それもそうですね。
ところで、どうして、「鹿」といえば「紅葉」と結び付き、「紅葉」といえば「鹿」に結び付くんでしょうか。
主人: どうしてなのかね・・・・・。「花札」にも「「鹿と紅葉」という取り合わせが登場してくるしね・・・・・。
ちょっとネットで調べてみるか。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
いろいろと出てくるね。まず、次のようなのが出てきたな。
「奈良の興福寺の小僧さん達が大勢でお堂で習字をしていたところ、ある日、一匹の鹿が庭に入り込み、小僧さん達が書いた紙を食べようとしたんだそうな。小僧の一人の三作という少年が、鹿を追い払おうとして近くにあった文鎮を投げたところ、運悪く、その文鎮が鹿の急所に当たってしまい、鹿は死んでしまったそうな。
当時、鹿は神の遣いの神鹿とされていたので、鹿を殺せば死罪となる定めだったそうな。まだ子供だった三作少年も例外ではなく、鹿殺しの罪で石子詰の刑に処せられることになったとのこと。
三作少年は、その年齢(13歳)にちなんで、1丈3尺の穴に、死んだ鹿と共に入れられ、十三鐘の鐘が鳴る時刻に石と瓦で生き埋めにされてしまったそうな。
三作少年の死を悲しんだ母親は、供養のために、三作少年が石子詰にされたすぐ側に紅葉の木を植えたんだとか。」
この鹿殺しの罪で、鹿と一緒に生き埋めにされた息子の霊を供養するために母親が紅葉の木を植えたという伝説が、「鹿と紅葉」の取り合わせの由来の一つのように言ってるね。
鹿紅葉: 「鹿と紅葉」の取り合わせの由来にはそんな悲しい伝説があるんですか(><)
主人: うん。
また、百人一首には、
奥山に 紅葉踏みわけ 鳴く鹿の
声きく時ぞ 秋は悲しき
というのもあるね。
前の伝説では、鹿殺しの「鹿」と、母親が植えた「紅葉」を無理に取り合わせて「鹿と紅葉」を創出したような感があるが、この百人一首では、最初から「鹿」そのものと「紅葉」そのものが存在し、それらが自然に結び付いて「鹿と紅葉」という取り合わせになったように感じるよね。
鹿紅葉: 「鹿と紅葉」の取り合わせの由来としては、この百人一首のほうが説得力があるような気がしますね。それに、私個人としましては、悲しい話は嫌ですから・・・・・。
主人: まっ、伝説になったり、百人一首に歌われたりするように、昔から、人々は「鹿」と「紅葉」を取り合わせてきたんだろうね。何が本当の取り合わせの由来なのかよくわからないね・・・・・。
鹿紅葉: そうかもしれませんね。何が本当の取り合わせの由来なのかなどを詮索するのは野暮というものでしょうか・・・・・。
=====================================