ハルは不気味な色合いのグラスを口に運び、グビリと飲んだ。
飲んだ瞬間にハルは俯いた。そして顔を上げる。
「やっぱこれでしょう!」
「わはははは!」
小磯が爆笑する。ママとムツミはやや気持ち悪そうにハルを見ている。
「ハルさん、それは美味いんですか?」
「そりゃ最高よ!ウイスキーはこうやって飲むのが一番美味いんだから」
ハルはもう一口飲む。
「飲むか?」
ハルがグラスをムツミに突き出す。
「飲むか馬鹿!」
「なんだとぉ、こいつの美味さを知らねえくせに!」
「知りたく無いね」
ハルは不満そうにもう一口飲んだ。
普通の人なら勧められても飲まないのかもしれないが、私の中には飲みたいという衝動が湧いてきた。目の前で他人が美味そうに飲んでいる以上、味覚的に強い興味を覚えたのだ。
「ハルさん、それ、どんな味がするんですか?」
「ん?飲む?」
ハルはグラスを私に向かって突き出した。私は席を立ってハルに近づいた。
「直接飲んでもいいんですか?」
「いいよ、いいよ」
思い切って一口、舌の上に流し込んでみる。
「おお!」
思っているたよりも飲み易い。不思議とまろやかな飲み口だ。
「なんかウイスキーと言うより、甘くないミルクセーキみたいな味わいですね。アルコール分をあまり感じない、まろやかな口当たりですよ。結構いけますよこれ!」
「んぉー、そうそうそう!」
ハルは私が味わいを的確に表現したのが嬉しいのか、私の感想に激しく賛同している。
「ホント?」
「嘘でしょ?」
ママとムツミは信じられないという顔をしている。
「ちょっと飲んでみたらどうですか?いいですよねハルさん」
私の勧めに、ママがグラスに恐る恐る口を付けた。
「あ、本当だ、不味くはないね」
「ふーん」
ムツミもまんざらでは無い様子だった。
ハルは満足そうに残りを飲み干し、二杯目を作り始めた。
ハルがその二杯目を半分ほど飲んだ時だった。
「なんかこの味にも飽きて来たなぁ」
ボソっと呟くと、彼はグラスを眺めた。
「くっくっくっ」
小磯が笑っている。
「どうしたんですか?」
「見てりゃ分かるから」
小磯が言い終わる前に、ハルはおもむろに白身の入った器を手に取ると、いきなりグラスに流し込んだ。
「醤油頂戴!」
いきなりハルが叫ぶ。ママが醤油挿しをカウンターに置いた。ハルは醤油をグラスに垂らすと、マドラーでかき混ぜ始めた。
「うわっ、何してんの?」
ムツミがハルの行動に気付いて叫ぶ。ハルは気にせず、攪拌を終えたマドラーをグラスから引き抜いた。てろーんとやや粘性のある液体が垂れる。間違いなく白身だ。ハルは気にせずマドラーをアイスペールに突っ込んだ。
「おおー、小磯さん!これ、卵かけご飯の味がするよぉ」
ハルはその液体を一口飲むと、大声で感想を言った。
「がははは、ハル、俺に報告しなくてもイイから」
「あ、木田さんも飲む?」
さすがにこれはなんとなく腰が引ける。
「いや、遠慮します」
ハルはこの後、ママに納豆と豆腐を出させると、それをグラスに追加した。
「おほほほ、いよいよハルちゃんスペシャルが完成だよぉ!」
ハルは大きな体を揺すると、不気味な流動食のような液体を喜んで『食べて』いる。
「わはははは!もう止まんないよ、あいつは」
小磯は爆笑している。ムツミは完全に引いてしまい、ハルに近寄らなくなっている。
「お、ソースもいけるね!」
ハルはさらに異物を投入して行く。これは罰ゲームでも無く、イジメでも無い。ただ単に本人が自ら行なっているのだ。
「ちゃあ、酢は失敗だ、これはちょっとキツイなぁ!」
ハルが大声で叫んでいる。
この夜、私には彼の味覚のボーダーラインが理解できなかった。
飲んだ瞬間にハルは俯いた。そして顔を上げる。
「やっぱこれでしょう!」
「わはははは!」
小磯が爆笑する。ママとムツミはやや気持ち悪そうにハルを見ている。
「ハルさん、それは美味いんですか?」
「そりゃ最高よ!ウイスキーはこうやって飲むのが一番美味いんだから」
ハルはもう一口飲む。
「飲むか?」
ハルがグラスをムツミに突き出す。
「飲むか馬鹿!」
「なんだとぉ、こいつの美味さを知らねえくせに!」
「知りたく無いね」
ハルは不満そうにもう一口飲んだ。
普通の人なら勧められても飲まないのかもしれないが、私の中には飲みたいという衝動が湧いてきた。目の前で他人が美味そうに飲んでいる以上、味覚的に強い興味を覚えたのだ。
「ハルさん、それ、どんな味がするんですか?」
「ん?飲む?」
ハルはグラスを私に向かって突き出した。私は席を立ってハルに近づいた。
「直接飲んでもいいんですか?」
「いいよ、いいよ」
思い切って一口、舌の上に流し込んでみる。
「おお!」
思っているたよりも飲み易い。不思議とまろやかな飲み口だ。
「なんかウイスキーと言うより、甘くないミルクセーキみたいな味わいですね。アルコール分をあまり感じない、まろやかな口当たりですよ。結構いけますよこれ!」
「んぉー、そうそうそう!」
ハルは私が味わいを的確に表現したのが嬉しいのか、私の感想に激しく賛同している。
「ホント?」
「嘘でしょ?」
ママとムツミは信じられないという顔をしている。
「ちょっと飲んでみたらどうですか?いいですよねハルさん」
私の勧めに、ママがグラスに恐る恐る口を付けた。
「あ、本当だ、不味くはないね」
「ふーん」
ムツミもまんざらでは無い様子だった。
ハルは満足そうに残りを飲み干し、二杯目を作り始めた。
ハルがその二杯目を半分ほど飲んだ時だった。
「なんかこの味にも飽きて来たなぁ」
ボソっと呟くと、彼はグラスを眺めた。
「くっくっくっ」
小磯が笑っている。
「どうしたんですか?」
「見てりゃ分かるから」
小磯が言い終わる前に、ハルはおもむろに白身の入った器を手に取ると、いきなりグラスに流し込んだ。
「醤油頂戴!」
いきなりハルが叫ぶ。ママが醤油挿しをカウンターに置いた。ハルは醤油をグラスに垂らすと、マドラーでかき混ぜ始めた。
「うわっ、何してんの?」
ムツミがハルの行動に気付いて叫ぶ。ハルは気にせず、攪拌を終えたマドラーをグラスから引き抜いた。てろーんとやや粘性のある液体が垂れる。間違いなく白身だ。ハルは気にせずマドラーをアイスペールに突っ込んだ。
「おおー、小磯さん!これ、卵かけご飯の味がするよぉ」
ハルはその液体を一口飲むと、大声で感想を言った。
「がははは、ハル、俺に報告しなくてもイイから」
「あ、木田さんも飲む?」
さすがにこれはなんとなく腰が引ける。
「いや、遠慮します」
ハルはこの後、ママに納豆と豆腐を出させると、それをグラスに追加した。
「おほほほ、いよいよハルちゃんスペシャルが完成だよぉ!」
ハルは大きな体を揺すると、不気味な流動食のような液体を喜んで『食べて』いる。
「わはははは!もう止まんないよ、あいつは」
小磯は爆笑している。ムツミは完全に引いてしまい、ハルに近寄らなくなっている。
「お、ソースもいけるね!」
ハルはさらに異物を投入して行く。これは罰ゲームでも無く、イジメでも無い。ただ単に本人が自ら行なっているのだ。
「ちゃあ、酢は失敗だ、これはちょっとキツイなぁ!」
ハルが大声で叫んでいる。
この夜、私には彼の味覚のボーダーラインが理解できなかった。


















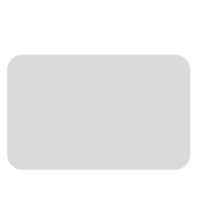

『ハルちゃんスペシャル』が常態化していたあの世界は、もうありません。
この前は『現役女〇大生キャバクラ』状態でした。「意気地なしぃー」っていう合いの手、ハマります・・・。