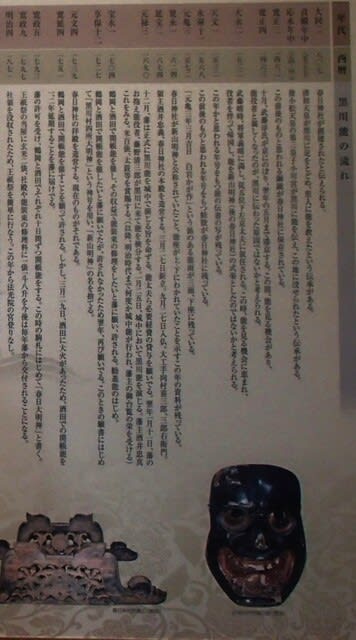日和山公園の木造六角灯台と酒田海上保安部所属船艇。酒田港。
2024年9月12日(木)。
本日は、日本海に浮かぶ離島である飛島(とびしま)の見学である。飛島へ向かう客船が出航する酒田港は「さかた海鮮市場」の隣にある。その前に酒田市北部にあるイオンで食料の補給をした。客船は9時30分に出て、10時45分に飛島勝浦港着。復路は13時45分発で酒田港15時着である。見学時間は3時間弱である。定刻どおり出航すると日和山公園の木造六角灯台と酒田海上保安部所属船艇が見えてきた。

20メートル型巡視艇べにばな (CL104)。
総トン数26トン H11.3月就役。すずかぜ型巡視艇。CL(Craft Large)型。

高速特殊警備船つるぎ(PS201)。
全長50.0m×幅8.0m総トン数 220トン H18.3月就役。PS型(Patrol Vessel Small=小型巡視船)。20ミリ機関砲装備。日立造船製。2001年竣工。



川のような酒田港から遠ざかる。



飛島の西方沖に浮かぶ烏帽子群島は火山岩でできた島々で、熔岩がゆっくりと冷えて固まったときにできる六角形の柱状の岩石(柱状節理)がたくさん見られ、地元では「材木岩」とも呼ばれている。
烏帽子群島の隣に位置する御積島(おしゃくじま)は粘り気の強い溶岩でできた島で、北側にある洞窟の内部は黄金色に輝くうろこ状の岩壁になっており、そのため龍が住む神秘的な場所として、北前船の船乗りや島民に信仰され、今も女人禁制の島として崇められている。うろこ状の岩壁になった要因はウミネコが関係しているといわれている。


飛島は、山形県酒田市に属し、酒田港から北西39㎞の沖合に浮かぶ。面積は2.75k㎡。最高標高は68m。島の平均標高は約50mで平坦な台地状の地形である。
山形県で最も北に位置し、本土からの距離は秋田県のほうが近い。古来、新潟県の粟島、佐渡島とは一直線に結ばれた海の道であり交流があった。
山形県唯一の有人島で島の東側(本土に面した側)の勝浦、中村、北側の法木の計3ヶ所の集落によって構成される。人口は 146人(2024年7月)。
飛島は約1000万年前に海底噴火によって形成され、奥尻島まで続く海底山脈の一部が海面上に出て島となって海底から飛島地塊が聳え立つ。900万年~ 200万年前に隆起や断裂、陥没により海盆や地塊が形成された。200万年~ 1万年前までに地塊は台地状になり、段丘が形成されたと考えられる。
島内では、縄文時代早期の終わり頃(約6000年前)などの遺物を出土する葡萄崎遺跡が最古の人類居住の痕跡を残す。葡萄崎遺跡に近い蕨山遺跡からは、東北地方北部の円筒系の土器(円筒上層b式期)と、東北地方南部の大木系土器(大木7b式期)が共に出土した。島内の台地上には、縄文時代のほぼ全期間を通して人々が住んでいたことを示す遺跡が分布する。弥生時代・古墳時代の遺跡は見つかっておらず、この期間には、飛島は生活の舞台とはなっていなかったと考えられる。
島の海岸に面した洞窟遺跡「テキ穴遺跡」からは、9世紀から10世紀前半頃の平安時代の人骨や須恵器、土師器、骨角器などが発見された。人骨は鶴岡市の致道博物館に展示されている。
平安時代には阿倍氏、清原氏の支配下に置かれた。15世紀には、羽後の豪族仁賀保氏の所領となる。戦国時代末期に仁賀保氏が常陸国武田へ移封されると最上氏の所領となった。最上氏、酒井氏が支配した近世には、特産のスルメを年貢として課されていた。
江戸時代には庄内藩の所領であり、酒田港に出入りする北前船の潮待ち港や、水や食料の補給港として重要な位置を占めた。
1996年、西海岸の荒崎が日本の渚百選に選ばれ、2016年「鳥海山・飛島ジオパーク」として日本ジオパークに認定された。
勝浦集落にある勝浦港と酒田市の酒田港の間で、酒田市定期航路事業所により定期船である貨客船「とびしま」が運航されている。所要時間は約1時間15分。
島内にバスやタクシー、レンタカーなどはない。観光用無料自転車および有料の電動アシスト自転車がある。島内は東側海岸線と島中央部の台地上に道路が走っており、大部分が平坦であることから、自転車での移動は容易である。

飛島の勝浦港に着いた。無料自転車は東に100mほどの場所に置いてあったので借りた。東から反時計回りに海岸から台地に上がり、西方向へ一周することにしていた。まず、東京都内で交通違反をした反則金納付が最終日になっていたので、飛島郵便局へ立ち寄った。納付書の書式が珍しいと言われて時間がかかった。その間にATMから数万円引き出した。その後、東に進みテキ穴遺跡へ向かった。




テキ穴遺跡。
勝浦と中村の境界であるホグラ岬の剣ヶ峯にある海食洞で、デデッポ(山鳩)穴の俗称もあるが飛島洞窟とも呼称する。平安時代の9世紀前半と10世紀前後に居住した人骨と土器類が発見されている。洞窟は海岸線に沿った道路際に入口がある。
開口部は幅、高さ共に1.5mほどであるが、洞窟内は三叉状になって3つの洞により構成され、入口より約25mで逆V字形に左折した第三洞で人骨や土器類が発見された。第3洞は奥行きが23m、天井部の高いところで4m、幅広いところで5mある。
人骨は22体分あり、共に出土した土器類から9 - 10世紀の年代が考えられる。人骨は鶴岡市の致道博物館に展示されている。



人が1人通れるくらいの狭い穴がつづく。中はひんやりと暗く、異質な空間である。

奥には深入りせず途中で引き返した。
とびしま総合センターへ立ち寄って、展示はないか、と尋ねると、ない、と言われたのでトイレだけ借りた。ここから台地上へ自転車を押しながら登った。小物忌神社への標識があり、鳥海山の大物忌神社と対をなす神社というので見学したかったが、時間を要しそうだったので諦めた。台地上の車道を西に進み、西海岸の荒崎海岸へと脇道へ入った。