荒木矩著『大日本書画名家大鑑』です。
黒い大部のこの本も、かつて、骨董屋の主人の横に、デンと鎮座してた骨董屋アイテムです。

まず、その圧倒的ボリュームに驚かされます。
『大日本書画名家大鑑』は、『伝記編』『落款印譜編』『索引編』の3部作になっています。本の奥付には、昭和50年発行となっていますが、序文を読むと、昭和9年に発刊された『大日本書画名家大鑑』をあらためて刊行したものであることがわかります。
『大日本書画名家大鑑 伝記上編』第一書房、昭和50年

大きな重い本です。1300頁、2.2㎏あります。なんと、これは『伝記上編』ですから、『伝記下編』もあるのですね。両方合わせれば、4㎏以上。『大日本書画名家大鑑』は古本屋で買ったので、『伝記下編』を欠いています。『大日本書画名家大鑑』は全4巻なのですね。最近まで気がつきませんでした(^^;

『大日本書画名家大鑑 伝記編』では、上古より昭和初めに互る名家二万人を網羅し、各人の概要を述べています。また、 日本における書画の由来及び変遷を編年的に叙説しています。

「石泉」の名をもつ人は、9人もいるのですね。
『大日本書画名家大鑑 落款印譜編』第一書房、昭和50年。

書画の落款と印象を、作家別に収録した大著です。1300頁、1.8㎏あります。この種の本の大御所的存在です。付箋の多さからも、私の座右の書であることがわかりますね(^^;

膨大なデータは、明治以前と明治・大正・昭和の二大別に分類収載されています。
以下の著者の言から、本書に対する著者の思いと自負がうかがえます。
一、從來、落款印譜書の刊行せられたるもの數多ありと雖も、概ね得失長短ありて、未だ満足の聲を耳にせず、此處に於て書畫愛好家多年の渇望を醫し、併せて、鑑定家の絶好資料たらしめんがため本書を発刊せり。
一、惟ふに真贋の鑑定は、運筆、傅彩の巧拙によること勿論なるも、又、一に落款印章によると言ふも過言にあらず、されば本書はあらゆる苦心を重ねて古今名家の落款印章花押を廣く蒐集し、原大の儘を探錄して、以て完璧を期したり、收載印顆の多種なること本書の右に出づるものなしと信ず。
実は、書画の落款印象に関する類書はいくつもあります。とにかく、『大日本書画名家大鑑』は大きく重いので、これを繰るにはやる気を奮い起こさねばなりません。チョコッと調べたい時などは、二の足を踏みます(^^;
なので、よく使うのはハンディタイプのこれ。
落款字典編集委員会『必携 落款字典』柏美術出版、1982年

460頁、620g、片手で繰れます。
ところが・・・・

『大日本書画名家大鑑』(上)と『必携 落款字典』(下)とをくらべてみると、載っている落款は、同じように思えるのです。同じ作者の落款だから当たり前だと言われるかも知れませんが、同一印章を用いても、媒体や押し方、印章の古さなどによって、細部は異なってきます。同じ作品の落款を載せているのなら可能ですが、実際上はありえません。どうもこの業界では、使いまわしが一般的なようです。著作権などやかましく言われなかった頃の大らかな慣行でしょうか(^.^)
『大日本書画名家大鑑 索引編』第一書房、昭和50年。

『大日本書画名家大鑑 伝記編上下』、『大日本書画名家大鑑 落款印譜編』の膨大なデータにアクセスするには、どうしてもしっかりとした索引が必要です。

800頁、1.1㎏ほどあります。姓氏索引はもとより、別称、総画、音訓索引とに分類し、それぞれで検索ができるようになっています。他に類をみない索引です。
4巻そろえば、重さ7㎏、総頁5000頁ほどにもなるこの大著を著した荒木矩(ただし、慶応元(1865)ー昭和十六(1941))とは、一体どんな人物なのでしょうか。『大日本書画名家大鑑 落款印譜編』の序文によれば、彼は、明治33年から京都市美術工芸学校、京都市立絵画専門学校(現京都市立芸大)に勤務し、国文学、漢文学を教えました。また文展、帝展などに関与して、多くの美術家と交流しました。大正14年に退職し、その後10年間、日本美術史の資料収集に没頭し、昭和9年『大日本書画名家大鑑 』を著しました。
明治人だからこそ出来た壮大なライフワークなのですね。













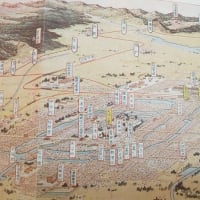




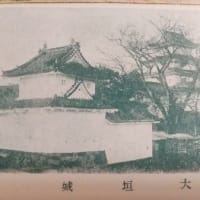
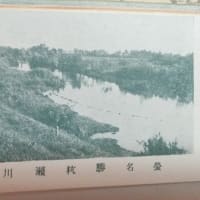
ここ10年、情報取得手段の激変は全く驚くばかりです。
遅れて生きている私など、一周遅れでぐるっと回ってもとに地点にいるかのような不思議な感覚です(^.^)
幸か不幸か、骨董は世の変化にかなり遅れをとっているので、なんとか行けています(^^;
でも昔は、特にインターネットの無い時代には情報・知識を得るために、大変重要な辞典であったろうと思われます。
また、そのような近代的なツールがあっても、瞬時に見比べることの利便性はネットに適わないものもあります。
私の持っている重い辞書と言えば、多くの方がお持ちの研究社の「新和英大辞典」・岩波書店の「広辞苑」・三省堂の「模範六法」くらいで、重さもかなり軽いです。他に工学系の大辞典が一冊ありましたが、後輩に譲って書名も忘れました。「新英和大辞典」(研究社)なんか、誰に貸したか忘れて戻らずそのままです。
10数年前に5cm厚位の「パソコン大辞典」的なものを数千円で買いましたが、今では全くと言ってよいほど役に立たず、捨てました。
初心者でも古い情報は間違いの元ですから・・・。
「大日本書画名家大鑑」なんぞは骨董屋さんの虎の巻で、所有しているだけ「お宝」になるのではないでしょうか。羨ましい!
それを、ヨイショと持ち上げ、必死になって落款、印章を照合する・・・骨董は、体力と気力の勝負ですね。
おっと忘れていました、その前に、何よりも資力が(^^;
まあ、そこそこの値段で手に入る今回の落款印譜集を手元に置いておくと、何となく落ち着きます。
このような、辞典で勉強されて、スゴイ!
2・2k片手で持てないです。
うちにある、日本語大字典も同じ重さで
片手で持てません(;^_^A
私は見たことがありません(~_~;)
多分、私が通っていた骨董屋は、田舎の小さな骨董屋で、また、老舗でもなく、知識も浅い骨董屋でもあったので、このような立派な本を備えていなかったからだろうと思います。
「書画骨董」と言いますから、「書画」のコレクションを始めようとすると、この本は必須アイテムかもしれませんね。
私も、少しは「書画」を所持してはいますが、「書画」のコレクションをしようとまでは思わなかったものですから、幸い、このような本を買わずに過ぎました。
「書画」のコレクションをするには、このような大部の本で勉強しなければならないわけで、大変ですね!
流石です😉この分厚さ、様々の落款の鑑定には、必須本ですね😃
もっとも、小生には、隷書が読めないので、枕にはちょうど良い厚さ?です。これで高額鑑定の夢でも😪💤💤
琴山印も、だんだん使って来ると、角が欠けて来ますね。
又お邪魔致します😆
本格的な書籍で、お調べになられるのですね。
付箋の数が、半端ない!
重い厚い書物
でも、楽しさ100倍
楽しいお時間をお過ごしください^^
厚さが半端ではないですね!!
これは付箋がなければ読みたい所を探すのも一苦労ですね笑
書の関連の本の情報量は膨大ですね。
私の集めている皿とは比べ物にならないです。
その分きっと調べる楽しみが大きそうで良いですね。
実に奥が深い素敵な分野だと感じます。
それにしても遅生さんの守備範囲の広さがすごいです(^^)