10月に入ったというのに、相変わらず、畑では、朝顔と酔芙蓉が咲き乱れています。
両方とも、時間がたつと色が変化します。
朝顔は、青色→赤紫
酔芙蓉は、白→濃ピンク
https://blog.goo.ne.jp/chisei/e/520f1e881d892bd64fa30a7dd020e799?fm=entry_awc
https://blog.goo.ne.jp/chisei/e/a22f36065541d49fab81c3ee23582879
畑では根がよく張り、十二分に栄養分が補給されるので、色が変化する前の咲いたばかりの花と、色が変化した前日の花とが混ざり合って、百花繚乱の趣があります。

これらの色の変化は、アントシアニン色素によると言われています。
アントシアニンは、pHによって色が違います。酸性では赤、アルカリ性では青です。
青色の朝顔では、咲いたばかりの花のアントシアニンは弱アルカリ性に保たれて青色なのですが、時間がたつにつれて酸性になり、色は赤紫に変わります。
酔芙蓉では、時間がたつにつれ、花の中でアントシアニンが生成され、白い花は次第に赤色に変わっていきます。

夕方に摘んだ朝顔の花です。赤紫色(酸性環境)になっています。
手で揉めば、簡単に潰れて色液が出てきます。それを水に溶かせば、

綺麗な赤紫色の水が得られます。
じゃあ、アルカリ性にしたら、どうなる?
これを入れてみました。

見事に、青色に変わりました。

朝顔の青色は、やはりアントシアニンだったのですね。
では、酔芙蓉はどうでしょうか?

夕方、酔芙蓉の花をどっさり採って、
手で揉みました。

赤色の液が出てくる、と思いきや
ただベタベタするだけです(^^;)
色らしきものはどこにもありません。
理由は二つ。
1)元々赤色色素が少ない。酔芙蓉の花びらをよく観察してみると、全部が赤色にはなっていません。まばらに赤。離れて見ると、赤く見えますが、実際は、うっすらと赤いだけなのです。
2)色素を取り出し難い。朝顔の花は、揉めばすぐに色素が出てきます。ところが、酔芙蓉の花は、どれだけ揉んでも、まったく色は出てきません。花の細胞が相当に頑丈なのです。
わずかにしかない色素が、なかなか外へ出てこない(>_<)

仕方がないので、木槌でしつこく潰しました。
それを水に入れて、布でこしてみました。
うーん、色がついていない。失敗?
ダメもとで、そこへ重曹を入れてみました。

少し色がつきました。
写真ではわかりづらいですが、黄緑色です。アントシアニンの可能性ありです。アントシアニンには、いろいろな種類がありますし、同じアントシアニンでも金属と結びつくと異なる色調になるからです。
以上、アルカリ性液中の、朝顔(左)と酔芙蓉の花(右)のしぼり汁です。

両方の花の色素、アントシアニンなら、酸性では赤系統の色に変化するはずです。

朝顔の花の液に、クエン酸を入れてみました。

見事に、赤紫色に変化。
酔芙蓉の花の液は、

非常に薄いですが、ピンクに変わりました。
アルカリ性から酸性への色の変化。やはり、朝顔、酔芙蓉の花色は、アントシアニンによるものだとわかります。
朝顔では、アントシアニンの置かれたpH環境、酔芙蓉では、時間経過によるアントシアニン生成が、色変化の正体だったわけですね。
アントシアニンは、花だけではなく、実、茎、葉にも広く含まれています。
ここで、大きな疑問が・・・植物は何のために、アントシアニンを作るのでしょうか?
目だつ色で鳥に食べてもらって、種を遠くまで運んでもらう?・・・・・
果肉よりも、内部の種の方が色が濃いことが多いし、葉、花、茎にもアントシアニンは含まれているし・・・
結局、よくわからないです。
現在考えられていることは、アントシアニンが植物の保護に役立っているのではないかということです。何らかの原因で、光合成が十分進まない場合、余った太陽エネルギーによって活性酸素ができてしまうのを防ぐ働きをしているらしい。また、アントシアニン自身が抗酸化作用をもっているので、植物の老化を防ぐ働きもする訳です。
アントシアニン類だけで20種以上、他のポリフェノール類を含めれば、非常に多種多様な抗酸化物質を植物が作り出しています。身近なところでは、お茶のカテキン。日本へお茶は、薬として入ってきたのもうなずけますね。
考えてみれば、どうでもいいことに追いまくられている毎日ですが、明日は、朝顔や酔芙蓉の色の変化を楽しみながら、朝と夕に、ゆっくりとお茶を飲んでみようと思います。













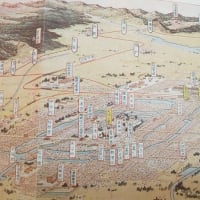




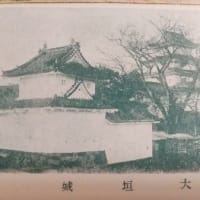
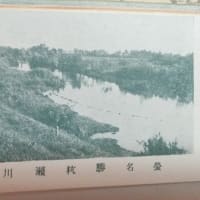
いろいろと実験されていますね。
酔芙蓉は色液が出ないんですか。
先日、酔芙蓉のしぼんだ花を白い靴下で踏んでしまい、靴下がピンクに染まってしまいました。
慌てて水で洗いましたが色が落ちませんので、漂白剤を使って落としました。
その経験から、色液が多く出るのかと思いましたが、意外に感じました。
明日は、朝と夕に、ゆっくりとお茶を飲みながら、また別な実験をするんですか、、、?
でも、たいがいの花の色素は弱いですから、しばらくすれば色はなくなります。
蓑虫山人という明治の放浪画人は、草花で飄々とした淡彩画を描いたと言われていますが、それは作り話です。古今東西、多くの発明家が、美しい花を使おうとしましたが、ほとんどダメでした・・・・うつろいやすきもの、○○○ごころと花の色(^^;)
ps。紅花は、花色素の利用が成功した数少ない例です。
是非、来年には紫陽花の七変化についても。
既に、土のpHとアルミニウムとか言われていますが。
芙蓉から、身体にいいと言われる、ハイビスカスティーを思い出したです。
紫陽花は本当に不思議ですね。
pHや金属は、色素の色に影響するので、七変化をうみだす可能性は十分にあると思います。
ハイビスカスティーにしても、現在利用されているのは、生えているときと収穫した後とで、あまり色調が違わない色素です。
でも、花色の妙は、やはり生きているときにあります。生きている状態で物事を精緻に観察するのは難しいです。
見事に色が変わっていきます。
これは知識と好奇心のたまものですね。
おかげで、骨董も、広く浅くの何でも屋になってしまいました(笑)
小学校の実験室を思いだし、ワクワクしたあの頃、胸をかきむしるほど懐かしいです。
なかなかできませんが、無心になれれば幸せが実感できます。
雑念、雑事無用といきたいですね(^.^)