古九谷金銀彩の中皿です。

径20.7㎝、高4.7㎝、高台8.2㎝。
びっしりとジカンが見られます。

ジカンは裏にまでは抜けていないようです。
半磁半陶の素地に、白釉で化粧掛けしています。

中央には、生花(盆栽?)が描かれています。赤も使われています。黒の部分は、銀か鉄かはっきりしません。

皿の外周部には、陽刻がなされています。模様は不明です。

床の間、違い棚の上に置いても様になります。
この皿、普通は、伊万里金銀彩盆栽紋皿と言われている品です。
中央の模様は、盆栽ではなく、やはり生花だと思います。花は、桔梗でしょうか。
一番の問題は、産地です。たいていの金銀彩皿は、藍九谷の美しい生地の上に金銀彩をおいています。
ところが、この皿の生地は、通常の伊万里とはかなり異なります。伊万里の白い磁器からは程遠い粗悪な生地。そこへ白化粧をして、その上に金銀彩で描いています。
伊万里脇窯、吉田窯あたりの品でしょうか。













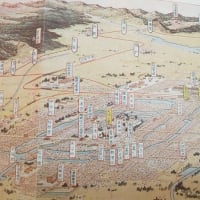




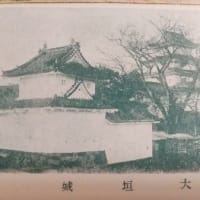
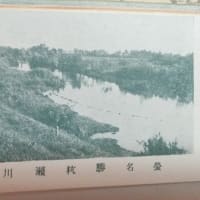
ここにも出てきましたか(笑)。
私も、この文様は、盆栽文ではなく、生け花文だと思いますね。
花は、桔梗ですよね。そうすると、葉っぱの形が違い過ぎますものね。
だいたい、文様名など、もともとは、数寄者や古美術商などが付けたんでしょうから、知りもしないで付けますから、いい加減ですよね(笑)。
これ、何処の窯で作られたんでしょうね。
有田でも、「ひび焼」とかいって、半陶半磁の物も作られていますよね。
確かに、吉田窯という線も考えられますね。
もう少し、吉田窯について詳しく研究され、本も出されると助かるんですがね。
私も、俗には古九谷と言われるんでしょうけれど、どうも、いまいち、腑に落ちない物を1点所持しています。
密かに、吉田窯製かなと思ているですが、自信がありません。生きているうちに発表できるかどうか分かりませんが、今は、発表する気になりません(><)
私も、足軽で参戦。しかし、装備があまりにも貧弱、早晩討ち死でしょう(*_*)
中野焼のようなひび焼なら、もっときれいにジカンが入っていると思うのですが・・・・半陶半磁で甘手。陽刻まで入っているので余計にややこしいです。
密かな古九谷、ぜひご披露を。どのみち、古九谷の定義などあいまいですから(^。^;
七寸サイズで見込みにちょっとだけ絵付けというのが珍しく
ワタシは初めて見るタイプの品です。
土の感じや釉薬感が独特なのは確かのようで、高台の感じとかは初期赤絵に近い印象です。
さすがにユニークな品をお持ちですね!。
これだけ多く余白をとって、小さな絵を描くのは、結構勇気が要ります。この頃はまだ、様式がきちっと決まっていなくて、いろんな事をやってみる自由度が大きかったのではないでしょうか。
三分の一高台とまではいきませんが、初期の雰囲気は残っていますね。
白磁を活かした見込みのみの花の図ですね。
少し甘手だったのかなと思います。
違い棚で主役として収まっていますね。
初期の頃だからできたのではないでしょうか。
甘手で嵌入。おかげで 何とか手が届きました。
床の間、普段は物でいっぱいですが、皿一枚に整理すると見違えるほどスッキリしますね(^。^;)