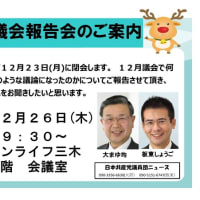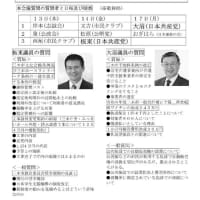7月10日(火)~12日(木)にかけて行政視察に行ってきました。
7月10日秋田県能代市は秋田県北西部に位置して、H18年に能代市と二ツ井町が合併した町でH24年3月末現在59,204名、24,524世帯、面積は426,740平方kmの町です。資料によると昭和40年に二つの自治体の合計が85千人をピークに50年から平成にかけて7万人台、平成10年代には6万人台となり平成23年には6万人を切る状況にあるようです。
視察項目は、教育環境整備として学校統廃合と木材を多用した施設整備についてです。
12の小学校が統廃合により4つの小学校となっています。
印象的だったのは、あくまでも地域の要望による統廃合で、教育委員会や行政による上からの統廃合は行っていないとのことです。
共産党の立場として統廃合と言えばあまり良い印象はないですが、合併を望んでいない地域については合併を行っていませんとのことでした。
また、小学校から中学校の進学がそのままスライドする地域では小中の併設校となってるのも特徴的だと思いました。ここでも、あくまでも地域の要望に基づいてこのような形を取っていますとの説明でした。
次に、木材を多用した施設整備ということで、私たちが訪問した二ツ井小学校は全面的な木造校舎(※といっても一部鉄骨造)で木の香りがする立派な校舎でした。
能代市は古くから、秋田杉の集散地として製材、木材加工業が盛んで、木材産業は市の基幹産業の一つとなって栄えてきたことから「木都」にふさわしいまちづくりを進めているとのことです。
木材産業への経済波及効果と木のぬくもりと安らぎのある快適な居住環境を創造しようとの考えから学校だけでなく、可能な限り今後の公共施設整備にあたっては木造・木質化での建設整備を行うことを基本としているとのことでした。
産業と小中等教育との連携という事がキーワードになるかと思いますが、わが町三木市で小学校・中学校教育の中でどのように金物が使われてるのかもう一度調べる必要があると思っています。
その上で、波及効果も必要ですが、道具を使ったものづくりによる教育効果といことも大事なのかなと思っています。
7月10日秋田県能代市は秋田県北西部に位置して、H18年に能代市と二ツ井町が合併した町でH24年3月末現在59,204名、24,524世帯、面積は426,740平方kmの町です。資料によると昭和40年に二つの自治体の合計が85千人をピークに50年から平成にかけて7万人台、平成10年代には6万人台となり平成23年には6万人を切る状況にあるようです。
視察項目は、教育環境整備として学校統廃合と木材を多用した施設整備についてです。
12の小学校が統廃合により4つの小学校となっています。
印象的だったのは、あくまでも地域の要望による統廃合で、教育委員会や行政による上からの統廃合は行っていないとのことです。
共産党の立場として統廃合と言えばあまり良い印象はないですが、合併を望んでいない地域については合併を行っていませんとのことでした。
また、小学校から中学校の進学がそのままスライドする地域では小中の併設校となってるのも特徴的だと思いました。ここでも、あくまでも地域の要望に基づいてこのような形を取っていますとの説明でした。
次に、木材を多用した施設整備ということで、私たちが訪問した二ツ井小学校は全面的な木造校舎(※といっても一部鉄骨造)で木の香りがする立派な校舎でした。
能代市は古くから、秋田杉の集散地として製材、木材加工業が盛んで、木材産業は市の基幹産業の一つとなって栄えてきたことから「木都」にふさわしいまちづくりを進めているとのことです。
木材産業への経済波及効果と木のぬくもりと安らぎのある快適な居住環境を創造しようとの考えから学校だけでなく、可能な限り今後の公共施設整備にあたっては木造・木質化での建設整備を行うことを基本としているとのことでした。
産業と小中等教育との連携という事がキーワードになるかと思いますが、わが町三木市で小学校・中学校教育の中でどのように金物が使われてるのかもう一度調べる必要があると思っています。
その上で、波及効果も必要ですが、道具を使ったものづくりによる教育効果といことも大事なのかなと思っています。