【私の正名論】評論家・呉智英 言葉の誤読による糾弾
2008.6.11 02:58
良い目的のためなら誤った知識を流し無知を煽(あお)ることが許されるのか。古来からあるテーマだが、近代国家では許されることではない。なぜならば、国家意志は国民の総意によって決定されるからである。
仮に「良い決定」がされたとしてもそれが「無知」の上に成立しているなら、いずれツケが回ってくる。そのうち、無知は正義だ、ということになりかねない。
六月四日付朝日新聞の社説を読んでそう思った。「アイヌ民族を日本の先住民族として認めるべきだ」。今国会の決議を支持して、同社説はこう書き出す。趣旨にはむろん私も賛成だ。しかし、この社説の中におかしな記述がある。
「明治以来、日本政府はアイヌ民族を『旧土人』と呼び」「この差別的な呼び方そのものが、先住の事実を認めたに等しい」
変な記述だ。差別的な呼称が、どうして先住の事実を認めたことになるのか。先住民の権利は差別の上に成り立つのだろうか。
この社説は「土人」は差別語だという謬説(びゅうせつ)に基づいている。「土人」とは「土着の人」「土地の人」という意味である。一九七〇年代に広がった、差別語狩りの愚行以前はごく普通に使われていた。
江戸時代の方言研究書『物類称呼』には「虹のことを、東国の小児は“のじ”と言い、尾張の土人は“鍋づる”と言う」とある。尾張(名古屋)は徳川御三家の一つだ。そこに住む人を土人(土地の人)として別に不思議はない。
昭和期の朝日新聞にもこんな記事がある。一九三八年十二月四日付だ。「〔山形県では〕こういう現象を土民は年に一度は体験する」(錦三郎『飛行蜘蛛』より)
戦後でもそうだ。一九六〇年代まで広く使われていた名英和辞書『新簡約英和辞典』(研究社)はIndianを「アメリカ土人」としている。アメリカ土着の人という意味であることは明らかだ。
「土人」が「土まみれの野蛮人」の意味に拡大解釈され、ほんの三十年程前からその意味にのみ解釈されるようになった。これは前述の差別語狩りによる。「土人」を差別語と“認定”し社会から抹殺したために本来の意味が分からなくなったのである。
明治時代に作られた「北海道旧土人保護法」が差別的な名称の法律だとして国会の議論の的になったのは一九八六年のことだ。この法律は保護の名目でアイヌ人の権利を制限する差別的な内容の法律である。内容が差別的なのであって、名称が差別的なのではない。北海道に「旧(もと)から住んでいる土地の人」という名称のどこが差別なのか。少なくとも明治時代には「土人」は本来の用法で使われていたはずである。こんな簡単な事実も知らず、中曽根康弘首相(当時)を初め閣僚も国会議員も左右を問わず、差別的な名称には驚いたと、それこそ驚くべき発言をした。
言葉がわからず、従って歴史がわからず、従って文化がわからない。困った良識家ばかりだ。
必ずや名を正さんか。孔子の言(げん)だ。「名」は言葉。言葉が正しくないと社会も文化も混乱する。迂遠(うえん)なようでもまず名を正す(正名)のがすべての基本である。(くれ ともふさ)
2008.6.11 02:58
良い目的のためなら誤った知識を流し無知を煽(あお)ることが許されるのか。古来からあるテーマだが、近代国家では許されることではない。なぜならば、国家意志は国民の総意によって決定されるからである。
仮に「良い決定」がされたとしてもそれが「無知」の上に成立しているなら、いずれツケが回ってくる。そのうち、無知は正義だ、ということになりかねない。
六月四日付朝日新聞の社説を読んでそう思った。「アイヌ民族を日本の先住民族として認めるべきだ」。今国会の決議を支持して、同社説はこう書き出す。趣旨にはむろん私も賛成だ。しかし、この社説の中におかしな記述がある。
「明治以来、日本政府はアイヌ民族を『旧土人』と呼び」「この差別的な呼び方そのものが、先住の事実を認めたに等しい」
変な記述だ。差別的な呼称が、どうして先住の事実を認めたことになるのか。先住民の権利は差別の上に成り立つのだろうか。
この社説は「土人」は差別語だという謬説(びゅうせつ)に基づいている。「土人」とは「土着の人」「土地の人」という意味である。一九七〇年代に広がった、差別語狩りの愚行以前はごく普通に使われていた。
江戸時代の方言研究書『物類称呼』には「虹のことを、東国の小児は“のじ”と言い、尾張の土人は“鍋づる”と言う」とある。尾張(名古屋)は徳川御三家の一つだ。そこに住む人を土人(土地の人)として別に不思議はない。
昭和期の朝日新聞にもこんな記事がある。一九三八年十二月四日付だ。「〔山形県では〕こういう現象を土民は年に一度は体験する」(錦三郎『飛行蜘蛛』より)
戦後でもそうだ。一九六〇年代まで広く使われていた名英和辞書『新簡約英和辞典』(研究社)はIndianを「アメリカ土人」としている。アメリカ土着の人という意味であることは明らかだ。
「土人」が「土まみれの野蛮人」の意味に拡大解釈され、ほんの三十年程前からその意味にのみ解釈されるようになった。これは前述の差別語狩りによる。「土人」を差別語と“認定”し社会から抹殺したために本来の意味が分からなくなったのである。
明治時代に作られた「北海道旧土人保護法」が差別的な名称の法律だとして国会の議論の的になったのは一九八六年のことだ。この法律は保護の名目でアイヌ人の権利を制限する差別的な内容の法律である。内容が差別的なのであって、名称が差別的なのではない。北海道に「旧(もと)から住んでいる土地の人」という名称のどこが差別なのか。少なくとも明治時代には「土人」は本来の用法で使われていたはずである。こんな簡単な事実も知らず、中曽根康弘首相(当時)を初め閣僚も国会議員も左右を問わず、差別的な名称には驚いたと、それこそ驚くべき発言をした。
言葉がわからず、従って歴史がわからず、従って文化がわからない。困った良識家ばかりだ。
必ずや名を正さんか。孔子の言(げん)だ。「名」は言葉。言葉が正しくないと社会も文化も混乱する。迂遠(うえん)なようでもまず名を正す(正名)のがすべての基本である。(くれ ともふさ)















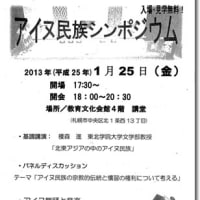

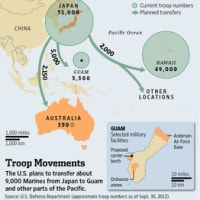


※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます