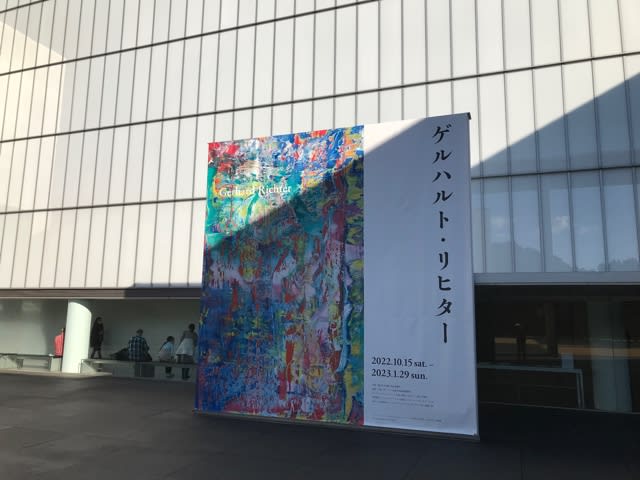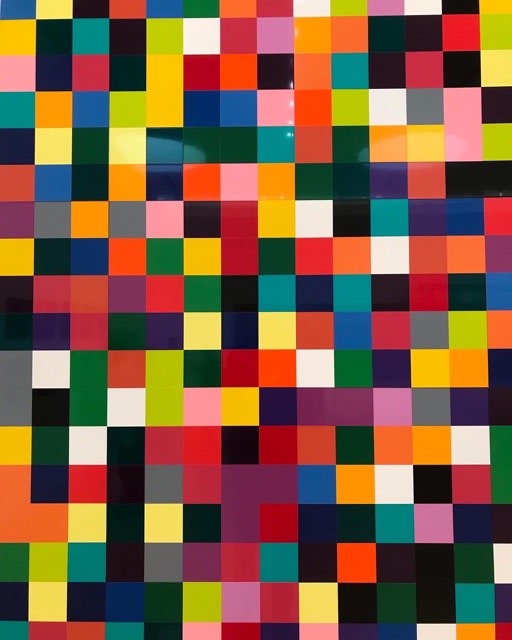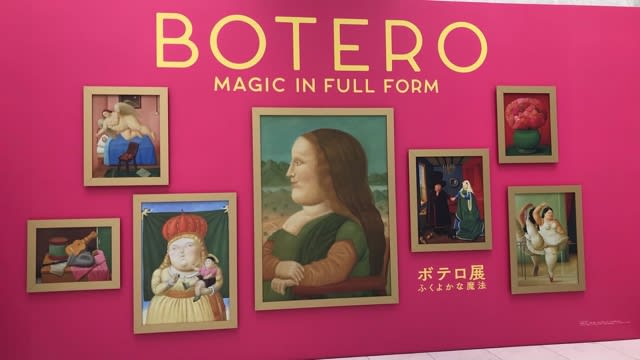今回の展覧会レビューは、異彩を放つ芸術家三人の美術展を鑑賞しましたのでご紹介します。先ずは愛知県美術館で開催中の「展覧会 岡本太郎」です。
史上最大の岡本太郎展と銘打ち開催中の本展、昨年からの中之島美術館、東京都美術館に続き愛知県美術館で現在開催中です。
岡本太郎と言えば、現在も万博記念公園に鎮座する「太陽の塔」や芸術家集団チンポムにより追加された「明日の神話」が思い浮かぶでしょうが、僕の記憶には小学生の頃の太陽の塔や同時期に描かれた原発へのアンチテーゼ作品である明日の神話は断片的な岡本太郎へのイメージしかなく、一番に感じるのはマクセルビデオテープでの「芸術は爆発だ」と叫ぶ奇々怪々な芸術家のイメージが強く残っています。当初は岡本太郎の存在を素直に受け入れることができない状況が続いていました。

しかし、岡本太郎を深く知るにつけて、その類まれなる画家としての技量を秘めながらも他人を介さず自らの意志を作品に注入するからこそ、現在も若者の強い支持を受けアヴァンギャルドの情熱めらめらと噴き上げてくるのでしょう。そんな芸術家の生き様が今回の展覧会に現れているようです。

会場には序章としてなじみの深いまた誰もが愛するパブリックの彫刻作品が、第1章ではパリ時代の幻の油彩画作品と共に初期のドローイング作品を展示、第2章では日本文化を挑発する太郎独特の油彩画作品がずらりと展示、また初期の肖像画やデッサン画は芸術家一家に生まれた太郎の隠された画家の技量を感じます。


第3章では太郎の芸術のルーツとである縄文、弥生文化をベースにした記録写真や作品、第4章では大衆芸術に根差した様々な作品が、第5章では太陽の塔と明日の神話ふたつの太陽をテーマに展開されいます。そして第6章では、大阪万博を境にメディアでの露出がふえ人間、岡本太郎の存在がクローズアップされた時期に描かれた知られざる芸術家・岡本太郎の芸術の眼がが黒い眼として象徴的に居並んでいます。
現代美術の世界において日本の芸術家にも注目が集まっている現在、国際的に通用したであろう岡本太郎。時代を突き抜けて疾走する太郎の精神が脈打つ展覧会に今訪れるべき時ではないかと感じます。
東京都美術館「展覧会 岡本太郎」