(1953/ヴィットリオ・デ・シーカ監督・共同製作/ジェニファー・ジョーンズ、モンゴメリー・クリフト、リチャード・ベイマー/89分)
 アメリカ、フィラデルフィアの主婦メアリーは姉家族の住むローマを訪れ、そこで現地の青年ジョバンニと恋に落ちる。メアリーにはキャシーという7歳の娘がいたが、ジョバンニはキャシーと三人で彼の実家のある田舎町ピサで暮らそうと言う。一旦はその気になったメアリーだが、日が変わると怖くなり、ジョバンニと別れて家族の元に帰ることにした。
アメリカ、フィラデルフィアの主婦メアリーは姉家族の住むローマを訪れ、そこで現地の青年ジョバンニと恋に落ちる。メアリーにはキャシーという7歳の娘がいたが、ジョバンニはキャシーと三人で彼の実家のある田舎町ピサで暮らそうと言う。一旦はその気になったメアリーだが、日が変わると怖くなり、ジョバンニと別れて家族の元に帰ることにした。
せめて別れの言葉を残そうとジョバンニのアパートのドアの前まで来るが、ノックが出来ずにそのまま踵を返して駅に向うメアリー。荷物もまとめずに、姉にさよならを言う余裕もないほど悩んだのだ。
公衆電話で甥っ子のポールに荷造りを頼んで、パリ行きの切符の手配をし、キャシーへのお土産に駅の中の店でドレスを買う。ジョバンニへ電報を送ろうとしたが結局出せなかった。何を書いても彼を納得させることなど出来ないと思えたからだ。
列車に乗り込んだものの大勢の客でごった返し五月蠅くて息苦しい。席を離れて通路の車窓からプラットホームを見ていると、そこには慌てた様子のジョバンニの姿があった・・・。
不倫モノは嫌いというお馴染みさんにはプラトニックと言っていい「逢びき」も敬遠されましたので、こちらは最悪でしょうな。明らかに男女の切実な想いが伝わってきますし、子供も巻き込みそうな設定ですからね。
しかしそこはそれ、狂おしい想いに寄り添って観れば別れの辛さも、家族への申し訳ない気持ちも伝わってきますし、映画の醍醐味も堪能できるってもんじゃないでしょうか。恋に盲目になるのは若者だけの特権では無いと思うんですが。

<ハリウッドの映画プロデューサー、デヴィッド・O・セルズニックが映画「逢びき」に匹敵するメロドラマを作ろうと、イタリア「ネオレアリズモ」の巨匠ヴィットリオ・デ・シーカ監督を招いて作りあげた恋愛映画の名作>とウィキには書いてありました。
確かに人妻の不倫と別れ、舞台として駅が出てくるところなどD・リーン監督の「逢びき」を彷彿とさせますが、「終着駅」では出逢いは描かれずに別れだけ、そして2時間足らずの物語の殆どが駅構内で展開されるというコンパクトに纏められた緊迫した映画となっていました。
主な登場人物は三人。
メアリー・フォーブスにはセルズニックの妻ジェニファー・ジョーンズ。当時34歳くらい。「慕情」の2年前ですね。お色気あり過ぎです。
ジョバンニ・ドリアにはモンゴメリー・クリフト。33歳。同じ年にジンネマンの「地上(ここ)より永遠に」とヒッチコックの「私は告白する」にも出ているので、まさに旬の俳優だったんでしょう。
劇中でジョバンニは母親がアメリカ人だと言っていました。スペイン広場でメアリーがイタリア語で話しかけたのが最初の出逢いだったらしいのですが、同じ年に作られた「ローマの休日」でもスペイン広場が印象的な場面に使われていたのを思い出しますね。
メアリーの甥ポールにはクレジットではディック・ベイマー。後の「ウエスト・サイド物語(1961)」のトニー役、リチャード・ベイマーの少年時代であります。
物語は二人の別れのドラマなので単調になりそうですが、巧妙なプロットで男女の想いのすれ違いを描いていて、イタリアの主要駅であるローマ・テルミニ駅の紹介を兼ねたような構内の描写、色々な職業の人々や様々な人生模様も点描されていて見応えがあります。
全編に漂う緊張感にはBGMも大いに貢献しておりましたな。
お勧め度は★四つ。
万人にお勧めするには、ヒロインの性格設定に少し難があるかなと。
優柔不断なのは惚れた弱さと割り切れても、お土産のドレスを買う時に自分の娘の身長も分からない母親ってちょっとおかしいでしょう。しかもひと月もほったらかしてるし。観る回数を重ねる度に気になりました。
トルーマン・カポーティが脚本に参加しているのは有名な話ですが、クレジットではダイアローグ担当と明確に書かれていました。
そして、ジェニファーさんの洋服はクリスチャン・ディオールのデザインであると、これもクレジットされていました。
 アメリカ、フィラデルフィアの主婦メアリーは姉家族の住むローマを訪れ、そこで現地の青年ジョバンニと恋に落ちる。メアリーにはキャシーという7歳の娘がいたが、ジョバンニはキャシーと三人で彼の実家のある田舎町ピサで暮らそうと言う。一旦はその気になったメアリーだが、日が変わると怖くなり、ジョバンニと別れて家族の元に帰ることにした。
アメリカ、フィラデルフィアの主婦メアリーは姉家族の住むローマを訪れ、そこで現地の青年ジョバンニと恋に落ちる。メアリーにはキャシーという7歳の娘がいたが、ジョバンニはキャシーと三人で彼の実家のある田舎町ピサで暮らそうと言う。一旦はその気になったメアリーだが、日が変わると怖くなり、ジョバンニと別れて家族の元に帰ることにした。せめて別れの言葉を残そうとジョバンニのアパートのドアの前まで来るが、ノックが出来ずにそのまま踵を返して駅に向うメアリー。荷物もまとめずに、姉にさよならを言う余裕もないほど悩んだのだ。
公衆電話で甥っ子のポールに荷造りを頼んで、パリ行きの切符の手配をし、キャシーへのお土産に駅の中の店でドレスを買う。ジョバンニへ電報を送ろうとしたが結局出せなかった。何を書いても彼を納得させることなど出来ないと思えたからだ。
列車に乗り込んだものの大勢の客でごった返し五月蠅くて息苦しい。席を離れて通路の車窓からプラットホームを見ていると、そこには慌てた様子のジョバンニの姿があった・・・。
*
不倫モノは嫌いというお馴染みさんにはプラトニックと言っていい「逢びき」も敬遠されましたので、こちらは最悪でしょうな。明らかに男女の切実な想いが伝わってきますし、子供も巻き込みそうな設定ですからね。
しかしそこはそれ、狂おしい想いに寄り添って観れば別れの辛さも、家族への申し訳ない気持ちも伝わってきますし、映画の醍醐味も堪能できるってもんじゃないでしょうか。恋に盲目になるのは若者だけの特権では無いと思うんですが。

<ハリウッドの映画プロデューサー、デヴィッド・O・セルズニックが映画「逢びき」に匹敵するメロドラマを作ろうと、イタリア「ネオレアリズモ」の巨匠ヴィットリオ・デ・シーカ監督を招いて作りあげた恋愛映画の名作>とウィキには書いてありました。
確かに人妻の不倫と別れ、舞台として駅が出てくるところなどD・リーン監督の「逢びき」を彷彿とさせますが、「終着駅」では出逢いは描かれずに別れだけ、そして2時間足らずの物語の殆どが駅構内で展開されるというコンパクトに纏められた緊迫した映画となっていました。
主な登場人物は三人。
メアリー・フォーブスにはセルズニックの妻ジェニファー・ジョーンズ。当時34歳くらい。「慕情」の2年前ですね。お色気あり過ぎです。
ジョバンニ・ドリアにはモンゴメリー・クリフト。33歳。同じ年にジンネマンの「地上(ここ)より永遠に」とヒッチコックの「私は告白する」にも出ているので、まさに旬の俳優だったんでしょう。
劇中でジョバンニは母親がアメリカ人だと言っていました。スペイン広場でメアリーがイタリア語で話しかけたのが最初の出逢いだったらしいのですが、同じ年に作られた「ローマの休日」でもスペイン広場が印象的な場面に使われていたのを思い出しますね。
メアリーの甥ポールにはクレジットではディック・ベイマー。後の「ウエスト・サイド物語(1961)」のトニー役、リチャード・ベイマーの少年時代であります。
物語は二人の別れのドラマなので単調になりそうですが、巧妙なプロットで男女の想いのすれ違いを描いていて、イタリアの主要駅であるローマ・テルミニ駅の紹介を兼ねたような構内の描写、色々な職業の人々や様々な人生模様も点描されていて見応えがあります。
全編に漂う緊張感にはBGMも大いに貢献しておりましたな。
お勧め度は★四つ。
万人にお勧めするには、ヒロインの性格設定に少し難があるかなと。
優柔不断なのは惚れた弱さと割り切れても、お土産のドレスを買う時に自分の娘の身長も分からない母親ってちょっとおかしいでしょう。しかもひと月もほったらかしてるし。観る回数を重ねる度に気になりました。
トルーマン・カポーティが脚本に参加しているのは有名な話ですが、クレジットではダイアローグ担当と明確に書かれていました。
そして、ジェニファーさんの洋服はクリスチャン・ディオールのデザインであると、これもクレジットされていました。
・お薦め度【★★★★=友達にも薦めて】 



























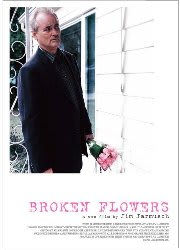







テーマ曲の"ローマの秋"のやるせない旋律が流れ、秋深いローマ駅の黄昏の風景の中で、激しい恋の最後の炎が燃える。
かなり通俗的な設定ですが、ヴィットリオ・デ・シーカ監督の演出は、ドキュメンタリーのように、リアルに時間を追い、オール・ロケの効果と共に、緊迫した映画空間を創り出していると思う。
段々と暮れてくる駅の様子と、恋の終わりを上手く溶け合わせたところ等、憎い演出で、秋の冷気と別離の淋しさを感じさせるラストが、実に秀逸。
それにしても、この「終着駅」という映画は、モンゴメリー・クリフトという俳優のナルシスティックな一面が全開した映画として、実に印象深いものがある。
ローマに旅行中のアメリカの夫人ジェニファー・ジョーンズに恋をしてしまい、帰国しようとする夫人をローマ駅まで追って来る、イタリア青年を演じているが、恋というよりは、年上の女にすがろうとする、孤独な青年のドラマという感じで、フランソワーズ・サガンの「ブラームスはお好き」を思わせるものがある。
発車する列車から飛び降り、ホームに転んでしまうクリフトの姿は、まさに淋しい少年そのものだ。
この甘さ、このやるせなさは、演技で出せるものではないと思う。
ジェームス・ディーンがそうであったように、この男の少年性は、クリフト本人が持っているものに他ならない。
最後の会話を交わすシーンで、クリフトの見せる表情と、列車が発車してしまってからの表情のデリケートな違いに、私はいつもこの映画の、いやクリフトの謎を見るのです。
すがりつこうとする弱さと、それを振り切ってしまう強さ。
クリフトは、この二つの表情の間で、実にセクシーに揺れているのだった。