
咲子さんは「いやさか句会についていけるか不安ですが一度伺います」という。彼女の句は何度かみていて、素質があるし句はかなりの水準にあると何度も言っているのに、彼女は口癖のように「ついていけるか不安です」という。
謙虚で控えめなのだがそれに終始するのがずっと気になっている。これは彼女の生きる方便であり武器ではないかと思ってしまう。
日本では尊大より謙遜のほうがずっと生きやすい。人は自分をよく見てくれるだろう。人によく見てもらうと生きやすいし自分も気持ちいい。だから謙遜が身についているような気がする。しかも磯の岩にくっつく藤壺のようにくっついている感じである、
咲子さんは十分ついていっている。ついていくどころか人がついていきたいと思うような句を出している。なのに「ついていけるか不安です」を連発すると人の顰蹙を買うのではないか。鼻持ちならない人ね、ということになる恐れがある。
彼女の場合、本音と装いとの間に境がなくなってしまっていてまさに岩と藤壺の関係になっているようだ。
謙遜というのは尊大の裏返しではないかと彼女を見て思う。
人は誰しも謙遜と尊大、偽善と偽悪との間でわが身を処している。文章など書いているとそれを痛切に感じる。自分をよく見せたいという心理と闘う。そうまでしてきみはなぜ表現するのかと別の自分が中空で問いかける。俳句を書くのも同様である。自分を誇りたい心理とそれを引きとどめる心理が闘う。
謙遜と尊大、偽善と偽悪の間で、では中庸を選べばいかといえば中庸とかふつうといったこともないように思えてくるから厄介である。
とにかく人に生まれたことが厄介なのである。自分を律することが至難なのである。
だから咲子さんのように謙遜に徹するのも生き方なのだがあきらかに行き過ぎている。それを抑えてもっとマイルドに自分をよく見せるか、謙遜を徹底して突き進んで人から嫌われるか、咲子さんはむつかしい生き方をしている。
俳句に関してもよけいなことを考えるので、「書きたいことを十全に言葉にできたか」それだけ考えるようにいった。すると「書きたいという感動が乏しくなってきました」という。
「俳句は感動がなくて書くのです。感動は書くことで湧いてくるのです」
作品と感動の間にも謙虚と尊大のような問題が横たわっている。なかなか解決できないが、それに気づくだけでも視界は変ってくるだろう。
写真:今年はじめて食べた秋刀魚。鷹の台駅前のレストラン










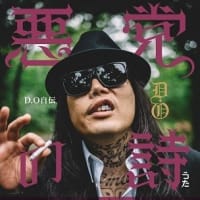



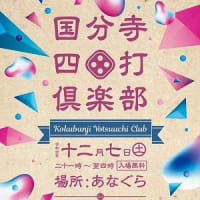
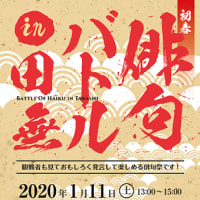


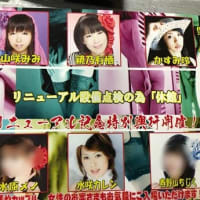

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます