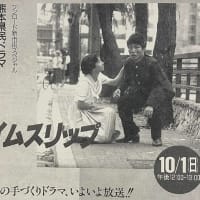今日はIT業界の大先輩やお仲間と長時間にわたって話し合う機会があった。ネット上の会話だったが。ネットの向こうにいる人たちはちょうど私がテレビ局を退職して、新たなスタートを切った頃にすでにネットの世界の最先端を歩いていた人たちだ。今現在の地域情報化の課題を詰めていったら、結局私に関しては,なぜ住民ディレクターを始めることになったかの原点が改めて浮き彫りににされた。
今から20数年前、村おこしの第1次ブームがあった。ちょうどその頃、私は誰も行きたがらない田舎回りをする番組のディレクターとして熊本県内98市町村を5年かけて2周半していた。その頃に気付いたのが村おこしを先導しているのは村の人ではなく東京から来たコンサルの人たちだということだった。村の人たちは、コンサルの指導を受け、「おたくの村はこうするといい。」「こんなことができるはずだ。」「小さな村だからこんなことをすればすぐに日本一になれる」などと教えられ、せっせと補助金で始まった事業をこなしていた。東京から来たコンサルの方々は悪気はなく、本当に村のために「そうすること」が発展につながると考えていたと思う。
しかし、私が2周半していく中で気が付いたのは、コンサルが帰った後、ではこの企画を「誰がするか?」「誰ができるのか?」ということだった。結局、補助金行政で様々な人が次々と手を変え品を変え、村にやってきては分厚い企画書、事業系計画書を作っていく。しかし、いつも誰がそれを実践するのか?が抜けている事業計画だった。だから、その企画書は村のロッカーの奥深くに置かれたり、ロッカーの上に積み上げられていくしかなかった。
その頃、私は田舎をひたすら歩いた。どこに行っても状況は同じだった。阿蘇郡の小国町のようなところはむしろ、そういう補助金行政を上手に活用していた地域の代表選手だったが、今、どうなっているだろう?私は自分が企画した地域づくり応援番組で小国町にも入り込んだが、あまりにも見事に補助金を活用する器用さに、山江村にはない「街の空気」を感じていた。実際、小国町には外から芸術家や文化人が多くやってきていた。町長も受け入れていた。由布院や、小布施町のようなセンスがあった。しかし、山江村にはみごとにそんな感覚はなく、素朴、大雑把、何かというと「焼酎飲まんば(飲まないと)始まらん」などの人間のスケールの大きさだけが目だった。
しかし。地域回りをしてもっとも気になったのは、地域のことを地域に住む人々が自分たちで判断、決断し、はじめたことを自分たちで責任を取るという姿勢が希薄なことだった。いつもコンサルや県の人がやってきては「ああしろ、こうしろ」といわれ、いわれるままにやることで責任を逃れ・・・、という田舎独特の生き方があった。私は、たかがテレビ局がといわれたが、この頃に共に責任を持って村がつぶれるまでやっていこうと考えていた。地域のことを知らぬ人や、そういう心がまえで地域に入ったことがない人は、よく結局岸本さんも「どこかへ行ってしまう存在でしかない」と批判されるが、少なくとも小国町をはじめ、今まで関わった地域はどこのひとつもいまだに気になっているし、いつか恩返し、お礼をしたいと考えている。そのためにもその地域だけでやることではなく、もっと大きな視点でお役に立てることを確実にやっていこうと思う。
そのひとつがプリズムTVの実験であったが、これは私の実験で、よりダイナミズムのある形で動けるようにならないとお役に立てないと思っている。私の基本は多くを求めなくとも「いつも必ず一人はいる。」という事実だ。その地域のことが気になり、離れていてもいつか必ず一緒にやろうよね、という仲間が確実に一人づつはいることだ。結局は人と人の個人的な付き合いがあるかどうかしかない。そろそろそのような全国のお仲間と「花を咲かせる」状況が来ていると感じる。今日のIT業界の話し合いでも発見が多かった。住民ディレクター活動は地域の主体性を確保していくための人材養成の場、松下村塾のようなものをイメージしている。少々大げさな話になってしまったが地域の主体性を保ち、住民自治を実現するためには相当なエネルギーと現代だからこそ可能なその人たちのネットワーク化が必要だと考える。
(写真は熊本県山江村)
今から20数年前、村おこしの第1次ブームがあった。ちょうどその頃、私は誰も行きたがらない田舎回りをする番組のディレクターとして熊本県内98市町村を5年かけて2周半していた。その頃に気付いたのが村おこしを先導しているのは村の人ではなく東京から来たコンサルの人たちだということだった。村の人たちは、コンサルの指導を受け、「おたくの村はこうするといい。」「こんなことができるはずだ。」「小さな村だからこんなことをすればすぐに日本一になれる」などと教えられ、せっせと補助金で始まった事業をこなしていた。東京から来たコンサルの方々は悪気はなく、本当に村のために「そうすること」が発展につながると考えていたと思う。
しかし、私が2周半していく中で気が付いたのは、コンサルが帰った後、ではこの企画を「誰がするか?」「誰ができるのか?」ということだった。結局、補助金行政で様々な人が次々と手を変え品を変え、村にやってきては分厚い企画書、事業系計画書を作っていく。しかし、いつも誰がそれを実践するのか?が抜けている事業計画だった。だから、その企画書は村のロッカーの奥深くに置かれたり、ロッカーの上に積み上げられていくしかなかった。
その頃、私は田舎をひたすら歩いた。どこに行っても状況は同じだった。阿蘇郡の小国町のようなところはむしろ、そういう補助金行政を上手に活用していた地域の代表選手だったが、今、どうなっているだろう?私は自分が企画した地域づくり応援番組で小国町にも入り込んだが、あまりにも見事に補助金を活用する器用さに、山江村にはない「街の空気」を感じていた。実際、小国町には外から芸術家や文化人が多くやってきていた。町長も受け入れていた。由布院や、小布施町のようなセンスがあった。しかし、山江村にはみごとにそんな感覚はなく、素朴、大雑把、何かというと「焼酎飲まんば(飲まないと)始まらん」などの人間のスケールの大きさだけが目だった。
しかし。地域回りをしてもっとも気になったのは、地域のことを地域に住む人々が自分たちで判断、決断し、はじめたことを自分たちで責任を取るという姿勢が希薄なことだった。いつもコンサルや県の人がやってきては「ああしろ、こうしろ」といわれ、いわれるままにやることで責任を逃れ・・・、という田舎独特の生き方があった。私は、たかがテレビ局がといわれたが、この頃に共に責任を持って村がつぶれるまでやっていこうと考えていた。地域のことを知らぬ人や、そういう心がまえで地域に入ったことがない人は、よく結局岸本さんも「どこかへ行ってしまう存在でしかない」と批判されるが、少なくとも小国町をはじめ、今まで関わった地域はどこのひとつもいまだに気になっているし、いつか恩返し、お礼をしたいと考えている。そのためにもその地域だけでやることではなく、もっと大きな視点でお役に立てることを確実にやっていこうと思う。
そのひとつがプリズムTVの実験であったが、これは私の実験で、よりダイナミズムのある形で動けるようにならないとお役に立てないと思っている。私の基本は多くを求めなくとも「いつも必ず一人はいる。」という事実だ。その地域のことが気になり、離れていてもいつか必ず一緒にやろうよね、という仲間が確実に一人づつはいることだ。結局は人と人の個人的な付き合いがあるかどうかしかない。そろそろそのような全国のお仲間と「花を咲かせる」状況が来ていると感じる。今日のIT業界の話し合いでも発見が多かった。住民ディレクター活動は地域の主体性を確保していくための人材養成の場、松下村塾のようなものをイメージしている。少々大げさな話になってしまったが地域の主体性を保ち、住民自治を実現するためには相当なエネルギーと現代だからこそ可能なその人たちのネットワーク化が必要だと考える。
(写真は熊本県山江村)