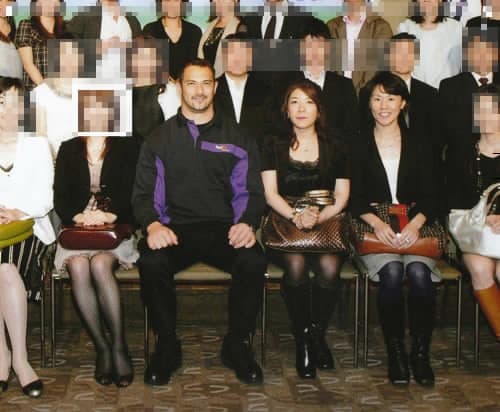ミネソタにいた時、アメリカのお父さんのLarryはよく夜になると私の部屋をノックして
「お茶を飲まないかい?」と少し大げさな程ゆっくりと大きな声で、でも優しく声を掛けてくれた。
キッチンに降りていくとLarryは穏やかに、ゆっくりと湯を沸かし
自分で焼いた茶碗に緑茶のティーバックを入れて私に差し出しながら
その時々で色んな話題を私に投げかけ意見を求めてくる。
ある時「S子、"Materialistic"(物質主義的)であることをどう思うか?」と聞いてきた。
17歳の私には少々難しい質問だったが思春期で色んなことを考えていた自分にとっては面白い質問でもあった。
Larryはアメリカ人はToo materialistic(物欲が大きすぎる)と少々批判的な部分も含め意見を出していたと思う。
そしてMaterialistic過ぎると人はどうなると思うか?ということも聞かれたと思う。
その時自分がどう答えたかは忘れてしまったが自分が週末家を片付けているとふと、そんな事を話し合った事を
思い出した。
Larryはアメリカ人ながら焼き物をとても愛し日本の和の心がわかるアメリカ人だった。
私は時々物が増えてくると自分が身動きできなくなるような感覚に襲われ
大胆に物を捨ててしまう。
ものが沢山あるのは便利だが自分の基本的な考え方や発想、研ぎ澄まされたもの、そして何より
本質的なものが見えなくなるような気がするのだ。
本質的なもの、、、それは何だろう。
私はLarryとVickiに会わなければ自分にとって本当に大切なものはわからなかったかもしれない。
私はたったの1年にも満たない時間の中でこれまでに見た事のない人の愛情の大きさを見せられた。
Larryは私が帰国するまでの間ずっとそうやって私の部屋をノックし続け私をキッチンへ連れ出した。
そしてずっと緑茶を入れ続けてくれ、私に語りかけた。
私の好きな70’Sの音楽がラジオから流れてくると一緒に聞いた。
私が泣いていると背中をさすりずーっとそばにいて涙の理由を聞いてくれた。
そうやって毎日、毎日、本当に毎日、私の答えが無くても私に語りかけ、私を外へ連れ出してくれた。
今の時代はどんな情報でも簡単に手に入れられる。
でも、自分自身の本質に耳を傾ける時間はあるだろうか?
そんな時ふと、今目の前にある当たり前の生活が蜃気楼のように思えてくる。
自分が死ぬ時、「いい家に住めたな」とか「いい車乗れたな」とか思い出すだろうか?
いや、少なくとも自分はそんなこと思い出さないだろうな。
自分が大切に思ってきた人達を思い出すだけできっとタイムオーバーになるだろうな。
「お茶を飲まないかい?」と少し大げさな程ゆっくりと大きな声で、でも優しく声を掛けてくれた。
キッチンに降りていくとLarryは穏やかに、ゆっくりと湯を沸かし
自分で焼いた茶碗に緑茶のティーバックを入れて私に差し出しながら
その時々で色んな話題を私に投げかけ意見を求めてくる。
ある時「S子、"Materialistic"(物質主義的)であることをどう思うか?」と聞いてきた。
17歳の私には少々難しい質問だったが思春期で色んなことを考えていた自分にとっては面白い質問でもあった。
Larryはアメリカ人はToo materialistic(物欲が大きすぎる)と少々批判的な部分も含め意見を出していたと思う。
そしてMaterialistic過ぎると人はどうなると思うか?ということも聞かれたと思う。
その時自分がどう答えたかは忘れてしまったが自分が週末家を片付けているとふと、そんな事を話し合った事を
思い出した。
Larryはアメリカ人ながら焼き物をとても愛し日本の和の心がわかるアメリカ人だった。
私は時々物が増えてくると自分が身動きできなくなるような感覚に襲われ
大胆に物を捨ててしまう。
ものが沢山あるのは便利だが自分の基本的な考え方や発想、研ぎ澄まされたもの、そして何より
本質的なものが見えなくなるような気がするのだ。
本質的なもの、、、それは何だろう。
私はLarryとVickiに会わなければ自分にとって本当に大切なものはわからなかったかもしれない。
私はたったの1年にも満たない時間の中でこれまでに見た事のない人の愛情の大きさを見せられた。
Larryは私が帰国するまでの間ずっとそうやって私の部屋をノックし続け私をキッチンへ連れ出した。
そしてずっと緑茶を入れ続けてくれ、私に語りかけた。
私の好きな70’Sの音楽がラジオから流れてくると一緒に聞いた。
私が泣いていると背中をさすりずーっとそばにいて涙の理由を聞いてくれた。
そうやって毎日、毎日、本当に毎日、私の答えが無くても私に語りかけ、私を外へ連れ出してくれた。
今の時代はどんな情報でも簡単に手に入れられる。
でも、自分自身の本質に耳を傾ける時間はあるだろうか?
そんな時ふと、今目の前にある当たり前の生活が蜃気楼のように思えてくる。
自分が死ぬ時、「いい家に住めたな」とか「いい車乗れたな」とか思い出すだろうか?
いや、少なくとも自分はそんなこと思い出さないだろうな。
自分が大切に思ってきた人達を思い出すだけできっとタイムオーバーになるだろうな。