
(つづき)
福岡県筑紫野市の「西鉄二日市」バス停。
「22番」の路線図には、かつて存在した「杉塚経由」の「遺産」が残っている(塔の原と大佐野の間の空白のバス停が旧「杉塚」)。
「杉塚経由」は、「天拝坂経由」ができる前の「22番」のオリジナル経路だが、「杉塚経由」が走っていた道路のうちの一部は、現在は道路自体がなくなってしまっている。
ここは西鉄二日市駅の「西口」にあるバスターミナルだが、路線図や時刻表の「昔ながら」の感じにとても癒される。
駅には2003年に「東口」もでき、線路の東側に向かう路線(梅香苑~星ケ丘~五条方面)は新しい「東口」からの発着に変更されたが、「東口」のほうはごく普通のバス停である。
現在の「西口」は、線路の西側に向かう路線がメインであり、駅のそばの踏切を渡って反対側に向かう路線は、現在では「1-3番」が土曜の夜に一本だけとなってしまっている(ただし「1-1番」「1-2番」も、まずは線路の西側に向かうものの、最終的には線路の東側に行くのだが)。
ちなみに、ここよりも停車するバスの本数が多い「JR二日市」のバス停は、たった1つののりばで乗客を捌いているが、ここ「西鉄二日市」には6つもののりばがある。
「西鉄二日市」と「JR二日市」の間、「西鉄二日市」と「塔の原」の間、「西鉄二日市」と「筑紫野市役所前」の間、「西鉄二日市東口」と「福岡経済大学前」の間など、二日市の市街地は、バス停の間隔が結構開いている。
市街地にバス停が少ないと、「駅」が通勤、通学のための単なる通過点にしかならず、駅利用者が中心市街地で回遊しないことから、地元経済にもマイナスなのでは?などと考えたりもする。
車線変更の必要性や渋滞懸念や踏切の存在など、実際は、バス停の設置にあたりいろんな問題がありそうなのはなんとなくわかるのだけど。
なお、下の写真は、二日市の市街地を循環する「3番」ののりばであり、今月1日のダイヤ改正で、これまで一方向のみの循環だったところにまさかの逆回りが新設されたことから、路線図も新しく(というか、東町を消して逆回りの線を書き足したものと思われる)なっていた。
「1-1番」の吉木行きが写っているが、ローマ字の「YOSHIKI」が「X JAPAN」のようである。
(つづく)
福岡県筑紫野市の「西鉄二日市」バス停。
「22番」の路線図には、かつて存在した「杉塚経由」の「遺産」が残っている(塔の原と大佐野の間の空白のバス停が旧「杉塚」)。
「杉塚経由」は、「天拝坂経由」ができる前の「22番」のオリジナル経路だが、「杉塚経由」が走っていた道路のうちの一部は、現在は道路自体がなくなってしまっている。
ここは西鉄二日市駅の「西口」にあるバスターミナルだが、路線図や時刻表の「昔ながら」の感じにとても癒される。
駅には2003年に「東口」もでき、線路の東側に向かう路線(梅香苑~星ケ丘~五条方面)は新しい「東口」からの発着に変更されたが、「東口」のほうはごく普通のバス停である。
現在の「西口」は、線路の西側に向かう路線がメインであり、駅のそばの踏切を渡って反対側に向かう路線は、現在では「1-3番」が土曜の夜に一本だけとなってしまっている(ただし「1-1番」「1-2番」も、まずは線路の西側に向かうものの、最終的には線路の東側に行くのだが)。
ちなみに、ここよりも停車するバスの本数が多い「JR二日市」のバス停は、たった1つののりばで乗客を捌いているが、ここ「西鉄二日市」には6つもののりばがある。
「西鉄二日市」と「JR二日市」の間、「西鉄二日市」と「塔の原」の間、「西鉄二日市」と「筑紫野市役所前」の間、「西鉄二日市東口」と「福岡経済大学前」の間など、二日市の市街地は、バス停の間隔が結構開いている。
市街地にバス停が少ないと、「駅」が通勤、通学のための単なる通過点にしかならず、駅利用者が中心市街地で回遊しないことから、地元経済にもマイナスなのでは?などと考えたりもする。
車線変更の必要性や渋滞懸念や踏切の存在など、実際は、バス停の設置にあたりいろんな問題がありそうなのはなんとなくわかるのだけど。
なお、下の写真は、二日市の市街地を循環する「3番」ののりばであり、今月1日のダイヤ改正で、これまで一方向のみの循環だったところにまさかの逆回りが新設されたことから、路線図も新しく(というか、東町を消して逆回りの線を書き足したものと思われる)なっていた。
「1-1番」の吉木行きが写っているが、ローマ字の「YOSHIKI」が「X JAPAN」のようである。
(つづく)














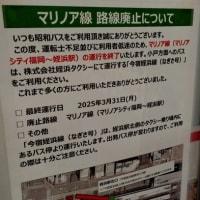





「西鉄二日市」の方が発着するバスが多かった理由は、
①甘木幹線のバスが今のように二日市発着でなく、博多駅(さらに前は天神)が発着であり、「JR二日市」バス停には立ち寄らず、旧3号線上の「二日市」バス停だけに停まっていたこと(西鉄にも入りません)。
②二日市エリア発着の路線のうち、湯町線、山口線、吉木線は「西鉄」始発「JR」経由なのに、宇美行きだけは「西鉄」始発で「JR」を経由せずに関屋へ向かっていたこと(後発の星が丘線も「JR」経由せず)。
です。
大昔、二日市の中央通(地図上のクランク状の道)が今のように一方通行のプロムナード状でなくて対面交通の商店街だった頃、「西鉄」から「国鉄」方面へ向かうバスが両方向走っていて中間に「中央通り」バス停がありました。たいへんな賑わいの中、バスは窮屈そうに走っていましたが、今のコミュニティバスのような(もっと小さかったかも)バスで(勿論西鉄バスです)、「ライトバス」とか「ライトバン」と呼ばれていました。
この路線が国鉄のさらに向こう側の湯町まで走っていた可能性がありますが、定かではありません。
「塔の原」~「大佐野」の空欄には、確かに「杉塚」があったのはまちがいないのですが(カッターのようなもので2字削った痕がある)、実は「杉塚公民館前」がこの路線図から抜け落ちているんですね。「杉塚公民館入口」~「天拝坂第三」が開通したときに抜け落ちてしまいました。これが「天拝坂第一」~「天拝坂第三」を復乗していた時は確かあったんですけどねぇ。
ここを始点とする「駅まで・駅から100円」もなくなりましたが、JR駅から西鉄駅へ160円で来ても、直後に西鉄駅から自宅最寄りまでバスに乗るので、乗り継ぎ割引で結局は以前と同額になっちゃいます。というわけで、ワタクシとしては全然影響を受けておりませぬ(笑)。
>昔、「JR二日市」が「国鉄二日市」だった頃、発着するバスの数は、「西鉄二日市」のほうが多かったと記憶します。
JR二日市の場合、郊外向けに加えて反対行きの「西鉄二日市行き」も同じバス停に停まるので、そこで本数に圧倒的な差が出るのですが、それを差し引いても、JRの「40番」「41番」と西鉄の「23番」の差し引きで、現状はJRのほうが多そうです。
40番が天神から出ていた頃、朝倉にある曾祖父母の家に40番で連れて行ってもらったこともありましたが、旧3号の「動脈」としての役割は終わってしまった感がありますね。
その後バイパス経由の急行ができ、それも衰退してしまった時期がありましたが、関屋高架橋の開通と都市高速の延長で、福岡都心部から甘木までの路線バスが再び息を吹き返したことは注目に値すると言えるかもしれません。
>大昔、二日市の中央通(地図上のクランク状の道)が今のように一方通行のプロムナード状でなくて対面交通の商店街だった頃、「西鉄」から「国鉄」方面へ向かうバスが両方向走っていて中間に「中央通り」バス停がありました。たいへんな賑わいの中、バスは窮屈そうに走っていましたが、今のコミュニティバスのような(もっと小さかったかも)バスで(勿論西鉄バスです)、「ライトバス」とか「ライトバン」と呼ばれていました。
>この路線が国鉄のさらに向こう側の湯町まで走っていた可能性がありますが、定かではありません。
その「ライトバス」というものが二日市温泉地区まで走っていて、それが現在の「3番」につながるというのはあり得そうな話ですね。
「ライトバス」の復活は無理にしても、もう少しバス停を増やして、小回りをきかせてほしいと考えるのですが、自動車交通全体からみると、なかなか実現は難しいのかもしれません。
Kassyさん、こんにちは。
>「塔の原」~「大佐野」の空欄には、確かに「杉塚」があったのはまちがいないのですが(カッターのようなもので2字削った痕がある)、実は「杉塚公民館前」がこの路線図から抜け落ちているんですね。「杉塚公民館入口」~「天拝坂第三」が開通したときに抜け落ちてしまいました。これが「天拝坂第一」~「天拝坂第三」を復乗していた時は確かあったんですけどねぇ。
なるほど。
そう考えると、西鉄二日市の路線図のペースは、(他ののりばも含めて)かなり歴史がありますよねぇ。
「デザインを新しくする」という発想がなければ、新たに一から作り替える必要性もあまりないのかもしれませんが。