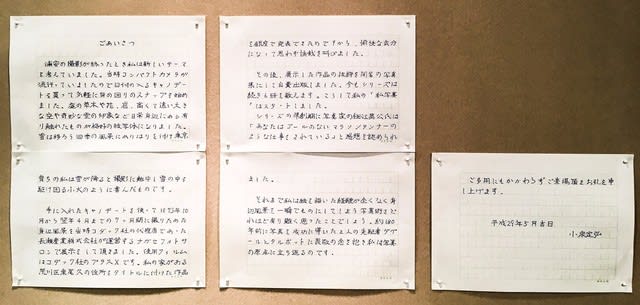ジョージ大塚『Sea Breeze』(テイチク、1971年)を聴く。

George Otsuka ジョージ大塚 (ds)
Takao Uematsu 植松孝夫 (ts, ss)
Shunzo Ohno 大野俊三 (tp)
Hideo Ichikawa 市川秀男 (elp)
Takashi "Gon" Mizuhashi 水橋孝 (b)
「和ジャズ」とかレッテルは安易に貼りたくないが、これは確かに「和ジャズ」で、異様にカッコ良い。
「どばしゃばだ」とジョージ大塚がプチ嵐を起こし、市川秀男のエレピ。勢いもある。やはり嬉しいことは、それぞれに確立した「声」をためらいなく放っていることである。植松孝夫の繰り返しのリフやマニッシュでポップス的でもある音も、まさに。大野俊三のラッパを聴くと実にすかっとする。
水橋孝のベースを聴くと、確かにマリオン・ブラウンの日本ライヴにおける音はその個性だったとわかる。1999年に赤坂でアーチ―・シェップを観たとき、水橋さんが飛び入りでベースを弾き、シェップに「Happy reunionだ」と紹介されていた。そのときも、ああ独特だなと感じ入って聴いていたのだった。70代のいまも現役のようだし(1943年生まれ)、また観に行こうかな。
●ジョージ大塚
植松孝夫『Debut』(1970年)
●市川秀男
菊地雅章『POO-SUN』(1970年)
●大野俊三
ギル・エヴァンスの映像『Hamburg October 26, 1986』(1986年)
大野俊三『Something's Coming』(1975年)
●植松孝夫
植松孝夫+永武幹子@北千住Birdland(JazzTokyo)(2017年)
本田竹広『EASE / Earthian All Star Ensemble』(1992年)
『山崎幹夫撮影による浅川マキ文芸座ル・ピリエ大晦日ライヴ映像セレクション』(1987-92年)
浅川マキ『アメリカの夜』(1986年)
植松孝夫『Debut』(1970年)