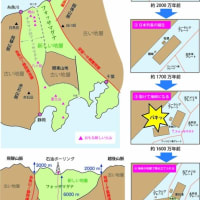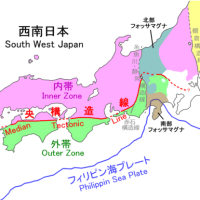中華人民共和国の「東北部」は日本では括弧書きで(満州)と表示され、「坂の上の雲」などの影響もあって、日露戦争で日本陸軍がロシア陸軍と戦った戦場との認識が強いかもしれません。

中国東北部
左内モンゴル、右東三省
南満洲鉄道株式会社(満鉄)は1905年(明治38年)9月、日露戦争終結後のポーツマス条約によって、ロシア帝国から大日本帝国に譲渡された東清鉄道南満州支線(長春―旅順間)764kmおよび支線を含む鉄道事業を行うため、1906年11月に設立された半官半民の国策会社です。
満鉄は本来の鉄道のほか各駅に設定された大規模な鉄道附属地での都市経営と一般行政(土木・教育・衛生)を担い、徴税権を行使するなど政府に当たる権限をもち、満洲の農産物を一手に支配し、炭鉱開発、製鉄業、港湾、電力供給、牧畜、ホテル、航空会社など多様な事業を行ないました。
1931年(昭和6年)9月に満洲事変が勃発し1932年3月に満洲国が建国されると満州国内の鉄道全線の運営を委託され、1935年には日満間で鉄道売却の協定が成立し、満鉄は満洲国の所有になりました。
最盛期には日本の国家予算の半分規模の資本金と80余りの関連企業をもち、鉄道総延長1万㎞、社員数40万人を擁しました。1945年日本の敗戦により満鉄が保有していた鉄道は中国・ソ連の共同経営となり、中華人民共和国成立後の1952年に中国に返還されました。

1945年東北部鉄道網
満鉄は日露戦争の最中に陸軍の児玉源太郎が「戦後満洲経営唯一ノ要訣ハ、陽ニ鉄道経営ノ仮面ヲ装イ、陰ニ百般ノ施設ヲ実行スルニアリ」と献策していたように、日本の満州における植民地経営を具体化するための組織でした。
日露戦争終結直後、伊藤博文、井上馨らの元老や第1次桂内閣の桂太郎首相は、戦争のために資金を使い果たした当時の我が国が、莫大な経費を要する満州鉄道を経営する自信が持てませんでした。
1905年8月に日露戦争中の外債募集に協力したアメリカの企業家エドワード・H・ハリマンが、世界を一周する鉄道網を完成する遠大な野望を持ち、南満洲鉄道さらには東清鉄道を買収する目的で来日しました。ハリマンは南満洲鉄道にアメリカ資本を導入すべきだと主張し、アメリカが満洲で発言権を持てばロシアが復讐戦を企てても制止できると説きました。
9月12日日本政府に対して1億円の資金提供と引きかえに、南満州鉄道と朝鮮鉄道の連結、満州の鉄道・炭坑などへの共同出資・経営参加を提案します。日本は鉄道を供出すれば資金支出の必要はなく、所有権は日米対等で、日露、日清間に戦争が起これば日本の軍事利用を認めると云う日米均等の権利のシンジケートの提案でした。
満州鉄道の運営が日本経済に悪影響を及ぼすのではないかと懸念する大蔵省、日銀の意見と、ロシアが復讐戦を挑んできた場合日本が単独で応戦するのは荷が重すぎると云う井上の危惧も、ハリマンの提案を好意的に受け止めた一因でした。桂は10月12日予備協定覚書を結び、本契約は外務大臣小村寿太郎がポーツマス会議より帰国した後のこととしました。
帰国した小村はハリマン提案に断固反対し、ポーツマス条約の規定では清国が承認しないと鉄道は日本のものにはならず鉄道の権利の半分を譲ることはできないと主張し、桂らも納得して10月23日の閣議で予備協定覚書の破棄が決定する一方で、ハリマンのライバルであるモルガン商会からより有利な条件で外資を導入することができました。

小村寿太郎外相
1905年10月30日日露両軍は撤兵手続きと鉄道線路引渡順序議定書に調印し、長春以南の南満洲支線が日本側に引き渡されます。四平街以南の線路はすでに1年半前に日本軍の占領下に入っていて、ロシアの広軌(5フィート)を日本国内採用の狭軌に改めて軍用に使用していました。四平街より北の鉄道はロシアの広軌のままで、いずれはすべての路線を国際標準軌(4フィート8.5インチ)に改める必要がありました。
小村は11月6日ポーツマス条約の決定事項を承認させるため清国に向かい17日から北京会議に臨みましたが、清国はポーツマスで清の頭越しになされたロシア利権の日本への譲渡を認める気はなく、交渉は難航し満洲善後条約が結ばれたのは12月22日のことです。
小村はこの条約に露清条約から引き継いだ鉄道利権の条項の遵守を盛り込むよう図り、租借期間はロシアの東清鉄道租借期間の36年間の内、既にロシアが租借済みの3年分を差し引いた33年としました。
清は長春やハルピンなど16市の開放を約束し、密約として南満洲鉄道の利益を妨げる併行線を敷設しないこと、ロシアから譲渡された鉄道沿線に日本が守備隊を置く権利を認めました。
1905年10月には奉天以南の区間で軍用以外の運輸営業も開始しており、1906年に入ると一般の人びとも利用できるようになっていましたが、1906年11月には孟家屯(長春南駅)までのロシアの広軌を狭軌に替えて、長春―大連間の直通列車の運行を開始しました。
日本国内では多くの人びとが満洲に強い関心を示し、旅館、食料品店、理髪店、飲食店、衣料品店、遊廓などの個人の企業も満洲に進出し、その人びとが大連、奉天といった大都市はもとより、大都市間の小さな町にも生活の基盤をつくろうとし、鉄道はこれらの人びとの活動をささえる重要な交通手段でした。
日本軍は撤兵期限ぎりぎりまで満洲に軍政を布き日本の勢力を植え付けようとしていましたが、1906年5月22日英米との関係悪化を憂慮した伊藤博文が元老、閣僚、軍部を集めて「満洲問題に関する協議会」を開催します。
陸軍参謀総長児玉源太郎は積極的満洲経営論を唱え、伊藤は関東州租借地の清国への返還と軍政の早期廃止方針を唱えました。山縣ら陸軍の誰も児玉を擁護せず伊藤の主張が通って軍政廃止が決定し、これにより英米の警戒心は解かれましたが、実際には軍政はすでに目的を達しており、英米商人の力は衰え満洲は日本の市場と化していきました。
児玉と台湾総督府で児玉の部下であった後藤新平が、領有開始10年で台湾財政独立を達成した実績が高く評価されていたため、満鉄は単なる鉄道会社ではなく一大植民会社たるべきだとする児玉、後藤の主張が次第に力を得ます。
1906年6月7日明治39年勅令第142号で「南満洲鉄道株式会社設立」が公布され、7月13日第1次西園寺内閣は児玉源太郎を設立委員長とする80名の満鉄設立委員を任命しましたが、この顔ぶれは国策会社としての性格の濃いものでした。

満鉄設立委員長児玉源太郎
7月23日に設立委員長の児玉が急逝し、25日陸軍大将寺内正毅が新委員長に就任します。8月1日「南満洲鉄道株式会社設立命令書」が下付され設立業務は寺内委員長のもとで進められました。
第1回株式募集は9月10日に開始され、募集株式10万株に対して1,077倍のブームを呈し、満鉄が植民地経営企業として一般から広く期待されていたことを物語っています。
1906年11月26日半官半民の南満洲鉄道株式会社が設立され、初代総裁には台湾総督府民政長官だった後藤新平が任命されました。総裁は勅任で、資本金は2億円でしたが、政府は日露戦争の戦費の処理と軍拡財源に苦しみ巨額の資金を支出できませんでした。

初代満鉄総裁後藤新平
政府による事業資金は日本興業銀行から社債のかたちで出資され、満鉄への投資は同行の対外投資総額の7割を占めましたが、同行の対外資金調達先は英米両国でした。
後藤新平を満鉄総裁に推挙したのは、台湾総督在任のまま満洲軍総参謀長となった児玉源太郎です。後藤は当初固辞していましたが児玉が急逝し、児玉の遺志を引き継ぐために総裁を引き受けたと云われます。
後藤は満鉄の監督官庁である関東都督府に干渉されて満鉄が自由に活動できなくなることを恐れ、総裁就任の条件として満鉄総裁が関東都督府最高顧問を兼ねることを西園寺公望首相と合意し、官僚は人材確保のため在官のまま満鉄の役職員に就任出来ることも認められました。
後藤総裁は「満鉄十年計画」を策定し、部下の中村是公とともに戦争中に狭軌にして使用した満鉄全線の国際標準軌化、大連―奉天間の複線工事、撫順線と安奉線の改良工事を急速に進め、撫順炭坑の拡張、大連港の拡張、上海航路の開設、鉄道附属地内の各都市の社会資本整備を強力に推進しました。
満鉄は国策を遂行する位置づけで植民地統治をおこない、緊急の事態には武断的行動を援助することを社の方針とし、後藤の発案で1907年に設けられた100名前後の満鉄調査部は当時の日本最高のシンクタンクで、経済調査、旧慣調査、ロシア調査に分かれ、情報収集活動も盛んに行いました。
後藤がまず着手したのは各線の改軌工事でしたが列車の運行を止めずに行うのは容易ではなく、1908年(明治41年)大連―長春間の本線の改築が終わり、不要になった狭軌の機関車は日本に還送されました。
ロシア帝国から引き継いだ鉄道附属地には鉄路を中心とした幅62mの地域の他に、駅ごとに設けられた広大な附属地があって、いずれも治外法権で独占的行政権が与えられていました。
大連、奉天、長春では、未開の付属地に新たに大規模な近代的都市計画が進められ、満鉄社員、日本からの商社員、軍人らの住宅街が建設され、日本人相手の食品店、雑貨店、理髪店、百貨店、宿泊施設、娯楽施設などがつくられ、上下水道や電力、ガスの供給、さらには港湾、学校、病院、図書館などのインフラの整備が進められました。

大連大広場
満鉄は沿線に近代的都市計画による都市建設を行なう
関東軍は日露戦争後にロシアから獲得した租借地の関東州と満鉄付属地の守備をしていた関東都督府陸軍部が前身で、1919年(大正8年)に関東軍として独立しましたが、当初の編制は独立守備隊6個大隊を直轄し、日本内地から2年交代で派遣される駐剳1個師団を指揮下におく小規模な軍でした。
関東軍と満鉄社員の接触は1920年代から始まり、特に関東軍と満鉄調査部ロシア班のスタッフとの交流は早くから行われましたが、満鉄の方が関東軍よりも歴史が古く関東軍を下にみる風潮がありました。
時代が明治から大正になると藩閥政治が政党政治に代わり、1913年(大正2年)12月には第2代総裁中村是公、副総裁国沢新兵衛が更迭され、以後政党内閣が交替する度に総裁以下の幹部が入れ替わる仕組みができました。
1914年第一次世界大戦が勃発し、戦場にならなかったアメリカや日本に大戦景気をもたらし、朝鮮や台湾、満洲を含む中国大陸にも好景気をもたらしました。日本政府は1915年1月中華民国の袁世凱政権に「対華21カ条要求」を突きつけます。
その第2号には旅順・大連(関東州)の租借期限、満鉄・安奉鉄道の権益期限の99年延長が含まれていました。秘密事項の第5号では政治・財政・軍事面で中国政府が日本人顧問を雇用することを求めていましたが、秘密事項が漏洩して排日運動が起こります。
1917年のロシア革命は満洲にも大きな衝撃を与えました。革命後に日米英仏など15か国による革命干渉戦争であるシベリア出兵が行われますが、ロシア革命に対する満鉄の反応は迅速でした。
1917年6月理事の川上俊彦をロシアに派遣して2月革命以降の状況を視察させ、11月に川上が帰国して本野一郎外相に10月革命も含めた「露国視察報告書」を提出、この報告書は当時の日本外交に決定的な役割をもちました。
1926年7月1日中国で蒋介石が北伐を開始し、国民革命軍が南京、上海を占領して1927年5月山東省にせまると、田中義一内閣は同省の在留邦人保護を理由に「山東出兵」を行います。
6月27日から7月7日に東京で「東方会議」が開かれ、出先の軍人、外交官、行政官によって中国情勢が検討されましたが、満蒙政策については奉天軍閥の張作霖を排除して傀儡政権を作る意見と、張作霖勢力と連携して日本の満蒙権益を維持拡大する意見に分かれました。
前者には満洲占領を実行に移そうと云う関東軍の意見が含まれ、後者は田中義一首相兼外相や陸軍省首脳部の意見でした。大陸政策に深くかかわっていた衆議院議員山本条太郎は後者に属していましたが、田中首相は山本を満鉄社長に任じ副社長に山本の腹心の松岡洋右が就任しました。
山本は「満鉄中興の祖」と云われ、持論は「産業立国論」で人口問題、食糧問題、金融恐慌、失業問題の解決のため、鉄道網の拡充を柱とした満洲開発の推進を唱え、満洲を農業、鉱工業、移民の受け入れ地とすべく満鉄を活用しました。
製鉄事業、製油事業の充実、マグネシウム・アルミニウム関連工業ならびに肥料工業の振興、移民拓殖を推し進める一方、張作霖と計5線の路線敷設の基本合意に達しました。
1928年(昭和3年)6月4日満鉄の専用列車が奉天郊外で爆破され、北京から奉天に帰るために乗車していた張作霖が重傷を負い2日後に死亡しました。張作霖の爆殺を企てたのは関東軍の参謀河本大作大佐で、実行したのは独立守備隊の東宮鉄男大尉です。

張作霖
河本らは張作霖を殺害し父親と不和であった息子の張学良を擁立しようとし、東宮は中国人の苦力2人を殺害して爆破を北伐軍の犯行とみせかけようとしました。
田中首相や白川義則陸相は軍の関与が確認されたら厳しく処断するつもりでしたが、上原勇作や閑院宮載仁親王の両元帥はじめ陸軍の長老や首脳は田中、白川の方針に反対で、白川は結局、張作霖の列車が爆破された線路の守備の責任のみを問う行政処分にとどめました。
張学良は蒋介石の国民政府と妥協する途を選び、国民政府側も張学良を東北政務委員会主席委員に任命しました。1928年12月張学良は国民政府の青天白日旗を掲げ、日本側には「満蒙権益」について誰を相手に交渉するのかと云う問題が生じます。
張学良は当時日本との間で最大の懸案事項であった鉄道交渉を、日本側の圧力をかわすため中央政府交渉に移管させようとしており、蒋介石もそれに応じました。
田中外交が行き詰まりをみせるなか、関東軍では石原莞爾を中心に満蒙領有論が具体化されつつあり、石原の論は行政組織のあり方にまで踏み込んだもので、具体性においても計画性においても従前の比ではありませんでした。
満鉄(2)に続きます。