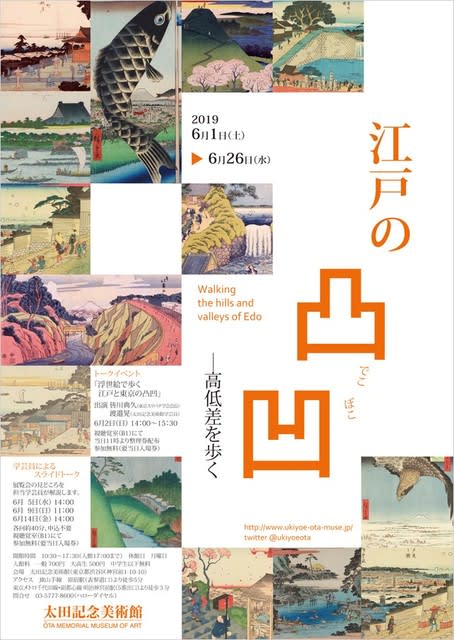アンサンブル・ノマドの今回の定期は「出会いVol.1 高橋悠治と」と題されている。高橋悠治をゲストに招き、その作品を中心にしたプログラム。高橋悠治以外の作品も含まれているが、その選曲も高橋悠治がしたのかもしれない。
1曲目はクセナキスの「モルシマ・アモルシマ」。コンピュータを使った作曲で知られる曲だが、(素人がこういってはなんだが)今の耳で聴くと、ずいぶん控えめな感じがする。
2曲目と3曲目は高橋悠治の作品。2曲目は「飼いならされたアマリリス」。シロフォン独奏の曲だが、あまりにも短いので、よくつかめなかった。3曲目は「チッ(ト)」という曲で、フルートとピアノのための作品。高橋悠治の特徴の一つと思われる「歌の復権」が窺われるが、中断するように終わるその終わり方が唐突だ。
4曲目はストラヴィンスキーの「2台のピアノのためのソナタ」。今までは、煩瑣になるので、演奏者名を省いてきたが、この曲では演奏者名を述べると、第一ピアノは中川賢一、第二ピアノは高橋悠治。流麗な中川賢一のピアノに対して、高橋悠治のピアノは(意図された)たどたどしさがあり、その妙がなんともいえない。
休憩をはさんで5曲目はクレイグ・ペプルズCraig Pepples(1961‐)の「遊ぶサル」Monkeys at Play。この曲がめっぽう面白かった。2台ピアノのための曲だが、音の数が少なくて無心に遊ぶような部分と(それこそ高橋悠治的だ)、音の数が増えて勢いがある部分とが、何度か繰り返される。
この曲では第一ピアノが高橋悠治、第二ピアノが稲垣聡。その高橋悠治のピアノが、ストラヴィンスキーの前曲とは打って変わって気迫があり、お茶目でもあれば、色気もあった。一言でいって、全然老け込んでいなかった。
ペプルズは「30年以上香港に住むアメリカの作曲家」(プログラム・ノート)。当夜はペプルズ本人もステージに現れ、聴衆から盛んな拍手を受けた。
6曲目以降は高橋悠治の作品。6曲目は「星火」Seong-hwa。ヴァイオリン・ソロの曲。野口千代光の演奏がヴィルトゥオーソ的だった。7曲目は「しばられた手の祈り」。ギター・ソロの曲。8曲目は「この歌をきみたちに」。メシアンの「世の終わりのための四重奏曲」のヴァイオリンをヴィオラに替えた編成で、音色がずいぶん落ち着いた感じになる。アンコールに高橋悠治のピアノ独奏で「トロイメライ2012」の冒頭部分が演奏された。
(2019.6.27.東京オペラシティリサイタルホール)
1曲目はクセナキスの「モルシマ・アモルシマ」。コンピュータを使った作曲で知られる曲だが、(素人がこういってはなんだが)今の耳で聴くと、ずいぶん控えめな感じがする。
2曲目と3曲目は高橋悠治の作品。2曲目は「飼いならされたアマリリス」。シロフォン独奏の曲だが、あまりにも短いので、よくつかめなかった。3曲目は「チッ(ト)」という曲で、フルートとピアノのための作品。高橋悠治の特徴の一つと思われる「歌の復権」が窺われるが、中断するように終わるその終わり方が唐突だ。
4曲目はストラヴィンスキーの「2台のピアノのためのソナタ」。今までは、煩瑣になるので、演奏者名を省いてきたが、この曲では演奏者名を述べると、第一ピアノは中川賢一、第二ピアノは高橋悠治。流麗な中川賢一のピアノに対して、高橋悠治のピアノは(意図された)たどたどしさがあり、その妙がなんともいえない。
休憩をはさんで5曲目はクレイグ・ペプルズCraig Pepples(1961‐)の「遊ぶサル」Monkeys at Play。この曲がめっぽう面白かった。2台ピアノのための曲だが、音の数が少なくて無心に遊ぶような部分と(それこそ高橋悠治的だ)、音の数が増えて勢いがある部分とが、何度か繰り返される。
この曲では第一ピアノが高橋悠治、第二ピアノが稲垣聡。その高橋悠治のピアノが、ストラヴィンスキーの前曲とは打って変わって気迫があり、お茶目でもあれば、色気もあった。一言でいって、全然老け込んでいなかった。
ペプルズは「30年以上香港に住むアメリカの作曲家」(プログラム・ノート)。当夜はペプルズ本人もステージに現れ、聴衆から盛んな拍手を受けた。
6曲目以降は高橋悠治の作品。6曲目は「星火」Seong-hwa。ヴァイオリン・ソロの曲。野口千代光の演奏がヴィルトゥオーソ的だった。7曲目は「しばられた手の祈り」。ギター・ソロの曲。8曲目は「この歌をきみたちに」。メシアンの「世の終わりのための四重奏曲」のヴァイオリンをヴィオラに替えた編成で、音色がずいぶん落ち着いた感じになる。アンコールに高橋悠治のピアノ独奏で「トロイメライ2012」の冒頭部分が演奏された。
(2019.6.27.東京オペラシティリサイタルホール)