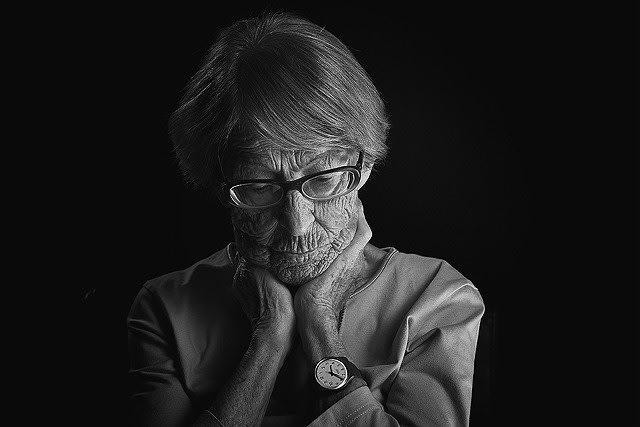7月の読響の定期は諸事情により振り替えた。振替先は、日程の都合で、同月の日曜マチネーにした。ルドヴィク・モルローLudovic Morlotという未知の指揮者のサマーコンサートのようなプログラム。モルローは1973年フランス生まれ。2011年からシアトル響の音楽監督を務めている。
プログラム前半はガーシュイン2曲。まず「キューバ序曲」。ラテン系のノリのよい曲だが、演奏は今一つだった。どこがどうと指摘できるものではなかったが、全体的に弾けたところがなく、もったりしていた。
次は「ラプソディー・イン・ブルー」。ピアノ独奏が小曽根真なので、これに期待していたが、どういうわけか、小曽根のソロが大人しく聴こえた。小曽根が乗ったときのノリのよさはこんなものではないと、わたしは心中で呟いた。
アンコールが演奏された。それが驚きだった。コントラバスの石川滋が前に出てきて、小曽根とジャズ・セッションを始めた。ソフィスティケートされた品のよいジャズ。読響のソロ・コントラバス奏者がジャズもできるとは‥と仰天した。曲はミルト・ジャクソンの「バグズ・グルーヴ」という曲。
話は脱線するが、もう10年以上も前に、年末年始をベルリンで過ごしたことがある。大晦日にコーミッシェ・オーパーのオペレッタを観にいった。途中休憩に入ったら、ホワイエでパーティーが始まった。だれでも参加できる。食べ物と飲み物もふんだんにある。そのうちジャズ演奏が始まった。オーケストラのメンバーによるジャズ。会場は大いに盛り上がった。それを想い出した。
プログラム後半は、ドビュッシーの「牧神の午後への前奏曲」、エネスコの「ルーマニア狂詩曲第1番」、ラヴェルの「ダフニスとクロエ」第2組曲。ドビュッシーとラヴェルの両曲ではフルート・ソロが入るが、フルート独奏は首席のドブリノヴ。何といったらよいか、ノーブルな音と演奏で、わたしは初めてこの奏者の個性がつかめた。
ただ、全体的には、やはり、もったりした感が否めなかった。きちんと仕事はしているのだが、そこを超える鮮烈さが出てこなかった。
モルローってこういう指揮者なのだろうかと思い、翌日NMLを検索したら、何枚ものCDが入っていた。その中からデュティユーの「メタボール」を聴いてみた(オーケストラはシアトル響)。精彩に富んだ演奏で、イメージがまったく違った。
(2018.7.29.東京芸術劇場)
プログラム前半はガーシュイン2曲。まず「キューバ序曲」。ラテン系のノリのよい曲だが、演奏は今一つだった。どこがどうと指摘できるものではなかったが、全体的に弾けたところがなく、もったりしていた。
次は「ラプソディー・イン・ブルー」。ピアノ独奏が小曽根真なので、これに期待していたが、どういうわけか、小曽根のソロが大人しく聴こえた。小曽根が乗ったときのノリのよさはこんなものではないと、わたしは心中で呟いた。
アンコールが演奏された。それが驚きだった。コントラバスの石川滋が前に出てきて、小曽根とジャズ・セッションを始めた。ソフィスティケートされた品のよいジャズ。読響のソロ・コントラバス奏者がジャズもできるとは‥と仰天した。曲はミルト・ジャクソンの「バグズ・グルーヴ」という曲。
話は脱線するが、もう10年以上も前に、年末年始をベルリンで過ごしたことがある。大晦日にコーミッシェ・オーパーのオペレッタを観にいった。途中休憩に入ったら、ホワイエでパーティーが始まった。だれでも参加できる。食べ物と飲み物もふんだんにある。そのうちジャズ演奏が始まった。オーケストラのメンバーによるジャズ。会場は大いに盛り上がった。それを想い出した。
プログラム後半は、ドビュッシーの「牧神の午後への前奏曲」、エネスコの「ルーマニア狂詩曲第1番」、ラヴェルの「ダフニスとクロエ」第2組曲。ドビュッシーとラヴェルの両曲ではフルート・ソロが入るが、フルート独奏は首席のドブリノヴ。何といったらよいか、ノーブルな音と演奏で、わたしは初めてこの奏者の個性がつかめた。
ただ、全体的には、やはり、もったりした感が否めなかった。きちんと仕事はしているのだが、そこを超える鮮烈さが出てこなかった。
モルローってこういう指揮者なのだろうかと思い、翌日NMLを検索したら、何枚ものCDが入っていた。その中からデュティユーの「メタボール」を聴いてみた(オーケストラはシアトル響)。精彩に富んだ演奏で、イメージがまったく違った。
(2018.7.29.東京芸術劇場)