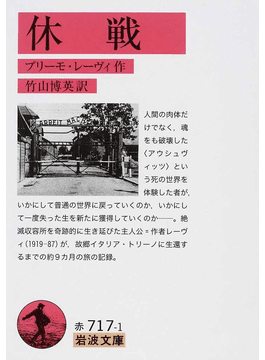自死した財務省職員・赤木俊夫氏の手記と遺書への6人の方々のコメントが、今週の週刊文春に載っている。それらのコメントから、人それぞれの温度差が窺える。取材に答えた各人の発言がどの程度記事になったのか、そしてそれは正確に切り取られたものか――そういったことはわからないが、ともかく記事になったコメントは、各人のスタンスをある程度浮き彫りにする。
一番おもしろかったのは、衆院議員の石破茂氏のコメントだ。まず印象的なことは、筋が通っていること。どんなときにも筋が通ったことを言うのは(今の政界では)貴重な資質だと思う。改憲論者である石破氏は、わたしとは意見を異にするが、それでも石破氏は自分の意見を正々堂々と述べる点で信頼できる。
石破氏は、3月23日の参院予算委員会で安倍首相と麻生財務大臣が「再調査はしない」と答弁したことについて、こう言っている。「(引用者注:赤木氏の手記には財務省の報告書にはなかった点が含まれているが)にもかかわらず「再調査はしない」としてしまえば、「手記には価値がない」と言っているように受け止められても仕方ない。こうした態度が、亡くなった職員の奥さまを始めとするご遺族にどう思われるのか。安倍首相や麻生大臣には、もう少し、部下の死に寄り添うお気持ちを示していただければと思います。」。このような心の機微にふれる部分が、安倍首相や麻生大臣の答弁には欠けていた。
石破氏は、「総理から改ざんについて指示があったとは考えられません。では佐川氏はどんな理由で改ざんを指示したのか、その胸の裡は、亡くなった職員のかたも知り得なかったでしょうが、佐川氏は未だにその説明をしないままです。」と言っている。たしかに首相は、指示はしていないだろうが、だれがどう動くか(=財務省に圧力をかける)はわかっていたはずだ。石破氏も、だれがどう動いたか、わかっているのだろう。
元東京地検特捜部検事で弁護士の郷原信郎氏はこう言っている。「おそらく佐川さんは、直接ここをこう改ざんしろと指示したり、自ら手を下したりはしていません。原則論を唱えただけ。(引用者注:財務省の)調査にもそう弁解したのでしょう。原則論を示して、実行行為は部下におしつける。」と。役人の世界を少しでも知っている者なら、想像に難くない事柄だ。
ひと味違う観点からは、英「エコノミスト」誌の東京特派員、デイビッド・マクニール氏がこう言っている。「「忖度」という言葉に代表されるように、日本語には、言葉によらないコミュニケーションが存在します。同時に、社会の摩擦を和らげるため、事実を明らかにしないという手法を取るのも日本人の特徴です。」と。外から見た日本人の特性が鮮明に言い表されている。
一番おもしろかったのは、衆院議員の石破茂氏のコメントだ。まず印象的なことは、筋が通っていること。どんなときにも筋が通ったことを言うのは(今の政界では)貴重な資質だと思う。改憲論者である石破氏は、わたしとは意見を異にするが、それでも石破氏は自分の意見を正々堂々と述べる点で信頼できる。
石破氏は、3月23日の参院予算委員会で安倍首相と麻生財務大臣が「再調査はしない」と答弁したことについて、こう言っている。「(引用者注:赤木氏の手記には財務省の報告書にはなかった点が含まれているが)にもかかわらず「再調査はしない」としてしまえば、「手記には価値がない」と言っているように受け止められても仕方ない。こうした態度が、亡くなった職員の奥さまを始めとするご遺族にどう思われるのか。安倍首相や麻生大臣には、もう少し、部下の死に寄り添うお気持ちを示していただければと思います。」。このような心の機微にふれる部分が、安倍首相や麻生大臣の答弁には欠けていた。
石破氏は、「総理から改ざんについて指示があったとは考えられません。では佐川氏はどんな理由で改ざんを指示したのか、その胸の裡は、亡くなった職員のかたも知り得なかったでしょうが、佐川氏は未だにその説明をしないままです。」と言っている。たしかに首相は、指示はしていないだろうが、だれがどう動くか(=財務省に圧力をかける)はわかっていたはずだ。石破氏も、だれがどう動いたか、わかっているのだろう。
元東京地検特捜部検事で弁護士の郷原信郎氏はこう言っている。「おそらく佐川さんは、直接ここをこう改ざんしろと指示したり、自ら手を下したりはしていません。原則論を唱えただけ。(引用者注:財務省の)調査にもそう弁解したのでしょう。原則論を示して、実行行為は部下におしつける。」と。役人の世界を少しでも知っている者なら、想像に難くない事柄だ。
ひと味違う観点からは、英「エコノミスト」誌の東京特派員、デイビッド・マクニール氏がこう言っている。「「忖度」という言葉に代表されるように、日本語には、言葉によらないコミュニケーションが存在します。同時に、社会の摩擦を和らげるため、事実を明らかにしないという手法を取るのも日本人の特徴です。」と。外から見た日本人の特性が鮮明に言い表されている。