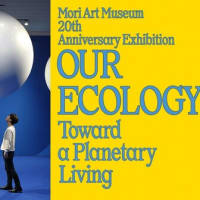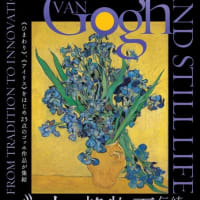マリー・ジャコが読響の定期を振った。1990年パリ生まれ。2023年からウィーン響の首席客演指揮者、24年からデンマーク王立歌劇場の首席指揮者、25年からケルン放送響の首席指揮者に就任。ヨーロッパのメジャーなポストを席巻中だ。
プログラムは20世紀前半の特徴ある曲を並べたもの。1曲目はプロコフィエフの「3つのオレンジへの恋」組曲。カラフルな音色で鮮やかな演奏だ。明るい感性が息づいている。力みなくオーケストラを鳴らす。集中力が途切れない。指揮者としての力量の発露が感じられる。
それにしてもこの曲は面白い曲だ。プロコフィエフはオペラというジャンルにじつに手の込んだ音楽を書いたものだと感嘆する。わたしは一度このオペラを観たことがある(ベルリンのコーミッシェオーパーでアンドレアス・ホモキの演出だった)。音楽もストーリーもモダンで奇抜なので驚いた。あのときの興奮がよみがえる。
2曲目はラヴェルのピアノ協奏曲。ピアノ独奏は小曽根真。小曽根は第1楽章の一部と第2楽章の冒頭でかなり崩した演奏をした。それはこの曲のジャズからの影響を明かしたともいえるが、一方で、オーケストラとかみ合わなかったこと、また音色の魅力に欠けたことで演奏全体は低調だった。なお小曽根はアンコールにコントラバスの首席奏者の大槻健とのデュオで「A列車で行こう」を演奏した。そのほうが演奏に精彩があり、音色にも魅力があった。
3曲目はプーランクの組曲「典型的な動物」。ラ・フォンテーヌの寓話をバレエ化した作品なので、人間の行いにたいする辛辣さがあるのだろう。オーケストラ編成がプーランクには珍しく3管編成が基本の大編成なのが目を引く。第1曲「夜明け」と第6曲「昼餐」の暗い音色に作曲当時の時代背景(ナチス・ドイツのフランス侵攻=パリ陥落)が感じられる。また第3曲「男とふたりの愛人」は若いころのバレエ音楽「牝鹿」にそっくりだが、「牝鹿」の軽快さはなく、どこか重い。
4曲目はクルト・ヴァイルの交響曲第2番。3曲目までのフランス音楽とはちがい、色彩感を失った渋い音色になる。せわしなく動きまわり、落ち着きがない音楽だ。ヴァイルがナチス・ドイツから逃れてパリで書いた曲だ。当時のヴァイルの心境が反映されているのだろう。演奏は水際立っていた。リズムに弾みがあり、アンサンブルも精緻だ。ジャコの指揮のもとで読響がのびのびと演奏していたように思う。第1楽章にはトランペットとチェロのソロがあり、第2楽章にはオーボエとトロンボーンのソロがあるが、いずれも情感たっぷりな演奏だった。
(2024.3.12.サントリーホール)
プログラムは20世紀前半の特徴ある曲を並べたもの。1曲目はプロコフィエフの「3つのオレンジへの恋」組曲。カラフルな音色で鮮やかな演奏だ。明るい感性が息づいている。力みなくオーケストラを鳴らす。集中力が途切れない。指揮者としての力量の発露が感じられる。
それにしてもこの曲は面白い曲だ。プロコフィエフはオペラというジャンルにじつに手の込んだ音楽を書いたものだと感嘆する。わたしは一度このオペラを観たことがある(ベルリンのコーミッシェオーパーでアンドレアス・ホモキの演出だった)。音楽もストーリーもモダンで奇抜なので驚いた。あのときの興奮がよみがえる。
2曲目はラヴェルのピアノ協奏曲。ピアノ独奏は小曽根真。小曽根は第1楽章の一部と第2楽章の冒頭でかなり崩した演奏をした。それはこの曲のジャズからの影響を明かしたともいえるが、一方で、オーケストラとかみ合わなかったこと、また音色の魅力に欠けたことで演奏全体は低調だった。なお小曽根はアンコールにコントラバスの首席奏者の大槻健とのデュオで「A列車で行こう」を演奏した。そのほうが演奏に精彩があり、音色にも魅力があった。
3曲目はプーランクの組曲「典型的な動物」。ラ・フォンテーヌの寓話をバレエ化した作品なので、人間の行いにたいする辛辣さがあるのだろう。オーケストラ編成がプーランクには珍しく3管編成が基本の大編成なのが目を引く。第1曲「夜明け」と第6曲「昼餐」の暗い音色に作曲当時の時代背景(ナチス・ドイツのフランス侵攻=パリ陥落)が感じられる。また第3曲「男とふたりの愛人」は若いころのバレエ音楽「牝鹿」にそっくりだが、「牝鹿」の軽快さはなく、どこか重い。
4曲目はクルト・ヴァイルの交響曲第2番。3曲目までのフランス音楽とはちがい、色彩感を失った渋い音色になる。せわしなく動きまわり、落ち着きがない音楽だ。ヴァイルがナチス・ドイツから逃れてパリで書いた曲だ。当時のヴァイルの心境が反映されているのだろう。演奏は水際立っていた。リズムに弾みがあり、アンサンブルも精緻だ。ジャコの指揮のもとで読響がのびのびと演奏していたように思う。第1楽章にはトランペットとチェロのソロがあり、第2楽章にはオーボエとトロンボーンのソロがあるが、いずれも情感たっぷりな演奏だった。
(2024.3.12.サントリーホール)