(原題:Cabaret )71年作品。私は“午前十時の映画祭”にて今回初めてスクリーン上映に接することが出来た。元ネタのブロードウェイミュージカルは今でも世界中で上演されているほど有名だが、この映画版は当時としてはかなり野心的な体裁で、そのあたりが評価され米アカデミー監督賞などの各種アワードを獲得している。ただし、今観て面白いと言えるかどうかは、意見が分かれるところだろう。
1931年のベルリン。アメリカから一旗揚げようとやってきた娘サリー・ボウルズは、彼の地の有名キャバレー“キットカットクラブ”の専属歌手として毎晩ステージに立っていた。ある日、イギリスから来た大学院生ブライアン・ロバーツがサリーの下宿に引っ越してくる。博士号を取得するまでの間、生活のためにドイツで英語を教えるのだという。
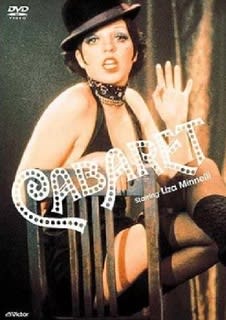
ブライアンのことが気になったサリーは彼を誘惑しようとするが、彼は何やら“問題”を抱えているらしく、上手くいかない。一方、サリーの友人であるフリッツ・ヴェンデルは裕福なユダヤ人のナタリア・ランダウアーに恋するが、宗教的な事情により今ひとつ踏み込めないでいた。やがて時代はヴァイマル共和政からナチス専制に移行。ベルリンの街にも不穏な空気が漂い始める。
通常、ミュージカル映画はストーリー展開の中で歌や踊りが挿入され、楽曲がドラマの一部として機能しているケースが大半だ。しかし本作はミュージカル場面は劇中での“キットカットクラブ”の舞台に限定されており、歌や踊りはそれ自体の役割しか付与されていない。いわば普通の歴史物の小道具として楽曲が存在しているに過ぎず、ストーリーを追うことが映画の主眼になっている。
ならばその筋書きは面白いのかというと、残念ながら個人的にはそう思えない。各登場人物が持ち合わせている苦悩や生き辛さ、暗さを増す時代の移ろいは、確かにヘヴィで真正面から描く価値はある。しかし、現時点で見れば掘り下げは不十分だ。特にブライアンが感じているジェンダーのディレンマは、表面的にしか描かれない。製作時期を考えれば仕方がないのかもしれないが、映画がこのモチーフを中途半端なままで終わらせているのは不満だ。
さらに“キットカットクラブ”の舞台のシーンにかなりの尺を当てなければならないため、ドラマが停滞する傾向がある。ボブ・フォッシーの演出は“当時としては斬新だったのだろう”というレベルで、あまり画面が弾まない。主演のライザ・ミネリはさすがの存在感だが、共感できるようなキャラクターではない。マイケル・ヨークにヘルムート・グリーム、ジョエル・グレイ、マリサ・ベレンソンなどのパフォーマンスも、やはり“当時としては熱演だったのだろう”という感想しか持てない。
1931年のベルリン。アメリカから一旗揚げようとやってきた娘サリー・ボウルズは、彼の地の有名キャバレー“キットカットクラブ”の専属歌手として毎晩ステージに立っていた。ある日、イギリスから来た大学院生ブライアン・ロバーツがサリーの下宿に引っ越してくる。博士号を取得するまでの間、生活のためにドイツで英語を教えるのだという。
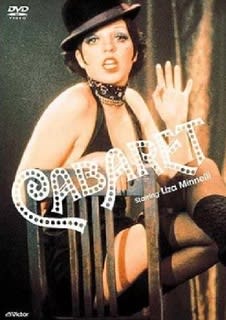
ブライアンのことが気になったサリーは彼を誘惑しようとするが、彼は何やら“問題”を抱えているらしく、上手くいかない。一方、サリーの友人であるフリッツ・ヴェンデルは裕福なユダヤ人のナタリア・ランダウアーに恋するが、宗教的な事情により今ひとつ踏み込めないでいた。やがて時代はヴァイマル共和政からナチス専制に移行。ベルリンの街にも不穏な空気が漂い始める。
通常、ミュージカル映画はストーリー展開の中で歌や踊りが挿入され、楽曲がドラマの一部として機能しているケースが大半だ。しかし本作はミュージカル場面は劇中での“キットカットクラブ”の舞台に限定されており、歌や踊りはそれ自体の役割しか付与されていない。いわば普通の歴史物の小道具として楽曲が存在しているに過ぎず、ストーリーを追うことが映画の主眼になっている。
ならばその筋書きは面白いのかというと、残念ながら個人的にはそう思えない。各登場人物が持ち合わせている苦悩や生き辛さ、暗さを増す時代の移ろいは、確かにヘヴィで真正面から描く価値はある。しかし、現時点で見れば掘り下げは不十分だ。特にブライアンが感じているジェンダーのディレンマは、表面的にしか描かれない。製作時期を考えれば仕方がないのかもしれないが、映画がこのモチーフを中途半端なままで終わらせているのは不満だ。
さらに“キットカットクラブ”の舞台のシーンにかなりの尺を当てなければならないため、ドラマが停滞する傾向がある。ボブ・フォッシーの演出は“当時としては斬新だったのだろう”というレベルで、あまり画面が弾まない。主演のライザ・ミネリはさすがの存在感だが、共感できるようなキャラクターではない。マイケル・ヨークにヘルムート・グリーム、ジョエル・グレイ、マリサ・ベレンソンなどのパフォーマンスも、やはり“当時としては熱演だったのだろう”という感想しか持てない。























