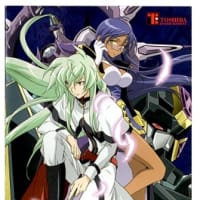冬の街を吹き抜けていった風の足音なんて、もう思い出せない。一時間ほど前に、窓を鳴らすほどしのつく雨脚のリズムも覚えてはいない。カチ、カチッと二分拍子で寸分狂いなく数字の輪を巡る時計の秒針の声も、さらに眠る鼓膜を揺さぶってくれる瀑布のようなアラームも、疲れを理由に聞こえないふりをする。
聞こえるものを選んでいる、というのはかなりぜいたくな生活ではないだろうか。もちろん、今の環境ですべてがそうではない。夜になれば星空のかなり近い静かな山上で、気まぐれに書庫にある洋書をひっぱりだしてきて目をとおしていた日々が、なつかしく思い出される。
音楽をパッケージメディアとして、買う時代は終わるのかもしれないと、ささやかれてきた。たしかに、ネットでもラジオでも気軽に聴ける。正確にいえば、CD音楽はデザインや解説など付加価値で釣られているのだろう。この現代社会、まずどこに行っても音楽に親しまない場所はありえない。
もはや、音楽を買うのではない。沈黙を買うのがむずかしいのだ。
ひとは時としてなぜ沈黙を好むのか。沈黙は無音ではない、聞こえない音に傾聴する静寂の状態だ。つまり、まったくの音の闇を願うのではない。自分のなかに埋められた音楽の再生をうながすために、沈黙は求められる。
喫茶店でくつろいでいたのに、ふいに背後の座席から携帯の着メロが鳴り響き、あたりかまわず大きな声で会話する人びと。ご近所の中学生男子を叱り飛ばす母親の声。その声はもう私の孤独には遠い声である。
何年も雑多な音に慣らされ、新しい声に囲まれてしまっていると、懐かしい声を忘れてしまうことがある。いっぽうで、いちど聞いただけでいやに耳の底にこびりついて、乾いた油のようにもう離れない音もある。そのような音楽はまさに心音さながらにして、自分の生を維持するのに必要で、一時たりとも奪われてはならないのだ。
日ごろあまり音楽も聴かず、教養として義務的に親しんだようなクラシック音楽なぞ、大半は音とタイトルとが一致しない。そんな鈍い音感の持ち主でも、忘れられない一曲がある。
その一曲をはじめて「正式な」音楽として聴いたのは、大学一年生のとき。
教養科目の英語の授業で、ビートルズの曲をヒアリングし書き取ったり、邦訳したりする学びだった。教材として使用されたのは、Hey Jude や Let it Be など有名曲ばかり。ある日、講師が曲をまちがって再生させた。ラジカセから流れてきたのは、レゲエ調の意味不明な、しかし底なしに明るい男の歌声。講師はあわてて、その曲をとめて、テープを差し替えた。その曲が、およそ教育上よろしくはない、男女のたわいもない恋愛について語っていると知ったのは、ごく最近だった。オプラ・ディ、オプラ・ダ…という赤ん坊の難語のような、未開人のくだけた咆哮のような歌い。れっきとしたソングでありながら、意味を解さずにBGMのように聴くのが好きだった。脳だけをほぐして、意識を他人の言葉に奪われないでいられるからだ。
わずか二分ほど耳に飛び込んだだけのこの曲が、私のこころをざわめかせたのは、むろん、それがとても懐かしかったからだった。小学生の私は、油の匂いのしみこんだトラックの助手席で、この歌を浴びるほど聴かされた。土曜や祝日になると、貨物で揚げ物や焼き鳥の移動販売をする父に連れられて、決まった街に行くのだった。自営業の忙しさから家族旅行らしいものもなく育った私にとって、父の仕事にくっついて、遠い街を巡るのが好きだった。そして、その日の仕事の終わりには、売れ残りではなくかならず揚げたてのコロッケを持ってきてくれる。
この音楽がかかるのは、車を停車してから。エンドレステープに録音されたビートルズの曲にのって、いらっしゃいませを連呼し、お買い得食品を並べるセールストークがはじまる。その父の声は、ふだんとは違って、かなり芯の通った親しみ深い男の明るい声で。私はお経のように聞き流していたけれど、家のなかとは違った父のすこし大きな外側を知ったような気がした。
このBGMがトラックの拡声器から響きわたると、夕食前のおかずにしようとする母親が、またおやつにしたい子どもやお年寄りがと、何棟もの団地から多くの客が集まってくるのだった。父の商い中、晴れた日は近くの公園で団地の子どもと遊び、雨曇りの日や寒い日は助手席で漫画を読みふけっていたりした。夏には強い陽ざしを逃れたのであろう、車窓から迷いこんできた青いバッタと仲良くなって、戯れたりもした。
父が走り売りしていた焼き鳥やコロッケには母の隠し味があって、消費税が導入されても値上げしなかったことから、高齢者や低所得者世帯、母子家庭の多い公営住宅では、評判がかなりよかった。
それからおよそ十年後、父は病に倒れ、Ob-La-Di, Ob-La-Da がこのつつましい生活者の暮らす街外れを賑わせることはなくなった。後年、姉の勤め先の同僚に、子どもの頃、あの音楽を聴くたびに飛び出していって揚げたてのコロッケを買うのを毎週楽しみにしていたと語ってくれた。(拙稿「狐いろの楕円の幸福」参照)だから、ある日を境にして、近所にあの曲が流れなくなったことがとても寂しかったのだと。
あの時代、私とおなじようにあの音楽を聴きなじんだ人は、何人ほどいてくれたのだろう。
父の残したあの商売用のデモテープは、しみついた油が埃を吸って、もはや再生できなかった。レコーダーが販売中止になってもはや聴けないテープをCD-Rに録音するという機器があるというけれど。元々のテープが傷んでしまったので、それは棄てられてしまったのだ。だから、父の声はもう永遠に帰ってこない。死者の面影を辿ることはできる。けれど在りし日の、しかも病に蝕まれていない声を望むことはできないのである。
洋楽に傾倒していたわけでもない父がなぜ、ビートルズのその曲を選んだのか、さだかではない。その理由をもう訊ねることはできない。私は独り勝手にその曲がなにかとても意味のある曲ではないかと踏んでいたのに、歌詞をしらべていささか拍子抜けしてしまった。それはふつうの恋人が出会って、子どもが生まれてというたわいもない家庭像がつづられているだけ。けれど聴けば陽気になってしまう歌。Ob-La-Di, Ob-La-Da, Life goes onと力を込めて発せられるかけ声は、肩を落として生きるような現代人へのエールのように思われる。
暇さえあれば、そのサビのフレーズがいつも頭のなかでリフレインする。私はその音を沈黙につつまれた時間で、記憶のレコーダーにかけて再生するのである。ラッパのような口からファンファーレのように弾けていくあの調子の Ob-La-Di, Ob-La-Da、そのおどけた旋律のなかに失われた声が潜んでいる。それは私が心音のように体内に埋め込んでいる声だ。なぜなら、私の鼓動の音源、存在の半分は、その声の主から分けあたえられたものだからである。
たまに自動車のCMでもかかっていたりして、立ち止ってしまう。だが、どんなCDを買っても、その曲にはビートルズの声しか収録していないことが、私にはますます悲しい。私の Ob-La-Di, Ob-La-Da は、一曲しかないのだ。
【〇九年一月二十六日記事を加筆修正】