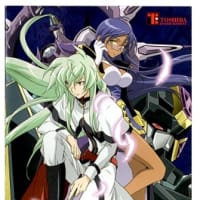夏は灯籠流しや花火など、なんとなく火をつかう行事が多く感じられる季節です。
本日は100万人のキャンドルナイトの日ということで。電気を消したら点けてみたいものの話などを。クリスマスツリーなんぞ点けて楽しむのもいいかと思うのですけれど。エコロジーじゃないって?炎を使うよりは、安全を重視したとお考えくださいな。
それは子どもの頃に見た灯りの原風景でした。
白い祭壇の両脇に、ぼんぼりが控えています。左右の灯籠は紙に描かれた桜花びらの意匠をぼんやりと透かしています。その光りは、床に桃いろの点描を落としながら、ビオスコープのようにくるくると回っているのです。花びらの影が、畳の床を這っては顔に張りつき、また薄くなって飛んでいくのを、私たちはとてもおもしろがっていました。
祖父母の家ではひな祭りでもないのに、年に数回はこのうつくしいぼんぼりが飾られているのでした。幼い私は、その光りの意味をつゆほどにも知らなかったのでした。その家に百年間の死者が多かったということを。無邪気に法要のあとの座布団を投げあったり、山を崩したりして遊んでいたのです。
私がそのとき知りたかったのは、このきれいな光りがどこから来ているのかということでした。きっとあのぼんぼりの提灯のような部分には、ふしぎな仕掛けがあるに違いないと胸おどらせながら、私はそれを眺めていたのです。
小学生になった私はある日、大人の目を盗んで紙の覆いを外してみました。そこにあったのはプラスティックの燭台。棒のうえにうずらの卵型の炎がちかちか瞬いていたのです。手品のタネを知ってしまったように、とてもがっかりしたのでした。私はもっと神秘的なものを望んでいたのです。
その分解した行灯を直せなくてあとで叱られてしまいました。大人が怒った理由はいわく、死者を悼む気持ちのかけらもない不敬の念なのでした。
秘密を知る前のぼんぼりの光りは、あたかもテレビでみた灯籠流しの映像のように、私の小さな胸に沁みました。亡くしたいのちの数だけ川を流れる灯籠とおなじで、ろうそくが入っていると思い込んでいたのです。人魂のように炎として存在の影をしめしたくて、燃えているのだと。ですから、あのぼんぼりが、おもちゃのような安っぽいろうそくでできていたことに、いたく失望したのです。
いま私の手元には昨日送られた、寂しい夜を埋めてくれる、やさしく幻想的な電気ろうそくがあります。(拙稿「電気じかけのキャンドル」参照)それはインテリアとして最適で、生活を明るくしてくれます。
しかし、風もないのにゆらりゆらりとなびいては照らす、遠い感じのするろうそくは、どことなく涙誘うものでした。
白い装束を着て横たわるからだの前で、夜通し線香の火と灯明が絶えないように番をした夜を思い出したのです。今度こそまちがいなく、眠ったりしないのだと。あのときほど一秒でも多く目覚めていたいと思った日はありませんでした。ろうそくに淡く照らされた眠り顔は能面のように美しかったのです。私はその顔を闇に埋もれさせるのが恐かったのでした。
白い祭壇と花のぼんぼりは、数年前の我が家にもやってきました。あいかわらずおもちゃのろうそくだと思いました。けれど、クリスマスツリーの飾りつけよりも、あのぼんぼりが愛おしくなってしまったのは、たぶんそのときからでした。ひな壇とおなじで、あの白い祭壇をしまい忘れたら、女が不幸になるというのなら、それは百年ぐらい前からの決まり事のように思えてならないのでした。
【〇八年十一月十六日記事を加筆修正】