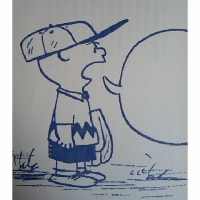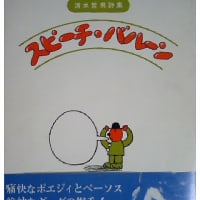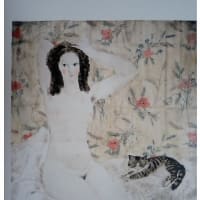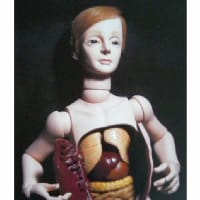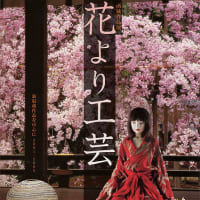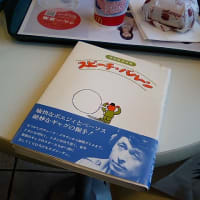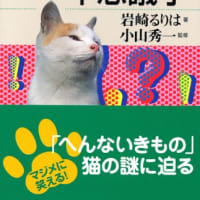擬態語、擬声語、歌なり詩のリズムを醸し出すことばのようです。今朝の日経、詩歌・教養欄では小池光(歌人)さんが佐佐木幸綱さんの新歌集「百年の船」を取り上げていて、幾つかの歌を紹介されています。で、「百年の船」では一貫して短歌に原初の生命感を回復することを試みてきた佐佐木さんが新しいオノマトペに挑戦されているとのことです。
あまり引用すると著作権の問題も発生しそうなので、1首ほど
蛍烏賊とるとつぎつぎととととと
出でゆきにけり船の後姿(うしろで)
解説によると「とととと」は船のエンジン音で五つ目の「と」は助詞として用いられているとのことです。
う~ん、なるほどなあと思ってしまいます。オノマトペ、語感は何だかアイヌ語っぽい(差別語でしたらごめんなさい)のですが、れっきとしたフランス語なんですよね。
で、このコラムを読んでハタと思ったのは現Fへ千月話子さんが投稿された詩作品「香り 触れよし」を拝見したときに感じ入ったオノマトペの効果的な使い方です。
「香り 触れよし」は小詩集、ソナチネのスタイルを取られていて4つの詩作品により構成されています。どのようにオノマトペが用いられているか簡単にご紹介しますと
「黄 緑」では
柚子ぽんぽん/柚子とんとん
ひらひら させて/はらひら させて
「白 壇」では
ふわら ふわら
「和三盆」の
もぎゅる もぎゅる/歯を押し返す
このように詩にリズムを繰り出すって感じで効果的に用いられていて、しかも短調なリズムではなく複雑に変調させているところが非常に素晴らしいと思います。この詩作品何故か現Fではあまり評価されていなくて、とても残念に思います。
千月さんの詩、いつも楽しみにしているのですが千月さんは寡作で在られる故に、新作が待ち遠しくてなりません。
コラムでは、短歌におけるオノマトペの用法について説明されていて「同じ二音を繰返す+助詞(例:わんわんと)」、「三音を繰返す+助詞(カランコロンと)」5音、7音と分節化するのがオノマトペの基本とのことです。
千月さんには到底及ばないにしても、オノマトペに挑戦したくなったYockです。
千月話子さん
香り 触れよし
http://po-m.com/forum/myframe.php?hid=747
(現代詩フォーラム)

あまり引用すると著作権の問題も発生しそうなので、1首ほど
蛍烏賊とるとつぎつぎととととと
出でゆきにけり船の後姿(うしろで)
解説によると「とととと」は船のエンジン音で五つ目の「と」は助詞として用いられているとのことです。
う~ん、なるほどなあと思ってしまいます。オノマトペ、語感は何だかアイヌ語っぽい(差別語でしたらごめんなさい)のですが、れっきとしたフランス語なんですよね。
で、このコラムを読んでハタと思ったのは現Fへ千月話子さんが投稿された詩作品「香り 触れよし」を拝見したときに感じ入ったオノマトペの効果的な使い方です。
「香り 触れよし」は小詩集、ソナチネのスタイルを取られていて4つの詩作品により構成されています。どのようにオノマトペが用いられているか簡単にご紹介しますと
「黄 緑」では
柚子ぽんぽん/柚子とんとん
ひらひら させて/はらひら させて
「白 壇」では
ふわら ふわら
「和三盆」の
もぎゅる もぎゅる/歯を押し返す
このように詩にリズムを繰り出すって感じで効果的に用いられていて、しかも短調なリズムではなく複雑に変調させているところが非常に素晴らしいと思います。この詩作品何故か現Fではあまり評価されていなくて、とても残念に思います。
千月さんの詩、いつも楽しみにしているのですが千月さんは寡作で在られる故に、新作が待ち遠しくてなりません。
コラムでは、短歌におけるオノマトペの用法について説明されていて「同じ二音を繰返す+助詞(例:わんわんと)」、「三音を繰返す+助詞(カランコロンと)」5音、7音と分節化するのがオノマトペの基本とのことです。
千月さんには到底及ばないにしても、オノマトペに挑戦したくなったYockです。
千月話子さん
香り 触れよし
http://po-m.com/forum/myframe.php?hid=747
(現代詩フォーラム)