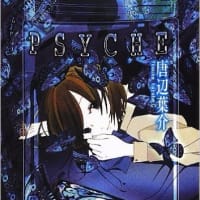2016年2月末日、幻影城の終刊号が発売された。
幻影城といえば70年代後半に創刊し、栗本薫、泡坂妻夫、連城三紀彦、田中芳樹、竹本健治と後に大ヒット作家になる面々を輩出しておきながら、だれもブレイクする前に四年半で潰れた悲運の雑誌。その雑誌の最終号が、2016年にもなって同人誌として刊行。
同人誌といってもページ数は二段組で420ページを超え、編集は当時のスタッフ、値段も税別1500円と商業雑誌と遜色ないクオリティだ。そして作家陣はもちろん当時の幻影城作家陣、その単行本未収録木作品や書きおろし作品であり、中でも特集として組まれたのが近年になった逝去した泡坂妻夫・栗本薫・連城三紀彦の、幻影城出世頭の御三方だ。
と、いうわけで、栗本薫の未読小説があると聞いては読まずにはいられないストーカーは即刻、この幻影城終刊号を確保し、栗本薫関連の収録作に対する感想を述べるのであった。
伊集院大介の追跡
これは『天狼星Ⅱ』のラストで世間から姿を消した伊集院大介を、森薫と山科警視を探してとある事件に遭遇する話。
この作品自体の感想は以前に同人誌に書いたので割愛するが、大介・薫・山科の三人の関係を楽しむうえではなかなかの好篇ではあるが、ミステリーとして面白いものではなく、短編作品としてのクオリティも高いわけではないため、『天狼星Ⅱ』を読んだ後のやきもきした状態でならともかく、いまさらこの一編だけを読むことに価値を見出だせるのは、自分のような「栗本作品を読破しなければならない」という義務感に駆られたフリークだけだと思う。
23世紀のラッシュアワー
この雑誌の(個人的な)目玉作品である、栗本薫が江戸川乱歩賞受賞以前に幻影城に「京堂司」という別名義で発表していたSFショートショート。
題名通り、未来社会における満員電車にまつわる情景を描いている。四つのACTで構成されているが、未来の満員電車というモチーフが同じである以外にストーリーのつながりはなく、ショートショート四篇からなる連作だ。
ACT1~ACT3までは筒井康隆風ドタバタ。面白いというほどではないがつまらないというわけでもなく、ショート・ショートとしてのみたときの偏差値は50といったところか。
ACT4は一転して小松左京風のリリカルショートショート。ぼくは栗本薫のリリカルオチに対して常人より威力が十倍増しになる体質なのでちょっとグッときたけど、客観的に判断して偏差値53くらいの出来だと思う。ただしドタバタ三連発からのリリカルオチにすることによって、この一個一個だとたいして印象に残らないショートショートの価値を一段階引き上げる構成をしているあたり、なかなか小憎らしい。
四編合わせても5ページちょっとで、内容的には筒井康隆と栗本薫の真似っ子をしてみただけなので、わざわざ読むほどの価値があるかは微妙。まあ、そもそも旦那がずっとハヤカワの社員だったんだから、発掘するだけの価値がある作品ならどこかの短編集に収録しているよね、という話ですね。
幻影城にはあと二篇『23世紀のポップス』『革命専科』というSFショートショートも掲載されていたそうだ。率直にいわせてもらえば「全部載せろよファッキン!」という気分でいっぱいである。というか80~90年代のときに発掘して収録しとけよハヤカワ、というか旦那!という気分でもある。
ぼくの探偵小説・新十則
ノックスの十戒が時代とそぐわなくなったいま(1970年代末)、新進気鋭のミステリー作家である栗本薫が新しく考えた新十則がこれだ!というもの。
一つ一つの項目がくだくだと長々しいためいっている意味を見失いがちだが、よく読むと「名探偵が出たほうが楽しいので出すべき」「別に起きないでもいいけど殺人事件起きたほうが楽しくない?」「純文学じゃないんだから美形出せよ」など、要するに「探偵小説とは萌え小説である」という観点で書かれたわりとクリティカルにミステリーマニアに喧嘩を売っているような理論だった。
お~前さ~こんなんいってたらミステリーマニアに嫌われるに決まってんじゃん!と思ううなぎであったが、しかしよく考えたら2010年代なかばを迎えた現代、もはやミステリーはキャラクター文芸がメインストリームとなり、薄い本みたいなシャーロックものが幅をきかせる、この新十則に沿ったような世界となっているではないか……。なんとおそろしい……。
居場所を求めて――ある青い鳥の物語(今岡清)
旦那である今岡清の手による「今だから言えるけどプライベートの薫はこんな感じだったよ」というつらつらとした思い出話。
旦那の口から語られる栗本薫は、一言でいうと「よくいる痛い文芸女子」だ。
いい歳こいて「母ちゃんが弟にかまって私を愛してくれなかった」とぐじぐじし、会話をしているとよくわからんところに地雷があって面倒くさく、定期的に失敗やいやなことを思い出しては「うあああああ」としている、という、別に天才性も特別性も感じない、「クラスに一人くらいはいるよねこういうめんどくさい子」レベルの人だ。
その「特別でなさ」「ありきたりなちょっとダメな子」感がなかなか沁みる、この特集で一番面白い記事だった。
栗本薫さんの多才ぶり(島崎博)
幻影城の編集長が語る当時の栗本薫の思い出話。
編集部に遊びにきたときに半ページの余白を見て「ショートショート書かせて」とその場で10分で書き上げるなど、若かりし頃の栗本薫の輝きぶりがまぶしい。
栗本薫变化(泡坂妻夫)
泡坂妻夫が1983年に雑誌に寄稿したエッセイ。
中途半端な時期に中途半端な関わりの人物が描いたエッセイのため、特に面白い部分はなかった。
ただ1981年の小説現代に載った座談会からの引用で、『絃の聖域』でダイイングメッセージ出したけど辻褄合わないからもういいやって意味なかったことにしたら小松先生に叩かれた、と語っていたくだりはアホらしくも薫イズム満載の創作姿勢である種の勇気が出たので良かった。いや、でもそもそもミステリなんだから最初からダイイングメッセージの意味は決めとけよ……。本当に自分の新十則に沿って萌えと雰囲気だけでミステリ書いてたんだな、薫は(知ってたけど)。
早慶戦の夜に
これは幻影城作家の親睦会である「影の会」のレポートで、各作家が持ち回りでやっていたものの栗本薫担当回。
単に飲み会であの作家はこんな雰囲気だったよ、というだけのもので、特に内容のある文章ではない。
だが、この影の会通信、この終刊号にはすべて載っているのだが、これ全体を含めてとても良い。
どの作家の筆を通じてもわかるのは、幻影城という雑誌が良くも悪くも半分趣味のサークルのような感じで、作家陣はお互いに敬意を払いつつ、探偵小説というひとつの情熱でつながった若さの塊だ、ということだ。まさに青春を切り抜いた肖像。幻影城を総括するこの終刊号でもっとも楽しく、それゆえに切ない、素晴らしいコーナーだ。
他の作家たちから見た栗本薫は、若く、生意気で、しかし小説への情熱と才に満ちた、コケティッシュな魅力をもった少女だ。先の旦那によるエッセイもそうだが、この本においては栗本薫当人の原稿よりも、他者から見た栗本薫の姿のほうが面白い。
弥生美術館 栗本薫/中島梓展について(堀江あき子)
2010年7~9月に弥生美術館でひらかれた栗本薫/中島梓展がどういう経緯で催されたのか、という弥生美術館員によるエッセイ。ただそれだけ。
自分も観に行ったが、しかしもう五年半も前なのかアレ……。時が過ぎるのが早過ぎる……。
この本自体はまだ完読していないが、栗本薫関連に関しては以上。
正直、栗本薫のみを目当てに読みなら微妙。
が、この幻影城終刊号という本自体は、会社の倒産により休刊のままであった雑誌を、関連作家が次々と死に、自身も死を近くに感じられるほどの歳になったかつての編集者が、一念発起して正式に終わらせたという、情念――というよりも執念を感じる良い本だ。連城三紀彦や泡坂妻夫の単行本未収録作品、竹本健治や友成純一の書きおろし短編などもあり、70年代後半の探偵小説とそれを取り巻く空気を愛する人にとってはたまらない一冊なのではなかろうか。
同人誌ゆえに一般流通はしておらず、一部署店での取り扱いのみ。それも発売数日で多くの場所で品薄になっているというから手に入れにくいかもしれないが、好事家の人にとっては見逃せない一冊だと思う。
幻影城といえば70年代後半に創刊し、栗本薫、泡坂妻夫、連城三紀彦、田中芳樹、竹本健治と後に大ヒット作家になる面々を輩出しておきながら、だれもブレイクする前に四年半で潰れた悲運の雑誌。その雑誌の最終号が、2016年にもなって同人誌として刊行。
同人誌といってもページ数は二段組で420ページを超え、編集は当時のスタッフ、値段も税別1500円と商業雑誌と遜色ないクオリティだ。そして作家陣はもちろん当時の幻影城作家陣、その単行本未収録木作品や書きおろし作品であり、中でも特集として組まれたのが近年になった逝去した泡坂妻夫・栗本薫・連城三紀彦の、幻影城出世頭の御三方だ。
と、いうわけで、栗本薫の未読小説があると聞いては読まずにはいられないストーカーは即刻、この幻影城終刊号を確保し、栗本薫関連の収録作に対する感想を述べるのであった。
伊集院大介の追跡
これは『天狼星Ⅱ』のラストで世間から姿を消した伊集院大介を、森薫と山科警視を探してとある事件に遭遇する話。
この作品自体の感想は以前に同人誌に書いたので割愛するが、大介・薫・山科の三人の関係を楽しむうえではなかなかの好篇ではあるが、ミステリーとして面白いものではなく、短編作品としてのクオリティも高いわけではないため、『天狼星Ⅱ』を読んだ後のやきもきした状態でならともかく、いまさらこの一編だけを読むことに価値を見出だせるのは、自分のような「栗本作品を読破しなければならない」という義務感に駆られたフリークだけだと思う。
23世紀のラッシュアワー
この雑誌の(個人的な)目玉作品である、栗本薫が江戸川乱歩賞受賞以前に幻影城に「京堂司」という別名義で発表していたSFショートショート。
題名通り、未来社会における満員電車にまつわる情景を描いている。四つのACTで構成されているが、未来の満員電車というモチーフが同じである以外にストーリーのつながりはなく、ショートショート四篇からなる連作だ。
ACT1~ACT3までは筒井康隆風ドタバタ。面白いというほどではないがつまらないというわけでもなく、ショート・ショートとしてのみたときの偏差値は50といったところか。
ACT4は一転して小松左京風のリリカルショートショート。ぼくは栗本薫のリリカルオチに対して常人より威力が十倍増しになる体質なのでちょっとグッときたけど、客観的に判断して偏差値53くらいの出来だと思う。ただしドタバタ三連発からのリリカルオチにすることによって、この一個一個だとたいして印象に残らないショートショートの価値を一段階引き上げる構成をしているあたり、なかなか小憎らしい。
四編合わせても5ページちょっとで、内容的には筒井康隆と栗本薫の真似っ子をしてみただけなので、わざわざ読むほどの価値があるかは微妙。まあ、そもそも旦那がずっとハヤカワの社員だったんだから、発掘するだけの価値がある作品ならどこかの短編集に収録しているよね、という話ですね。
幻影城にはあと二篇『23世紀のポップス』『革命専科』というSFショートショートも掲載されていたそうだ。率直にいわせてもらえば「全部載せろよファッキン!」という気分でいっぱいである。というか80~90年代のときに発掘して収録しとけよハヤカワ、というか旦那!という気分でもある。
ぼくの探偵小説・新十則
ノックスの十戒が時代とそぐわなくなったいま(1970年代末)、新進気鋭のミステリー作家である栗本薫が新しく考えた新十則がこれだ!というもの。
一つ一つの項目がくだくだと長々しいためいっている意味を見失いがちだが、よく読むと「名探偵が出たほうが楽しいので出すべき」「別に起きないでもいいけど殺人事件起きたほうが楽しくない?」「純文学じゃないんだから美形出せよ」など、要するに「探偵小説とは萌え小説である」という観点で書かれたわりとクリティカルにミステリーマニアに喧嘩を売っているような理論だった。
お~前さ~こんなんいってたらミステリーマニアに嫌われるに決まってんじゃん!と思ううなぎであったが、しかしよく考えたら2010年代なかばを迎えた現代、もはやミステリーはキャラクター文芸がメインストリームとなり、薄い本みたいなシャーロックものが幅をきかせる、この新十則に沿ったような世界となっているではないか……。なんとおそろしい……。
居場所を求めて――ある青い鳥の物語(今岡清)
旦那である今岡清の手による「今だから言えるけどプライベートの薫はこんな感じだったよ」というつらつらとした思い出話。
旦那の口から語られる栗本薫は、一言でいうと「よくいる痛い文芸女子」だ。
いい歳こいて「母ちゃんが弟にかまって私を愛してくれなかった」とぐじぐじし、会話をしているとよくわからんところに地雷があって面倒くさく、定期的に失敗やいやなことを思い出しては「うあああああ」としている、という、別に天才性も特別性も感じない、「クラスに一人くらいはいるよねこういうめんどくさい子」レベルの人だ。
その「特別でなさ」「ありきたりなちょっとダメな子」感がなかなか沁みる、この特集で一番面白い記事だった。
栗本薫さんの多才ぶり(島崎博)
幻影城の編集長が語る当時の栗本薫の思い出話。
編集部に遊びにきたときに半ページの余白を見て「ショートショート書かせて」とその場で10分で書き上げるなど、若かりし頃の栗本薫の輝きぶりがまぶしい。
栗本薫变化(泡坂妻夫)
泡坂妻夫が1983年に雑誌に寄稿したエッセイ。
中途半端な時期に中途半端な関わりの人物が描いたエッセイのため、特に面白い部分はなかった。
ただ1981年の小説現代に載った座談会からの引用で、『絃の聖域』でダイイングメッセージ出したけど辻褄合わないからもういいやって意味なかったことにしたら小松先生に叩かれた、と語っていたくだりはアホらしくも薫イズム満載の創作姿勢である種の勇気が出たので良かった。いや、でもそもそもミステリなんだから最初からダイイングメッセージの意味は決めとけよ……。本当に自分の新十則に沿って萌えと雰囲気だけでミステリ書いてたんだな、薫は(知ってたけど)。
早慶戦の夜に
これは幻影城作家の親睦会である「影の会」のレポートで、各作家が持ち回りでやっていたものの栗本薫担当回。
単に飲み会であの作家はこんな雰囲気だったよ、というだけのもので、特に内容のある文章ではない。
だが、この影の会通信、この終刊号にはすべて載っているのだが、これ全体を含めてとても良い。
どの作家の筆を通じてもわかるのは、幻影城という雑誌が良くも悪くも半分趣味のサークルのような感じで、作家陣はお互いに敬意を払いつつ、探偵小説というひとつの情熱でつながった若さの塊だ、ということだ。まさに青春を切り抜いた肖像。幻影城を総括するこの終刊号でもっとも楽しく、それゆえに切ない、素晴らしいコーナーだ。
他の作家たちから見た栗本薫は、若く、生意気で、しかし小説への情熱と才に満ちた、コケティッシュな魅力をもった少女だ。先の旦那によるエッセイもそうだが、この本においては栗本薫当人の原稿よりも、他者から見た栗本薫の姿のほうが面白い。
弥生美術館 栗本薫/中島梓展について(堀江あき子)
2010年7~9月に弥生美術館でひらかれた栗本薫/中島梓展がどういう経緯で催されたのか、という弥生美術館員によるエッセイ。ただそれだけ。
自分も観に行ったが、しかしもう五年半も前なのかアレ……。時が過ぎるのが早過ぎる……。
この本自体はまだ完読していないが、栗本薫関連に関しては以上。
正直、栗本薫のみを目当てに読みなら微妙。
が、この幻影城終刊号という本自体は、会社の倒産により休刊のままであった雑誌を、関連作家が次々と死に、自身も死を近くに感じられるほどの歳になったかつての編集者が、一念発起して正式に終わらせたという、情念――というよりも執念を感じる良い本だ。連城三紀彦や泡坂妻夫の単行本未収録作品、竹本健治や友成純一の書きおろし短編などもあり、70年代後半の探偵小説とそれを取り巻く空気を愛する人にとってはたまらない一冊なのではなかろうか。
同人誌ゆえに一般流通はしておらず、一部署店での取り扱いのみ。それも発売数日で多くの場所で品薄になっているというから手に入れにくいかもしれないが、好事家の人にとっては見逃せない一冊だと思う。