依頼品の繕いの続きです。
ベースを整えた上に本漆の黒艶漆を塗って。
こちらの茶碗、黄色味を帯びた個所の下側部分に透明の釉薬がなくなっている部分に気が付いて、その部分にも波型に漆を塗って。
その次は、銀の丸粉を蒔いて(私が使っているのは少し粒子の大きな3号です)。
丸粉は消粉と違って、しっかりと漆の中に入り込んでいます。
こんな風に仕上がりました。
二日ほど置いて、十分に漆を乾かして。
丸粉の場合は消粉と違って、この後金属粉を固める「粉固め」という工程があります。
生漆をテレピンで薄めたものを塗ります。
筆では後の処理が面倒で、僅かな部分ですので棉棒で間に合います。
塗った後はさっそくキムワイプでふき取って。
この作業を漆を乾かしてから、1日1回あと2回実施して。
今の時期、気温も湿度も高くて、漆が早く乾いてくれて有難いですね。
さあ、最後の仕上げです。
まずは石粉で繕った個所を指でしっかりと磨いて。
そして、いよいよ鯛の牙(たいき)の出番です。
きれいな光沢が現れます。
仕上がりました。
丸粉は消粉と違って、強固な仕上がりとなります。
波型の部分も面白いですね。


























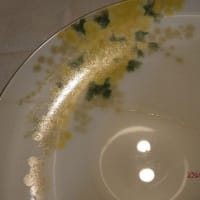


※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます