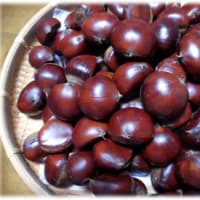清々しい週明けの初夏の朝、晴れ のち 曇り、最高気温28℃(-1)、洗濯指数100ジーンズなど厚手のものもOK、との予報。
朝からガンガン照りの日差しで、午前中には歩いていると汗がにじむほどに気温が上がったのですが、まだまだ初夏の陽気、全般的には過ごしやすい一日となった北摂。


今日も朝一、整骨院で施療してもらい、少しスッキリなって…、前かがみの歩き方を改善させ無ければ、おしりから背中、肩、首にかけての負担はなくならないようです。
努力目標の一つですが、腹筋背筋が弱ってしまっているので、まずそちらの改善が先決…。
体がだるく倦怠感、少しスッキリさせても、完全な改善にならず、1700歩の歩きとベランダでの日光浴で、あとはごろごろの生活…、全くの病人状態です。
今日の1枚の写真は、細い枝や葉が見えなくなるほど白い多数の花を咲かせ、枝垂れる姿がとても見事な「コデマリ(小手毬)」です。
「コデマリ(小手毬、学名:Spiraea cantoniensis)」は、バラ科シモツケ属の落葉低木で中国(中南部)原産で、日本では帰化植物。名前は小さな手毬状の花姿に由来します。
日本でも古くから知られており、「スズカケ(鈴掛)」の古名があり、江戸時代の初めには庭木などに利用されていました。
現在でも庭木として親しまれているほか、切り花としても広く利用されます。
細い枝や葉が見えなくなるほど白い多数の花を咲かせ、枝垂れる姿がとても見事です。
花言葉は「友情」「優雅」「上品」です。
☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆
明日5月14日(辛亥 かのとい 先勝)
●「温度計の日」
1686(貞享3)年、温度計(水銀温度計)の発明者のドイツの物理学者、ガブリエル・ファーレンハイトが生まれた日にちなんで制定されました。
ファーレンハイトの名に中国で華倫海の字を当てたことから°F=華氏になりました。
華氏温度は、塩化アンモニウムを寒剤として得られる当時人間が作り出せた最低温度を0度、人間の平均体温を96度とし、その間を等分して得られます。
この温度目盛りによると、水が凍る温度は32度、沸騰する温度は212度となります。
華氏温度はファーレンハイトが1724年に発表し、主にアメリカ・カナダ・イギリスなどで使われています。
華氏温度(°F)を摂氏温度(℃)に換算する公式は、C=5(F-32)÷9です。
●「種痘記念日」
1796(寛政8)年、イギリスの外科医ジェンナーが初めて種痘の接種に成功しました。
種痘の登場以前は、天然痘は最も恐ろしい病気の一つでした。
発症すると、高熱に引き続いて、全身に化膿性の発疹ができるため、運良く治った人もあばた面になりました。
以前より、一度天然痘にかかった人は、二度とこの病気にならないことが知られていました。
また、ジェンナーは、乳絞りの女性から牛痘にかかると天然痘にはかからないことをききました。
そこで、牛痘にかかった乳絞りの女性サラ・ネルムズの手の水疱からとった膿を、近所に住んでいた8歳の男児フィップスの腕に接種しました。
10日後に発症しましたがすぐに治癒し、その後天然痘を接種しても感染しませんでした。
この実験は、学会には認められませんでしたが、ジェンナーは貧しい人たちに無料で種痘の接種を行い、次第に認められるようになりました。
天然痘による死亡者は劇的に減少し、1979(昭和54)年10月末に世界保健機構(WHO)によって根絶が確認されました。
●「ゴールドデー」
新年度、新学期など、ゴールデンルーキーとして入った新人たちに期待とエールを込めて先輩からゴールドキウイフルーツを贈る日です。
五月病に負けずに甘くてポリフェノールたっぷりのゴールドキウイで元気になって欲しいと、この記念日を制定したのはゼスプリ インターナショナル(ジャパン)リミテッドです。
●「合板の日」
丸太を薄くむいた板(単板)を貼り合わせて作る合板。天然木に比べ、狂いにくく、ほとんど伸び縮みしない合板を通して、自然と人が共存共栄できる豊かな社会づくりに貢献することを目的に2007年にオープンした特定非営利活動法人「木材・合板博物館」が制定しました。
日付は日本における合板の創始者、故浅野吉次郎氏の誕生日1859年(安政6年)5月14日から。
●「三社祭」
浅草神社例大祭のことで、東京を代表する祭りです。期間中には毎年200万人もの人々が見物に訪れます。
浅草の伝統的な町並みの中を、氏子各町の神輿が威勢よく練り歩くところが見どころの一つで、江戸っ子の気質が堪能出来ます。
浅草神社 東京都台東区浅草
●「中将姫大会式」
和歌山県有田市 雲雀山得生寺で行われます。中将姫(ちゅうじょうひめ)といえば奈良の「當麻寺」と思うのですが、ここは、右大臣藤原豊成公の姫「中将姫」が、継母のにくしみによって雲雀山に捨てられた遭難の旧跡で姫の殺害を命じられた刺客伊藤春時が、姫の徳に打たれて改心し、創建したと伝えられています。
姫は少女時代をこの寺で過ごし、17歳の時に當麻寺で出家。曼荼羅を織り、25菩薩(ぼさつ)の来迎を受けて往生したとされています。
毎年5月14日は中将姫の命日で、金色の菩薩面や衣装をまとった地元小学生ら25人の二十五菩薩が、本堂と開山堂を結ぶ長さ30メートルの朱塗りの特設回廊を練り歩き、姫が極楽浄土へ導かれる様子を再現した、来迎会式(県指定無形文化財)が修せられ大賑いを呈します。
奈良県の當麻寺でも毎年5月14日に練供養会式が営まれ、正しくは聖衆来迎練供養会式と呼ばれます
得生寺(とくしょうじ) 和歌山県有田市糸我町中番229 TEL0737-88-7110
当麻寺(たいまでら) 奈良県葛城市当麻1263 TEL0745-48-2001
![]() 「にほんブログ村」ランキング参加中です。
「にほんブログ村」ランキング参加中です。
今回は4563話 よかった!と思われたらポチっとお願いします。