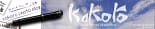蒼鉛の空へ
永訣の朝
~宮沢賢治~
けふのうちに
とほくへいってしまふ わたくしの いもうとよ
みぞれがふって おもては へんにあかるいのだ
(あめゆじゅ とてちて けんじゃ)
うすあかく いっさう陰惨(いんざん)な雲から
みぞれは びちょびちょ ふってくる
(あめゆじゅ とてちて けんじゃ)
青い蓴菜(じゅんさい)の もやうのついた
これらふたつの かけた陶椀(たうわん)に
おまへが たべる あめゆきを とらうとして
わたくしは まがった てっぽうだまのやうに
この くらい みぞれのなかに 飛びだした
(あめゆじゅ とてちて けんじゃ)
蒼鉛(さうえん)いろの 暗い雲から
みぞれは びちょびちょ 沈んでくる
ああ とし子
死ぬといふ いまごろになって
わたくしを いっしゃう あかるく するために
こんな さっぱりした雪のひとわんを
おまへは わたくしに たのんだのだ
ありがたう わたくしの けなげな いもうとよ
わたくしも まっすぐに すすんでいくから
(あめゆじゅ とてちて けんじゃ)
はげしい はげしい 熱や あえぎの あひだから
おまへは わたくしに たのんだのだ
銀河や 太陽、気圏(きけん)などと よばれたせかいの
そらからおちた 雪の さいごのひとわんを・・・・・・
・・・ふたきれの みかげせきざいに
みぞれは さびしく たまってゐる
わたくしは そのうへに あぶなくたち
雪と水との まっしろな 二相系(にさうけい)をたもち
すきとほる つめたい雫に みちた
この つややかな 松のえだから
わたくしの やさしい いもうとの
さいごの たべものを もらっていかう
わたしたちが いっしょに そだってきた あひだ
みなれた ちゃわんの この藍のもやうにも
もう けふ おまへは わかれてしまふ
(Ora Orade Shitori egumo)
ほんたうに けふ おまへは わかれてしまふ
ああ あの とざされた病室の
くらい びゃうぶや かやのなかに
やさしく あをじろく 燃えてゐる
わたくしの けなげな いもうとよ
この雪は どこを えらばうにも
あんまり どこも まっしろなのだ
あんな おそろしい みだれた そらから
このうつくしい 雪が きたのだ
(うまれで くるたて
こんどは こたに わりやの ごとばかりで
くるしまなあよに うまれてくる)
おまへが たべる この ふたわんの ゆきに
わたくしは いま こころから いのる
どうかこれが天上のアイスクリームになって
おまへと みんなとに 聖い資糧をもたらすやうに
わたくしの すべての さいはひをかけて ねがふ
心象スケッチ『春と修羅』より-「永訣の朝」-
無声慟哭
- 『永訣の朝』 宮沢賢治詩集 -
![]()
風の旅人
おくのほそ道
月日は百代の過客にして、行きかふ年も又旅人なり。
舟の上に生涯をうかべ馬の口をとらへて老いをむかふる者は、
日々旅にして旅を栖とす。
古人も多く旅に死せるあり。
予もいずれの年よりか、片雲の風にさそはれて漂白の思ひやまず、・・・・・
松尾芭蕉

芭蕉の言葉-「おくのほそ道」をたどる-
春の空
春の雲がゆっくりと流れていきます
あれほどたくさん積もった雪は
もはや跡形もなく大地に染み込み
その大地からは春の息吹が薫ってきます
どこからかヒバリの鳴き声が聞こえ
まだ少し冷たい風が
頬をキリリと撫でていきました
春が
始まりました
森の人~ 春の空 ~
森山直太朗
冬茜
久しぶりの冬茜(ふゆあかね)の中、雀たちが冬木立に群れていました。
野に生きる鳥たちは、体一つで飢えと寒さに立ち向かっています。
食料の少ない冬。彼等は一粒の糧を探すにも雪をかき分け必死です。
時には危険を冒し、人間の近くにも接近しなくてはいけません。
そして夕方には、凍てつく冬の夜を越えるために安全な宿を探さなくてはならないのです。
冬は、成鳥だけでなく幼鳥や老鳥に対しても容赦なくその厳しさを与えます。
その冬の厳しさに耐え、過酷な状況を乗り越えたものにだけ、春が訪れるのです。
そんな鳥たちは冬の束の間、時折見せるこの綺麗な冬茜をどのように感じているのでしょうか。
人と同じく、冬を越える勇気をもらっているのでしょうか。
冬はまだまだ続くことを、鳥たちも知っているのです。

おすすめbook100冊
世界の約束
宮崎駿さんの「ハウルの動く城」を見ました。
相変わらずの素晴らしい作品に感動しました。
宮崎アニメを見るといつも感じるのですが、「風」がとても効果的に使われているように思います。
少女の髪をさらさらと撫でる風。傍らの花を揺らす風。草原をざわざわと走る風。
大切なものを見つけたときに吹いてくる心の風。(室内なのに何故か風が吹いてくるのです)
(^^;)
アニメの中の様々な場面で、いつも風が吹いています。
そしてその風が吹いているシーンが心の琴線を微かに揺らし、何かしらの「懐かしさ」を感じます。
そんな、微かに懐かしいシーンが宮崎アニメの魅力だと思っています。
これもまた、「風の記憶」・・・かな?
(10月16日の記述「風の記憶」参照)
今回の「ハウルの動く城」では物語の最後に、自分の心を取り戻したハウルにソフィーが言った言葉が、心に残りました。
『そうよ、こころって、重いのよ。♪』
それと、このアニメの主題歌「世界の約束」がとても気に入っています。(DVDのラストシーンだけ何回もリピートして聞いています。(^^ゞ )
谷川俊太郎さんの詩と木村弓さんの曲、久石譲さんの編曲、どれもが素晴らしい。
そして何よりも倍賞千恵子さんの歌声が、まるで風のようです。
→ 「世界の約束」
僕らの写した写真が、僕らの目にした風景の
特別な力を写し取っていることは、極めて希である。
僕らがそのときに目にして、そのときに心をかきたてられたものは、
もう戻ってはこない。
写真はそこにあったそのままのものを写し取っているはずなのに、
そこからは何か大事なものが決定的に失われている。
でも、それもまた悪くはない。
僕は思うのだけれど、人生においてもっとも素晴らしいものは、
過ぎ去って、もう二度と戻ってくることのないものなのだから。
-村上春樹-
「使いみちのない風景」より
風を超えて
秋も終わりに近づくと、徐々に風が強く吹くようになる。
風は木々から枯れ葉をもぎ取り、上空では大きな雨雲をぐんぐん流してゆく。
ザーッと急に雨が降ったかと思うとすぐに止み、風に流されてゆく巨大な雲々の彼方には、吸い込まれるぐらいに真っ青な空が顔をのぞかせる。
陽の光はぶ厚い雲の固まりに遮られ、四方に放射するライトのようにめまぐるしく回りの風景を変えてゆく。
人々は、そんな光景に急き立てられるように、冬の準備に取りかかる。
陽の光を見つけて飛び出してきたように飛ぶ鳥が、一羽。
残り少ない光を目差して風を超える鳥の姿が、秋の終焉を告げている。
蝉しぐれ
故 藤沢周平さんの名作「蝉しぐれ」が映画化されて、10月1日から全国上映されています。
庄内を舞台にした藤沢作品の映画としては、山田洋次監督の「たそがれ清兵衛」、同監督の「隠し剣、鬼の爪」に続き三作品目、監督は黒土三男さんです。
山田洋次監督の「たそがれ清兵衛」は素晴らしい映画でした。藤沢文学の世界を見事に表現されていた名作だったと思います。DVDを買って、何度も見ています。
黒土三男監督の今回の作品はどうでしょうか。期待で胸がいっぱいなのですが、実はまだ見に行っていません。
本当であればすぐにでも見に行きたいのですが、何となく見たくない気持ちも少しあるのです。
その理由は・・・、「蝉しぐれ」だからです。
私は藤沢文学ファンです。特に「蝉しぐれ」は、何度と無く読み返したほど思い入れの深い作品です。だから、自分の中の「蝉しぐれ」をこわされたくない、なんて思ってしまうのです。
「蝉しぐれ」は、藤沢作品の中でも特に人気がありますから、私と同じような人も多くいるのだと思いますし、それを承知で黒土監督は映画化したのですから、きっと期待を裏切らない映画になっているのだと思います。が、やはり見たいけど、見たくないと思ってしまいます。
まあ、なんだかんだ言っても、見に行くんですけどね。(^^ゞ
藤沢周平さんの作品を読んで感じること、それは、
まっすぐに生きることの美しさ、平凡に生きることの偉大さ、人を大切に想う心の優しさ、目立つことのない本当の勇気の気高さ、風土と共に生きることの大切さ、かけがえのない命を精一杯生きることの尊さ、です。
そして、詩情豊かな美しい日本語で表現された、美しい日本の四季折々の風景。
藤沢さんが描かれているもの、それは、
現代の日本人が失ってしまった「精神の豊かさを大切にする日本人の心」だと思うのです。
是非、多くの若い人に読んでもらいたい作家です。
(参考)
「蝉しぐれ」公式HP → http://www.semishigure.jp/
「たそがれ清兵衛」公式HP → http://www.shochiku.co.jp/seibei/
つるおか旅読本HP → http://www.tsuruokakanko.com/index.html
海坂藩研究所HP → http://www.e-yamagata.com/unasaka/index.htm
庄内空港HP → http://www.shonai-airport.co.jp/
鶴岡市HP → http://www.city.tsuruoka.yamagata.jp/