一昨日、県立ミュージアムの後、三越高松店に行ってきました。
5階の美術画廊で、何か素敵な展覧会してないかな~?と覗いてみたんです。
よく、知らずに行って、ラッキー ってことがあったので。
ってことがあったので。
すると、なんと今回もしてました

『アイリーン・フェットマン絵画展』
しかも初日だったみたいです。
お名前から男性かな?と思ったんですが、55歳の女性の画家さんだそうで、
ウクライナ生まれで、現在カルフォルニア在住の方だそうです。
窓越しの風景画が多かったんですが、
私のツボど真ん中
以前ここでギーデサップさんという方の絵画展をしていて、すっかりファンになったんですが、
彼女の絵も優しい感じの絵が多く、
その方とどっち?というほど大好きになりました。
一番気に入ったのは、この絵。
・・・実は版画なんですが、どう見ても油絵です。
最近版画の技術が進んでいるから、ここまで素晴らしいものが出来るんだそうです。

夏の日差しを浴びた青い海。
白いカーテン。
ライムと氷水の入ったピッチャーとグラス。
…周りの水滴で、冷たさが伝わってきます。
外の暑さと対照的な室内の涼しげな空気。
優しい風さえ感じられます。
全体を白っぽい色調でまとめた優しい絵 で、
で、
出来ることなら、部屋に飾ってずっと見ていたい~ (´ー`*)。・:*:・☆
(´ー`*)。・:*:・☆
原画は本当に美しくて、感動があるんですが、
パンフレットの写メなので、素晴らしさの半分も伝えられないのがくやしいです。
光の表現がとっても上手なんですが
ルノワールとも誰ともまた違う画風っていうのかな?
とにかくいっぺんで好きになりました。
もう一枚、見た事ない絵で心を奪われたのが、雨粒に煙る窓ガラスのある風景。
全体が優しいグレージュ色・・・でも、地味じゃない。
本当にその窓辺にいるような写実的な絵。
残念ながら、パンフレットにその絵がなかったんですが、
こんな感じです。

そして、この絵。

「サンライズ+サンセット」という題の
同じ場所から見た”明け方の海”と”夕暮れの海”を表現した2枚セットの油絵です。
打ち寄せる波の一瞬を切り取ったような絵で、
これも波打ち際に立って見ている錯覚に陥ります。
光の表現が本当に見事です
他の絵も色がキレイで、光の当たっているところの表現がうまくて、
本当の景色を見ているかのよう。
夜や雨の光の表現が秀逸なギーデサップさんに対して、
昼間の自然の中の光を描いたら
誰にも負けないと言っていいと思うアイリーン・フェットマンさん。
雨の表現もギーデサップさんとまた違う優しい表現で、
彼女の世界に引き込まれます。
そして、もうひとつ
フィットマンさんの描く子どもが、また可愛らしいんです。
さすが女性~
見つめるまなざしに、母のような愛を感じます。

そして、どの絵にもストーリーがあるんです。

子どもの見た目の可愛らしさだけでなく、
その行動の中の愛らしさまでも表現している絵は
初めて見ました

今回も、こんな素敵な絵画展を見れるという機会に巡りあえて
私ってつくづく本当に幸せ者だな~と思います。
アイリーン・フェットマンさんの絵画展は、
17日(月)まで、高松三越で開かれています。
もし行く機会があれば、是非~
私も、近ければまた何度でも見に行きたい、そんな素晴らしい絵画展です。
<追記>
Youtubeがありましたので、よかったら・・・
(埋め込みがどうもうまくいかないので、このURLで飛んでみてください)
https://www.youtube.com/watch?v=QRYUwFlWMD4
私のパンフの写メよりは、素晴らしさをお伝えできるかも?
5階の美術画廊で、何か素敵な展覧会してないかな~?と覗いてみたんです。
よく、知らずに行って、ラッキー
 ってことがあったので。
ってことがあったので。すると、なんと今回もしてました


『アイリーン・フェットマン絵画展』
しかも初日だったみたいです。
お名前から男性かな?と思ったんですが、55歳の女性の画家さんだそうで、
ウクライナ生まれで、現在カルフォルニア在住の方だそうです。
窓越しの風景画が多かったんですが、
私のツボど真ん中

以前ここでギーデサップさんという方の絵画展をしていて、すっかりファンになったんですが、
彼女の絵も優しい感じの絵が多く、
その方とどっち?というほど大好きになりました。
一番気に入ったのは、この絵。
・・・実は版画なんですが、どう見ても油絵です。
最近版画の技術が進んでいるから、ここまで素晴らしいものが出来るんだそうです。

夏の日差しを浴びた青い海。
白いカーテン。
ライムと氷水の入ったピッチャーとグラス。
…周りの水滴で、冷たさが伝わってきます。
外の暑さと対照的な室内の涼しげな空気。
優しい風さえ感じられます。
全体を白っぽい色調でまとめた優しい絵
 で、
で、出来ることなら、部屋に飾ってずっと見ていたい~
 (´ー`*)。・:*:・☆
(´ー`*)。・:*:・☆原画は本当に美しくて、感動があるんですが、
パンフレットの写メなので、素晴らしさの半分も伝えられないのがくやしいです。
光の表現がとっても上手なんですが
ルノワールとも誰ともまた違う画風っていうのかな?
とにかくいっぺんで好きになりました。
もう一枚、見た事ない絵で心を奪われたのが、雨粒に煙る窓ガラスのある風景。
全体が優しいグレージュ色・・・でも、地味じゃない。
本当にその窓辺にいるような写実的な絵。
残念ながら、パンフレットにその絵がなかったんですが、
こんな感じです。

そして、この絵。

「サンライズ+サンセット」という題の
同じ場所から見た”明け方の海”と”夕暮れの海”を表現した2枚セットの油絵です。
打ち寄せる波の一瞬を切り取ったような絵で、
これも波打ち際に立って見ている錯覚に陥ります。
光の表現が本当に見事です

他の絵も色がキレイで、光の当たっているところの表現がうまくて、
本当の景色を見ているかのよう。
夜や雨の光の表現が秀逸なギーデサップさんに対して、
昼間の自然の中の光を描いたら
誰にも負けないと言っていいと思うアイリーン・フェットマンさん。
雨の表現もギーデサップさんとまた違う優しい表現で、
彼女の世界に引き込まれます。
そして、もうひとつ

フィットマンさんの描く子どもが、また可愛らしいんです。
さすが女性~

見つめるまなざしに、母のような愛を感じます。

そして、どの絵にもストーリーがあるんです。

子どもの見た目の可愛らしさだけでなく、
その行動の中の愛らしさまでも表現している絵は
初めて見ました


今回も、こんな素敵な絵画展を見れるという機会に巡りあえて
私ってつくづく本当に幸せ者だな~と思います。

アイリーン・フェットマンさんの絵画展は、
17日(月)まで、高松三越で開かれています。
もし行く機会があれば、是非~

私も、近ければまた何度でも見に行きたい、そんな素晴らしい絵画展です。

<追記>
Youtubeがありましたので、よかったら・・・
(埋め込みがどうもうまくいかないので、このURLで飛んでみてください)
https://www.youtube.com/watch?v=QRYUwFlWMD4
私のパンフの写メよりは、素晴らしさをお伝えできるかも?











 だったんですが、
だったんですが、 と思える作品がいくつかありました。
と思える作品がいくつかありました。





 紅潮した頬
紅潮した頬 光を写す透明肌
光を写す透明肌 ぽっちゃりボディ
ぽっちゃりボディ





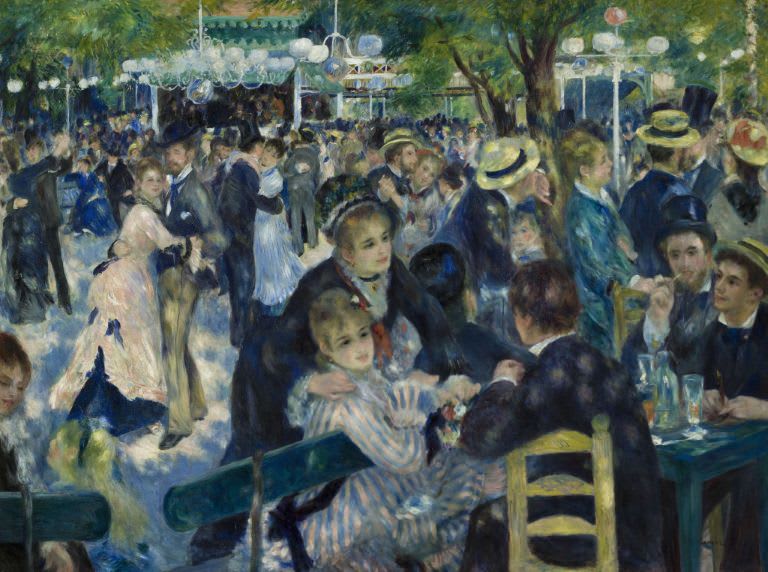

 ネットより
ネットより
 ネットより
ネットより


