
さてさて、継手の二個目の課題は「腰掛け鎌継ぎ」です。
先ずは、スケッチアップのモデルをダウンロードしてください。
これは、継手の中でも一番有名なものじゃないでしょうか?
なんと言っても、プレカットでもこの継手は多く使われていますからね~

蟻継ぎよりは強いですが、追掛け継ぎなどに比べると、強度はあまり期待できません。
それでも、この継手が便利なのは、胴差しなどの部材で、大きさが違うものなどを接合するときなどは比較的簡単にできるからですね。
 昨年のこのブログにて説明しましたが、この継手面白いのは、時代と共に形を変化させてきたことですね。
昨年のこのブログにて説明しましたが、この継手面白いのは、時代と共に形を変化させてきたことですね。
少し、バージョンアップして襟輪を入れると、捻れをさらに防ぐことができます、
どこが違うか解るかな?
ここまでの仕事はあまりお目にかかりませんね~

墨付けのさしがねの合わせ方が少し、難しいかな?

でも馴れるとホント簡単ですよ。
このさしがね使いは今後も多用しますので覚えておいて欲しいものです。
刻みのポイントは滑りこう配です、この部分が上手にできるときは、ノミを良く砥いでいる証拠です、逆にバサける(バサバサになること)人は良くノミを砥いでおきましょうね。

滑りこう配のおかげで、意外と鎌の部分は良く付くのですが、いかんせん腰掛けが目透かしになる方が多いですね、5分(15mm)のさしかね使いがまちまちなのと、横切りが良くないみたいですね~

まぁいつかは上手くなるでしょう。(なるのか?)

おしまい。

先ずは、スケッチアップのモデルをダウンロードしてください。

これは、継手の中でも一番有名なものじゃないでしょうか?
なんと言っても、プレカットでもこの継手は多く使われていますからね~

蟻継ぎよりは強いですが、追掛け継ぎなどに比べると、強度はあまり期待できません。
それでも、この継手が便利なのは、胴差しなどの部材で、大きさが違うものなどを接合するときなどは比較的簡単にできるからですね。
 昨年のこのブログにて説明しましたが、この継手面白いのは、時代と共に形を変化させてきたことですね。
昨年のこのブログにて説明しましたが、この継手面白いのは、時代と共に形を変化させてきたことですね。少し、バージョンアップして襟輪を入れると、捻れをさらに防ぐことができます、
どこが違うか解るかな?
ここまでの仕事はあまりお目にかかりませんね~

墨付けのさしがねの合わせ方が少し、難しいかな?

でも馴れるとホント簡単ですよ。
このさしがね使いは今後も多用しますので覚えておいて欲しいものです。

刻みのポイントは滑りこう配です、この部分が上手にできるときは、ノミを良く砥いでいる証拠です、逆にバサける(バサバサになること)人は良くノミを砥いでおきましょうね。

滑りこう配のおかげで、意外と鎌の部分は良く付くのですが、いかんせん腰掛けが目透かしになる方が多いですね、5分(15mm)のさしかね使いがまちまちなのと、横切りが良くないみたいですね~

まぁいつかは上手くなるでしょう。(なるのか?)

おしまい。



















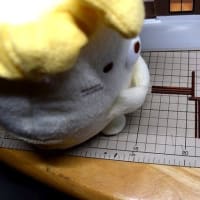

いえ、なってもらわないと困るはず
って、鞭をふるうと、へこたれるんですよね~
大工仕事が上手になるグミとかローソンで売ってないかな~(現実逃避)
材料は何だろう????