法人の解散
法人は解散によって権利能力は消滅し、一切の活動が出来無くなる。民法法人は社会的貢献の達成を目的として成立されるものだが、それだけに解散による社会的影響は大きいものとなる。それ故、法人が所期の目的を達成した場合以外に解散することになるようなことは努々避けられねばなら無いのだ。しかし、奮闘努力空しく、或いは、怠惰や不正の為に解散することになったとしても、社会への迷惑は最小限に抑えられなければなら無い。破産による解散の場合は別として、解散となっても、大抵の場合は残余財産はあるものだ。そこで、破産による以外の事由により、解散しても、利害関係人達への損害を極力避けれた目にも財産関係の清算が完了するまでは、法人の権利能力を消滅させないようしているのだ。以下、民法の条文の順に従って、考察していく。
(法人の解散事由)
①定款又は寄附行為で定めた解散事由の発生、②法人の目的である事業の成功又はその成功の不能、③破産手続開始の決定、④設立の許可の取消し(民法第68条1項各号)。社団法人の解散自由として①総会の決議、②社員が欠けたことが、加えられる(民法第68条2項各号)。ここでの「成功」とは、既にやることが無くなってしまった場合と考える。
(法人の解散の決議)
社団法人は、総社員の四分の三以上の賛成がなければ、解散の決議をすることができない。ただし、定款に別段の定めがあるときは、この限りでない(民法第69条)。
(法人についての破産手続の開始)
法人がその債務につきその財産をもって完済することができなくなった場合には、裁判所は、理事若しくは債権者の申立てにより又は職権で、破産手続開始の決定をする(民法第70条1項)。前項に規定する場合には、理事は、直ちに破産手続開始の申立てをしなければならない(民法第70条2項)。
(法人の設立の許可の取消し)
法人がその目的以外の事業をし、又は設立の許可を得た条件若しくは主務官庁の監督上の命令に違反し、その他公益を害すべき行為をした場合において、他の方法により監督の目的を達することができないときは、主務官庁は、その許可を取り消すことができる。正当な事由なく引き続き三年以上事業をしないときも、同様とする(民法第71条)。
(残余財産の帰属)
解散した法人の財産は、定款又は寄附行為で指定した者に帰属する(民法第72条1項)。定款又は寄附行為で権利の帰属すべき者を指定せず、又はその者を指定する方法を定めなかったときは、理事は、主務官庁の許可を得て、その法人の目的に類似する目的のために、その財産を処分することができる。ただし、社団法人にあっては、総会の決議を経なければならない(民法第72条2項)。それでも、処分し切れ無い財産は、国庫に帰属する。
(清算法人)
解散した法人は、清算の目的の範囲内において、その清算の結了に至るまではなお存続するものとみなす(民法第73条)。
(清算人)
法人が解散したときは、破産手続開始の決定による解散の場合を除き、理事がその清算人となる。ただし、定款若しくは寄附行為に別段の定めがあるとき、又は総会において理事以外の者を選任したときは、この限りでない(民法第74条)。
(裁判所による清算人の選任)
如何しても清算人となる者がないとき、又は清算人が欠けたため損害を生ずるおそれがあるときは、裁判所は、利害関係人若しくは検察官の請求により又は職権で、清算人を選任することができる(民法第75条)。
(清算人の解任)
第七十六条 重要な事由があるときは、裁判所は、利害関係人若しくは検察官の請求により又は職権で、清算人を解任することができる(民法第76条)。「重要な事由」というのは、清算人が、清算人として相応しく無い場合のことを意味します。
(清算人及び解散の登記及び届出)
清算人は、破産手続開始の決定及び設立の許可の取消しの場合を除き、解散後主たる事務所の所在地においては二週間以内に、その他の事務所の所在地においては三週間以内に、その氏名及び住所並びに解散の原因及び年月日の登記をし、かつ、これらの事項を主務官庁に届け出なければならない(民法第77条1項)。清算中に就職した清算人は、就職後主たる事務所の所在地においては二週間以内に、その他の事務所の所在地においては三週間以内に、その氏名及び住所の登記をし、かつ、これらの事項を主務官庁に届け出なければならない(民法第77条2項)。なお、本項の違反に対しては、罰則が適用されます(第84条の3第1項1号)。 前項の規定は、設立の許可の取消しによる解散の際に就職した清算人について準用する(民法第77条3項)。
(清算人の職務及び権限)
清算人の職務は、次のとおりとする。①現務の結了、②債権の取立て及び債務の弁済、③残余財産の引渡し(民法第78条1項)。清算人は、前項各号に掲げる職務を行うために必要な一切の行為をすることができる(民法第78条2項)。
(債権の申出の催告等)
清算人は、その就職の日から二箇月以内に、少なくとも三回の公告をもって、債権者に対し、一定の期間内にその債権の申出をすべき旨の催告をしなければならない。この場合において、その期間は、二箇月を下ることができない(民法第79条1項)。前項の公告には、債権者がその期間内に申出をしないときは、その債権は清算から除斥されるべき旨を付記しなければならない。ただし、清算人は、知れている債権者を除斥することができない(民法第79条2項)。清算人は、知れている債権者には、各別にその申出の催告をしなければならない(民法第79条3項)。第一項の規定による公告は、官報に掲載してする(民法第79条4項)。
(期間経過後の債権の申出)
前条第一項の期間の経過後に申出をした債権者は、法人の債務が完済された後まだ権利の帰属すべき者に引き渡されていない財産(完済後も残っている財産)に対してのみ、請求をすることができる(民法第80条)。
(清算法人についての破産手続の開始)
清算中に法人の財産がその債務を完済するのに足りないことが明らかになったときは、清算人は、直ちに破産手続開始の申立てをし、その旨を公告しなければならない(民法第81条1項)。清算人は、清算中の法人が破産手続開始の決定を受けた場合において、破産管財人にその事務を引き継いだときは、その任務を終了したものとする(民法第81条2項)。前項に規定する場合において、清算中の法人が既に債権者に支払い、又は権利の帰属すべき者に引き渡したものがあるときは、破産管財人は、これを取り戻すことができる(民法第81条3項)。第1項の規定による公告は、官報に掲載してする(民法第81条4項)。
(裁判所による監督)
法人の解散及び清算は、裁判所の監督に属する(民法第82条1項)。裁判所は、職権で、いつでも前項の監督に必要な検査をすることができる(民法第82条2項)。
(清算結了の届出)
清算が結了したときは、清算人は、その旨を主務官庁に届け出なければならない(民法第83条)。
単なる条文の羅列に終始してしまったことを詫びます。今後は、私の書いたノート書きを文章にしてお送りします。










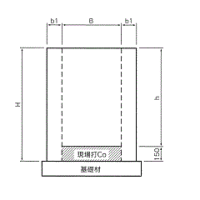









※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます